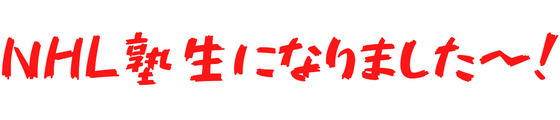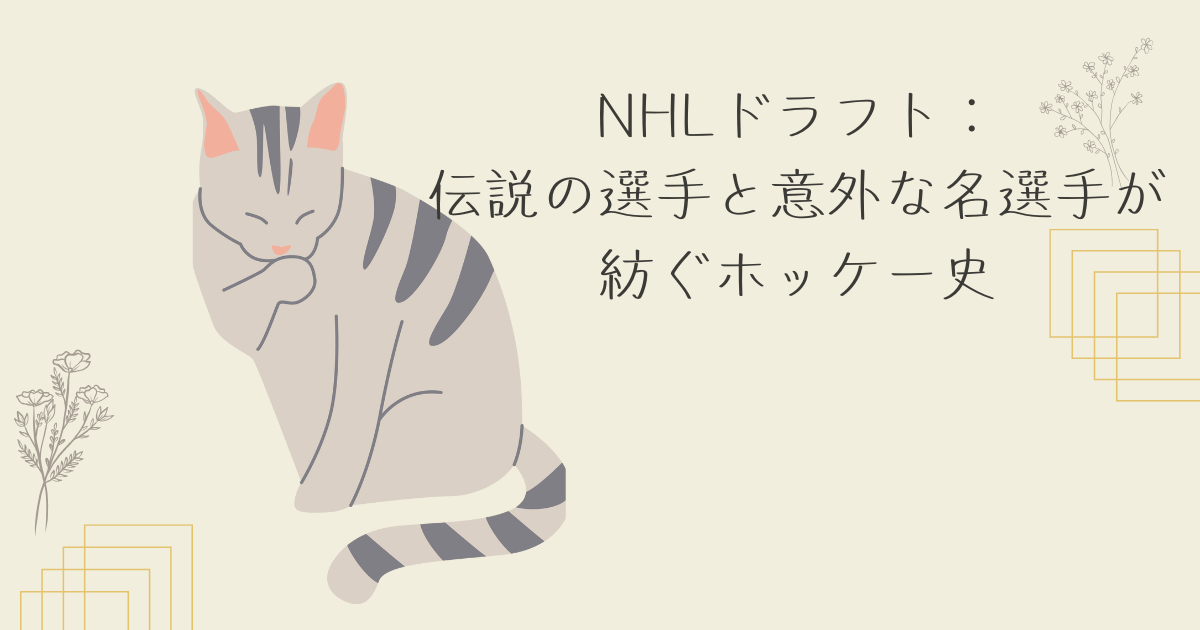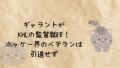- はじめに
- ミスター61と呼ばれる男、ウェイン・シモンズの物語👑
- 「最高の選手」ってどうやって決めるの?🤔
- ドラフト1位の熾烈な戦い、ルミューと新世代の天才たち🔥
- 2位指名も超激戦!マルセル・ディオンとエフゲニー・マルキンの比較🤔
- 輝く個性派選手たち:特異な才能が光る指名選手たち✨
- 7位 バーニー・フェダーコ、C、セントルイス・ブルース(1976年)
- 8位 レイ・ボーク、D、ボストン・ブルーインズ(1979年)
- 15位 マイク・ボッシー、RW、ニューヨーク・アイランダーズ(1977年)
- 17位 ボビー・クラーク、C、フィラデルフィア・フライヤーズ(1969年)
- 21位 ケビン・ロウ、D、エドモントン・オイラーズ(1979年)
- 22位 ブライアン・トロティエ、C、ニューヨーク・アイランダーズ(1974年)
- 29位 ダニー・ゲア、RW、バッファロー・セイバーズ(1974年)
- 30位 ランディ・カーライル、D、トロント・メープルリーフス(1976年)
- 31位 デイブ・タイガー・ウィリアムズ、LW、トロント・メープルリーフス(1974年)
- まとめ
はじめに
NHLのドラフトは、若き才能たちがプロの世界へ飛び込むための、とても大きなイベントです🏒。毎年、1位から数多くの選手が指名されますが、どの順位からも素晴らしい選手が生まれる可能性があります。中には伝説的なキャリアを築く選手もいれば、後にトリビアとして語られるような存在になる選手もいるんです💡。
この記事では、そんなドラフトの各順位を代表する選手たちを、その功績と選定理由とともにご紹介します。なぜその選手がその順位の「最高」と称されるのか。この記事を読めば、NHLドラフトの奥深さと、隠された名選手たちの物語を知ることができるでしょう。
参照記事:ESPN公式サイト「The best NHL draft pick ever at every slot from No. 1 to 224」
ミスター61と呼ばれる男、ウェイン・シモンズの物語👑
今回、まず注目したのが、2007年のドラフトで全体61位で指名されたウェイン・シモンズです。61位という順位は、2巡目の後半に位置するため、一般的にはあまり大きな注目を集めるわけではありません。
しかし、この61位で指名されたすべての選手の中で、彼はNHLでの最多ゴール数(263ゴール)と最多ポイント数(526ポイント)を記録しました。まさに、驚くべき功績ですよね!😳✨
この偉業から、シモンズは「ミスター61」という愛称で呼ばれています。ESPNのインタビューでは、「そう言ってもらえるのは嬉しいね。感謝しているよ」と笑顔で語っていたそうです😊。
彼は「バンクーバーがアナハイム経由で獲得した補償ピック1だったと覚えている」と語りました。彼の記憶は正しくて、その指名には面白い背景があるのです。もともとは、アナハイム・ダックスがコーチのランディ・カーライルを雇ったことへの補償として、バンクーバー・カナックスに送られたピックだったんです。
そのピックはトレード期限にディフェンスのブレント・ソペルとの交換でキングスにトレードされたのです。こうして、ロサンゼルスは61位という遅い2巡目指名で、掘り出し物を手に入れたわけです。キングスにとっては、このドラフト指名が大成功だったと言えるでしょう👑。
「最高の選手」ってどうやって決めるの?🤔
毎年のドラフトのすべての指名順位から、1人以上のNHL選手が生まれています。中には伝説的な選手もいるし、トリビアの答えになるような選手もいます。今年初め、ESPNのベン・ソラック記者は、NFLドラフトの各指名順位を代表する選手を1人ずつ選びました。
今回、NHLドラフトで同じことをやってみようと思ったのです。今回のランキングを作成するにあたって、明確な基準を設けていて、NHLドラフトの各指名順位(1位から224位2まで)を代表する選手を1人ずつ選ぶことにしたんです📝。
対象は、リーグが拡張された1967年以降3(つまり、リーグ拡張後)の選手を対象にランク付けを行っています。
選定の基準は、「最高」を「最も才能がある」と「最も成功した」の組み合わせとして定義し、統計的なインパクト、NHLアワードの受賞歴、キャリアの功績を考慮に入れて「最高」の選手を定義しました。そして、各順位には1人だけ代表選手を選び、同順位は設けませんでした。
また、選定にはいくつかの注意点があります。一度ドラフトされた後に再びドラフトに入った選手については、2度目の指名を基準にしています。評価の対象はNHLでの功績のみです。
最初の100位までの選手については選定理由を詳しく説明し、それ以降は特に議論になりそうな選手や注目すべき選手について、いくつかピックアップして解説しています。他のNHLドラフトと同様に、ここでもトップから始めていきます…。
【追記】今回の記事は、1位の選手の他に、70年代にドラフト指名された上位選手を中心としています。
ドラフト1位の熾烈な戦い、ルミューと新世代の天才たち🔥
ドラフト61位に素晴らしい選手がいる一方で、やはり最も注目されるのはドラフト1位ですよね!🏒1位で指名された選手たちの中で、誰が最高なのか?その議論はとても白熱しているんです。
1位 マリオ・ルミュー、C、ピッツバーグ・ペンギンズ(1984年)
※C=ポジションがセンター。
もし15年前にこのランキングを作っていたとしたら、間違いなくマリオ・ルミューが最高のドラフト1位だと誰もが答えたでしょう。議論の余地はほとんどなかったかもしれません。彼は「ル・マニフィーク(Le Magnifique)」と呼ばれ、その才能は圧倒的でした✨。
怪我や病気4でキャリアが短くなってしまい、プレーしたのはたった915試合でしたが、それでも1,723ポイント(690ゴール、1,033アシスト)という驚異的な記録を残しました。1試合あたりの平均ポイントは1.88で、これはウェイン・グレツキー(1.92)に次ぐ、歴代2位の数字なんです。
しかし、近年、新たな3人の天才選手(3人とも現役)が登場し、この議論を複雑にしました。
アレックス・オベチキン(ワシントン・キャピタルズ、2004年指名)は、NHL史上最多ゴール記録を更新しました。
シドニー・クロスビー(ペンギンズ、2005年指名)は、少なくとも3回のスタンレーカップ優勝を成し遂げ、彼らの世代で最も完成度の高い選手と評価されて引退するでしょう。
コナー・マクデイビッド(エドモントン・オイラーズ、2015年指名)は、すでに5回の得点王と3回のMVPを獲得し、少なくとも600試合以上プレーした選手の中では、1試合あたりの平均ポイントも歴代3位(1.52)という驚くべき記録を持っています。
もちろん、この答えがまだマリオではないと言っている訳ではありません。ただ、マリオ・ルミューである可能性は十分にあると言っているだけです。今はもう、誰が本当に最高のドラフト1位なのか、真剣に話し合うべき時が来たということなんです😊。
2位指名も超激戦!マルセル・ディオンとエフゲニー・マルキンの比較🤔
2位 マルセル・ディオン、C、デトロイト・レッドウィングス(1971年)
1位指名に劣らず、ドラフト2位の「最高の選手」を選ぶのも本当に難しいんです。激しい議論になるでしょう。
この順位からは、ブレンダン・シャナハン(ニュージャージー・デビルズ、1987年)、パトリック・マーロー(サンノゼ・シャークス、1997年)、やダニエル・セディン(カナックス、1999年)のような引退したスターフォワード選手がいます。
アレクサンダー・バーコフ(フロリダ・パンサーズ、2013年)、ガブリエル・ランデスコグ(コロラド・アバランチ、2011年)、ジャック・アイヒェル(バッファロー・セイバーズ、2015年)のような現役のスターフォワード選手もいます。
さらにはクリス・プロンガー(カロライナ・ホエーラーズ、1993年)、ドリュー・ダウティ(ロスアンゼルス・キングス、2008年。現役)、ビクター・ヘドマン(タンパベイ・ライトニング、2009年。現役)のような伝説的なディフェンスマンまで、数々の偉大な選手が輩出されています。
最終的に、この議論はマルセル・ディオンとエフゲニー・マルキン(ペンギンズ、2004年。現役)のどちらが上かという話になりました。
エフゲニー・マルキンは、1,213試合で1,346ポイントを挙げ、ディオンよりも多くの賞(カルダー、コーン・スマイス、ハート、2つの得点王)を獲得しました。
一方、元キングスのスター選手マルセル・ディオンは、1,348試合で1,771ポイントを記録し、その殿堂入りキャリアでの通算ゴール数(731)は史上6位という驚異的な数字を持っています。
ディオンは、キングスに所属していたため、彼の功績が当時は正当に評価されにくかった5という時代背景もあります。時代を考慮すると、本当に甲乙つけがたい選択なんです。多くの正解がある中で、ここではディオンが2位で最も正しい選択だと考えていますが、この差は本当にわずかです。
輝く個性派選手たち:特異な才能が光る指名選手たち✨
ドラフトの後半の順位にも、個性あふれる素晴らしい選手たちがたくさんいます。
7位 バーニー・フェダーコ、C、セントルイス・ブルース(1976年)
この殿堂入りフォワードは、ドラフト7位指名の選手で、唯一1,000ポイントの大台を突破した選手なんです。ブルースでの1,000試合(そしてレッドウィングスで1シーズン)で1,130ポイントを記録しました。クイン・ヒューズ(カナックス、2018年。現役)も一見の価値がありますが、彼にはまだ先が長くありますから…。
8位 レイ・ボーク、D、ボストン・ブルーインズ(1979年)
※D=ポジションがディフェンス。
彼は15回もノリス・トロフィー(「そのシーズン最も優れたディフェンスマン」に贈られる賞)の最終候補に選ばれ、そのうち5回も受賞しました。さらに、ディフェンスマンとしてNHL史上最多の1,579ポイントを記録しているんです。この選出は、リストの中でも特に簡単な判断でしたね!😎
コロラド・アバランチに移籍後、初ゴール!ディフェンスマンとしてNHL史上最多ポイントを記録しただけあって、シュートの正確さは抜群。
15位 マイク・ボッシー、RW、ニューヨーク・アイランダーズ(1977年)
※RW=ポジションが右ウィング。
さて、ここでは議論を歓迎しよう。マイク・ボッシー以外に、ミスター15にふさわしい選手が他に3人います。
ホッケー殿堂入りを果たした、強烈なスラップショットとディフェンスマンとして歴代3位の通算1,274ポイントを記録したアル・マクインズ(カルガリー・フレームス、1981年)。
ホッケー殿堂入りを果たし、1,378試合で1,641ポイントを記録したジョー・サキック(ケベック・ノルディクス=現在のコロラド・アバランチの前身、1987年)。この順位で指名された選手の中ではトップの成績です。
ペンギンズのエリック・カールソン(オタワ・セネターズが指名、2008年)。ホッケー殿堂入りが確実視されており、ノリス・トロフィーを3回受賞しています。
こういった名選手たちとの間で、激しい議論が繰り広げられました。しかし、最終的に選ばれたのは、故マイク・ボッシーなのです。
ホッケー殿堂入りを果たし、怪我でキャリアは短かったものの、752試合で573ゴールを記録し、ウェイン・グレツキーが「史上最高のゴールスコアラーの一人6として語り継がれなければならない」と称賛するほどの選手でした。ゴールを決めることについては894回以上の実績を持つ、グレツキーの言葉ですからね。
17位 ボビー・クラーク、C、フィラデルフィア・フライヤーズ(1969年)
彼は、フィラデルフィア・フライヤーズのチーム精神・美学を体現するような選手7でした。殿堂入りキャリアの1,144試合で1,210ポイントと1,453ペナルティミニッツを記録し、フライヤーズを唯一の2度のスタンレーカップ優勝に導きました。
17位指名選手の中で最も多くのゴール(434)を記録したザック・パリシー(デビルズ、2003年)にも敬意を表します。
21位 ケビン・ロウ、D、エドモントン・オイラーズ(1979年)
これは明らかな選択です。オイラーズ王朝の守備の要として活躍し、スタンレーカップを掲げ(5回優勝)、6度目のカップは、その非公式な延長8ともいえるマーク・メシエ率いる、1994年のニューヨーク・レンジャーズで獲得しました。間違いなく、この順位の代表選手ですね。

70年代NHLを見る機会はYouTubeに限られちゃうんだけど、その中でも、一段と輝きを放っているのが、ロウとメシエの別チームでカップ獲得→しかも6回!だにゃ。ボッシーとトロティエのアイランダーズ4連覇も凄まじいけど、ロウとメシエの6回には叶わない。チーム数も今より少なく、しかも集まった選手が少数精鋭だったNHLで成し遂げたことに意味がある。
22位 ブライアン・トロティエ、C、ニューヨーク・アイランダーズ(1974年)
アイランダーズの4年連続スタンレーカップ優勝(1979~83年)の立役者、MVP級のスター選手として活躍し、その後ペンギンズの連覇(1990~92年)にも貢献しました。524ゴールと1,425ポイントを記録し、ホッケーの殿堂入りを果たしている、文句なしの選択です。
29位 ダニー・ゲア、RW、バッファロー・セイバーズ(1974年)
テッポ・ヌンミネン(ウィニペグ・ジェッツ、1986年)は長寿なキャリア(1988〜2009年までの21年間)を持っており、ステファン・リシェール(モントリオール・カナディアンズ、1984年)は通算421ゴールを記録し、マイク・グリーン(キャピタルズ、2004年)は3シーズンにわたる輝かしい活躍を見せ、ノリス・トロフィーの投票で2度も2位に終わっています。
こういった候補者がいる中で、もし短期間に多くのことを成し遂げた選手を選ぶなら、ダニー・ゲアしかいません。彼はキャリア通算827試合で354ゴールを記録し、50ゴールを2度達成しています(1975–76シーズンと1979–80シーズン)。
ダニーのゴールも凄いんだけど、80年初旬のスーパー・シリーズ、セイバーズvs.CSKAモスクワも興味深い。YouTubeで全編見られますよ。
30位 ランディ・カーライル、D、トロント・メープルリーフス(1976年)
彼は17年間NHLでプレーしたディフェンスマンで、この順位で指名された選手の中で最も多い647ポイントを獲得しました。1980-81シーズンにはペンギンズで83ポイントを挙げ、ノリス・トロフィーを受賞しています。
コーチとしては、HBOの『24/7』でトースターと格闘している姿9で最もよく知られています。
31位 デイブ・タイガー・ウィリアムズ、LW、トロント・メープルリーフス(1974年)
フェリックス・ポトヴィン(メープルリーフス、1990年)とジェイコブ・マークストロム(パンサーズ、2008年)は、31位で指名された興味深いケースを提供する2人のゴールテンダーです。しかし、選ばれたのは「タイガー」ことデイブ・ウィリアムズでした。
彼はグローブを外して喧嘩をしながらも、ポイント(キャリア通算513)を稼ぐという稀なタイプのNHLエンフォーサー10でした。そして、彼がいかに喧嘩が強かったかというと、962試合のキャリアで3,971ペナルティミニッツという、NHL史上最多の記録を持っています。
今のNHLでは、この記録はもう破られないかもしれませんね…😅
まとめ
今回のランキングを通じて、NHLドラフトの各順位が持つストーリーの奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。ドラフト1位の座をめぐる伝説的な議論から、後半の指名順位から生まれた個性豊かな選手たちまで、彼らの功績はホッケーの歴史に深く刻まれています。
統計や受賞歴だけでなく、彼らがキャリアで築いたレガシーこそが、その順位を代表する選手を決める重要な要素なのです。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- 2005年夏、アナハイムが当時バンクーバー傘下AHL・マニトバ・ムースの指揮官だったランディ・カーライルをNHLのヘッドコーチとして招聘した際、当時の「コーチ/幹部引き抜き補償」ルールに基づくピック補償が発生し、バンクーバーは補償パッケージの一部として「アナハイムの2007年ドラフト2巡指名権」を受け取った(2005年8月8日のトレード記録では、バンクーバーが2008年3巡をアナハイムへ差し出し、見返りに“2006年3巡+アナハイムの2007年2巡”を受領したことが明記されている)。
その後、2007年のトレードデッドライン当日(2月26日)、バンクーバーはロサンゼルスからDFブレント・ソペルを獲得する見返りとして、この「アナハイム由来の2007年2巡指名権」と2008年4巡をキングスへ譲渡。複数の報道・公式記録が、この“ソペル対2007年2巡+2008年4巡”という枠組みを確認している。
↩︎ - 「224」という数字は、単純明快に言えば現行のドラフト制度の掛け算の結果。現在のNHLエントリードラフトは1回の大会で7ラウンドあり、リーグには32チームが存在するため、各ラウンドで各チームが1回ずつ指名すると標準的に7 × 32 = 224の指名枠になる(各チームが1ラウンドにつき1つの指名権を持つという基本ルール)。
この「7ラウンド制」は2005年の制度変更以降継続しているもので、それ以前は拡張や運用方針の変化によりラウンド数は大きく変わっていた(かつては二十数ラウンドあった年もあれば、ごく少ないラウンドだった年も)。一方で「32チーム」という数もリーグ拡大(例:ベガス、シアトルの加入)で決まるため、ラウンド数やチーム数が変われば総指名数も当然変動する。
↩︎ - NHLは1942年から「オリジナル・シックス」と呼ばれる6チーム体制が25年以上続いていたが、1960年代半ばにはテレビ放映権の再獲得をはじめとする外部からの圧力が高まり、これまで拡張に消極的だったリーグも方針を一変させていく。
実際、1963年にはウェスタン・ホッケー・リーグ(WHL)がメジャーリーグ化を狙う動きを見せ、テレビ放映の権利や将来的な市場獲得を巡る危機感が拡張への転換点となった。
その結果、新たなテレビ契約の条件にもなっていたこともあり、1967年の1967-68シーズンにNHLは一挙に6チームを加え、リーグを12チーム体制に拡大。この拡張はプロスポーツ史上最大の単年拡張とも評され、カリフォルニア・シールズ(後のオークランド/カリフォルニア・ゴールデン・シールズ)、ロサンゼルス・キングス、ミネソタ・ノーススターズ、フィラデルフィア・フライヤーズ、ピッツバーグ・ペンギンズ、セントルイス・ブルースの6チームが新規参入した。
↩︎ - 大きく分けて(1)がん(ホジキンリンパ腫)との闘い、(2)度重なる腰(背中)トラブルとそれに伴う手術、(3)晩年の心臓トラブル――という三つの健康問題が重なったため。まずがんについては1993年1月に首のしこりの生検でホジキン病と診断され、放射線治療を受けながら短期間で復帰するという劇的な出来事があった。最終回の放射線治療を終えた日のうちにアイスに戻りゴールを記録した「復帰劇」は今でも語り草になっているが、その後の治療の影響で倦怠感や貧血が残り、1993–94シーズン以降は体調面の影響で長期欠場や体調不良による離脱を強いられた。
背中の問題はルミューの選手生活に繰り返し影を落とした。1990年には椎間板ヘルニアの手術を受け、その後も1993年に「ヘルニア化した筋肉」の修復手術を受けるなど複数回の手術と長期離脱が続き、1990–91年や1993–94年には大半の試合を欠場する年があった。これらの腰のトラブルはプレーの継続性を削ぎ、同時期のがん治療による体力低下と相まって「フルシーズンに出続けられない」状況を生み出していく。
さらにキャリア晩年には股関節や慢性的な故障に悩まされ、最終的には心臓の不整脈(心房細動)が判明したことが引退の決め手となる。2006年の最終引退発表時には心房細動を薬で管理する必要があることが明かされ、「まだ滑れたら続けたかったが健康面で続けられない」という本人の言葉も報じられている。
↩︎ - 理由は複合的で、主に(1)チームの成績やプレーオフでの不振、(2)ロサンゼルスという市場でのアイスホッケーの扱われ方、(3)メディア露出・世間の注目が東部・カナダ寄りだった事情――が絡み合っている。
まず成績面ではディオンヌ自身は得点王や各種個人賞を獲得するハイレベルな選手だったにもかかわらず、キングス自体が長期間にわたって上位進出や深いプレーオフランを果たせなかったため、優勝やポストシーズンでの印象的な活躍によってレガシーが強化される機会に恵まれていない。これが「個人成績は素晴らしいがチームの成功が伴わない選手」という評価につながりがちだったのである。
次に、1970〜80年代のロサンゼルスはまだアイスホッケーが主流スポーツではなく、カリフォルニア地域全体でもファン層は限られていた。このため地元外のメディアや全国ネットの注目を集めにくく、東部やカナダの伝統的なホッケー市場でプレーしていたスター選手に比べて知名度や評価が低く見られる傾向があった。
さらに当時は今日ほどリーグ全体のテレビ露出や全国的なブランド化が進んでおらず、情報の中心が東部・カナダ寄りだったことも、ディオンヌの功績が相対的に埋もれた要因になっている。
最後に、同時代やその後の世代に強烈な「顔(フェイス)スター」やチームと結びついた偉業(たとえば複数回の優勝や劇的なプレーオフ活躍)を残した選手がいると、個人記録だけでは評価が相対化されやすい面がある。
ディオンヌは通算得点やゴールで屈指の記録を残した一方で、そうした“物語”(チームを優勝へ導く伝説的瞬間)が乏しかったため、後年のランキングや記憶で過小評価されることが少なくない。
↩︎ - マイク・ボッシーは、ニューヨーク・アイランダースでのキャリアを10年という短い期間で終えたにもかかわらず、752試合出場で573得点という驚異的な数字を残した。1試合あたり0.76ゴールという得点率は、NHL史上の中でも群を抜いており、現代の枠組みでも「最も純粋なゴールスコアラー」として称えられるにふさわしい存在である。
この卓越した実力に対し、NHL史上最多得点記録を持つ「スコアリングの神」、ウェイン・グレツキーも深い敬意を表していた。
グレツキーはボッシーについて「まさしく史上最高のゴールスコアラーの一人として語り継がれなければならない存在だ」と言い切っただけでなく、「彼が打ったシュートが入らないわけがない。もしパワープレー中に少しでも隙(すき)があったら、センターラインに戻ってもゴールが入っているだろう」とも語っており、その鋭さと正確性を「シュートが放たれた時にはすでにゴール裏にある」と表現したほどである。
さらに、ボッシーの得点能力についてファンや評論家も強調しており、「彼ほど自然で純粋なゴールスコアラーはほかにいない」との声が多く聞かれる。特にそのシュートは、“手品師のごとく速く正確で”、ゴールキーパーが反応する前にすでにネットを揺らしているようだった、と感嘆されることも少なくない。
↩︎ - チームが1970年代に築いた「Broad Street Bullies(ブロード・ストリート・ブルリーズ)」と呼ばれる闘争的で肉弾戦を厭わないスタイルと、キャプテンとしてその最前線に立ったボビー・クラークの人物像が一体化しているからとされる。
クラークは得点能力とパスセンスを兼ね備えた攻撃的センターでありながら、1453分という多量のペナルティタイムに示されるようにフィジカルで泥臭いプレーをためらわず、チームの「徹底した勝利至上主義」と「相手を押し倒す」姿勢を体現した。
彼の献身的な働きぶりと闘志はチームメイトの規範となり、1974年・1975年の連続スタンレーカップ制覇で示されたように、個人技だけでなく“勝つために何でもやる”というフライヤーズの文化を牽引したことが評価されている。
同時に、この美学は賛否を呼ぶものだった。相手選手へのラフプレーや挑発的な戦術はリーグ内外で物議を醸し、フライヤーズは「恐れられる」存在として注目を集めた一方で、スポーツ的美徳という観点からは批判も受けた。
クラーク自身も鋭い競争心と時に過激なプレーで知られ、そうした側面がチームの象徴的イメージ──強さ・タフさ・泥臭さ──をより鮮明にしたのである。
↩︎ - ケビン・ロウはエドモントン・オイラーズの80年代王朝を支えた“静かな守備の要”であり、5度のスタンレーカップ獲得に際しては、たとえ骨折していても欠場せずに戦い抜く忍耐力も発揮した。
キャプテンに昇格した後は、1994年に新天地ニューヨーク・レンジャーズでもプレジデンツ・トロフィー獲得に貢献し、6度目のカップを手にする礎となる。
一方、マーク・メシエは両チームで異なるスタイルながら“王朝を築くリーダー”として揺るぎない存在だった。アイス上の集中力と情熱を具現化する象徴的瞬間が、1994年プレーオフのイースタン・カンファレンス決勝第6戦での発言である。
シリーズ2勝3敗と追い込まれた状況で「俺たちはこの試合に絶対勝つ」とメディアに宣言し、その言葉通りにハットトリックを達成してチームを救っている。この一撃はレンジャーズ54年ぶりのスタンレーカップ制覇につながるモーメントとして、今も語り継がれている。
このように、両者ともオイラーズ→レンジャーズにとって欠かせない存在であり、同時期に両チームでカップを掲げ、歴史に名を刻んだのである。
↩︎ - 2013年12月に放送されたHBOのドキュメンタリーシリーズ『24/7 Red Wings/Maple Leafs: Road to the NHL Winter Classic』の第1話で、トースターの使い方に苦戦する姿が映し出され、視聴者に親しまれるエピソードとなっている。
このシーンでは、カーライルが朝食の準備中にトースターにトーストが挟まってしまい、「トーストがトースターに挟まっている!」と困惑しながらも笑顔で語る姿が映し出された。その後、スタッフがトーストを取り出す手助けをする場面もあり、カーライルの人間味あふれる一面が垣間見えた。
このエピソードは、カーライルのコーチとしての厳格なイメージとは対照的な、ユーモラスで親しみやすい一面をファンに印象づけることとなり、シリーズの中でも特に話題となった。カーライル自身もこの出来事を笑い話として語っており、彼の人柄を知る上で印象的なエピソードとなっている。
↩︎ - 主に試合中に他の選手の反則行為や危険なプレーに対して、物理的な対応をする役割を担う選手。
エンフォーサーは、ファイト(乱闘)を通じて相手選手に対し自チームを守る姿勢を示すことが多く、特にスター選手を守る役割も果たす。乱闘は通常、悪質なプレーに対する反応として行われ、チームの抑止力として重要視されてきた。
かつてNHLでは、エンフォーサーはチームの重要な役割を果たし、特に1980年代から1990年代にかけて、多くのチームに専任のエンフォーサーが存在した。ボブ・プロバートやタイ・デュラシェ、ジョージ・パロスなどが有名。
しかし、近年ではNHLが選手の安全性を強化するためにルールを改訂し、特に頭部への攻撃に対する罰則が厳しくなったため、エンフォーサーの役割は減少。暴力的な行為や乱闘を減らす方向に進んでいるため、現代のNHLではエンフォーサーを持つチームは少なくなっている。
それでも、現代でもエンフォーサー的な役割を担う選手は存在し、物理的なプレーや選手間の対立を管理することが求められる。エンフォーサーに対する意見は分かれており、支持者はその役割が試合の進行を厳格に保ち、選手を守る重要な役割を果たすと考える一方、批判者は暴力を助長し、選手の健康リスクを高めると指摘している。 ↩︎