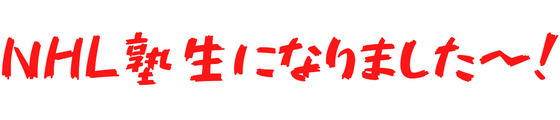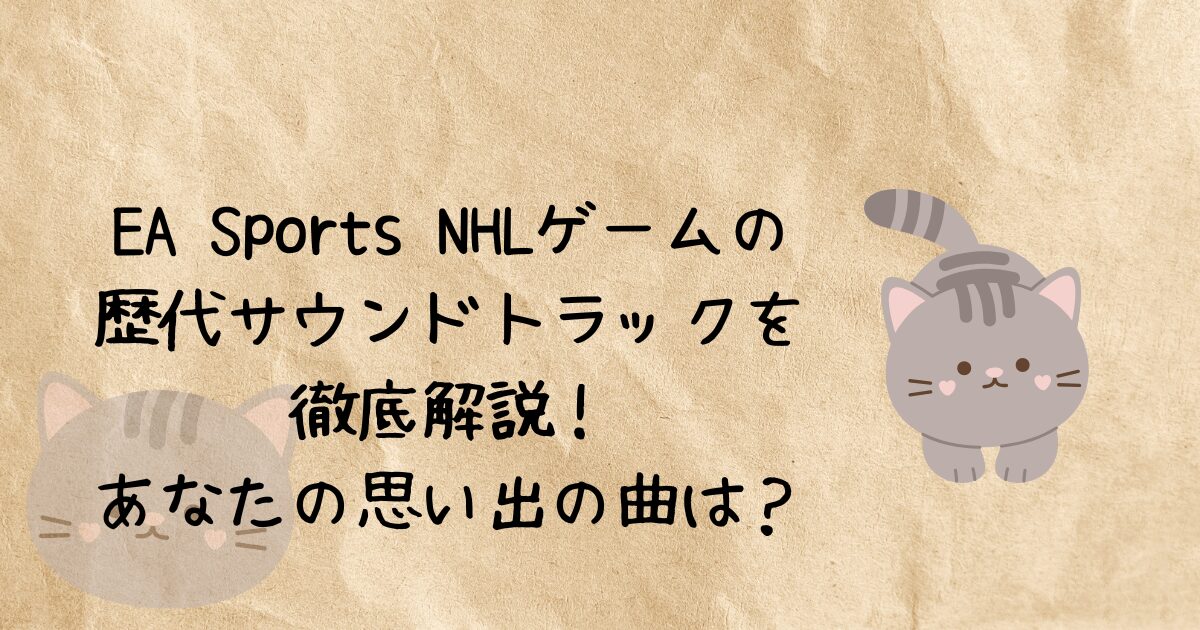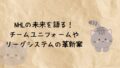はじめに
アイスホッケー好きの皆さん、そしてゲームファンの皆さん、こんにちは!✨
今回は、NHL 99からNHL 2005まで、各作品のサウンドトラックを深掘りし、筆者が選ぶ「最高の1曲」を厳選してご紹介します。単なる曲のリストではなく、当時のゲームの雰囲気や、音楽がどうゲーム体験と結びついていたかを感じられるような内容になっています。
あなたの思い出の曲は入っているでしょうか?ぜひ、懐かしい気持ちで読み進めてみてくださいね。
参照記事:Daily Faceoff「The best song in every EA Sports NHL video game」
ノスタルジーに浸る!EA Sports NHLゲームの歴代ベストソング✨
アイスホッケーファンの皆さん、そしてゲーマーの皆さん、こんにちは!👋
EA SportsのNHLビデオゲームシリーズ1は、常に高評価を受けているわけではありませんが、ホッケーファンにとって特別な存在ですよね。特に若い頃、何時間もゲームに没頭できた日々は、忘れられない思い出になっているはずです。
そんな当時のノスタルジアを一気に呼び覚ますのが、ゲームの起動時に流れていたあの曲たちです。サウンドトラックはゲームの最も重要な部分ではないかもしれませんが、間違いなく記憶に残るものですよね。
特にEASHL/World of Chel2の試合がロードされるのを10〜20分待っている間や、何時間もループ再生される曲を聴きながら、Be a GMモード3を進めている場合はなおさらです。
私(参照記事の筆者)をよく知らない方のために説明すると、私はホッケーオタクであると同時に音楽オタクでもあります。そのため、この2つの情熱を組み合わせる機会があれば、私はそれを逃しません。そして、それにビデオゲームを楽しむという要素が加わることで、さらに素晴らしいものになります。
今回は、そんな思い出深いNHLシリーズの歴代サウンドトラックの中から、最高の1曲をピックアップしてご紹介します。もちろん、音楽はとても主観的なものなので、主に個々のリスナーの好みに依存するため、このリストはあくまで筆者のお気に入り、またはゲームと強く結びついていると感じる曲で構成されています。
もし、あなたの好きな曲や、みんなが選ぶような曲が入っていなくても、その点はご了承くださいね。
筆者ははあらゆる音楽を聴きますが、オルタナティブロックやインディーロック/ポップに傾倒していて、また、NHL Slapshot4とNHL 12から本格的にシリーズをプレイし始めたので、初期のゲームのクラシックな曲についてはあまり詳しくないという点も、あらかじめお伝えしておきます。
対象となるのは、サウンドトラックが初めて登場したNHL 99からNHL 25までの最高の曲です。NHL 26のサウンドトラックはまだ発表されていません。ちなみに、今回はメニューミュージック5のみを対象とし、「Fat Lip6」や「No One Knows7」といったアリーナ内の名曲8は含んでいません。
さっそく見ていきましょう!💨
サウンドトラック時代の幕開け!NHL 99からNHL 2002まで
NHL 99 – デヴィッド・ボウイ「Heroes9」
次点候補:なし
記念すべきサウンドトラック時代の幕開け、NHL 99で選ばれたのは、デヴィッド・ボウイの「Heroes」です。実際の曲が収録されたシリーズ初のゲームであり、ゲームにたった4曲しか収録されていなかったことを考えると、「Heroes」のような名曲を起用したのは、かなり印象的なことですよね。
これはNHLゲームに収録された最高の曲の1つかもしれません(少なくとも名曲という観点から見れば)。それにしても真剣な話、ボウイの伝説的な名曲の中でも最高のトラックの1つとされている、この素晴らしい曲を悪く言うことはできません。

レコードが粉を吹くほど聴いたにゃあ、『Heroes』。70年代のデヴィッド・ボウイとはホント推理しながら、いろいろ語れてしまう存在。『Station To Station』はホワイト・ファンクの最高峰だと思う…おっと、このブログはアイスホッケー、NHL中心でしたね。最新作『NHL26』、日本で手軽に買いたいよ。音楽も楽しみたいし。
NHL 2000 – Garbage「Push It」10
次点候補:なし
あー、この映像見ただけで燃えるわぁ。ゲームやりたくなるよ!
NHL 99の「Heroes」をさらに印象的にしているのは、EA Sportsがその後数作のサウンドトラックで同じ高みを達成するのに苦労したという事実です。NHL 2000では、たった6曲のうち4曲が、2000年代初期のビデオゲームや映画『マトリックス』に出てきそうなインストゥルメンタルのトランスポップ11でした。
そんな中、最もキャッチーだったのがGarbageの「Push It」です。この曲も同じ雰囲気ですが、間違いなく最もキャッチーな曲なので、一度聴いたら忘れられませんよね!
NHL 2001 – Collective Soul「Heavy」12
次点候補:なし
NHL 2000と同様に、NHL 2001も、選べる曲が7曲と限られていました。その大部分がインストゥルメンタルでしたが、Collective Soulの「Heavy」が選ばれています。
EA Sportsがこの時代のシリーズで目指していた明確な音楽スタイルがあったことは明らかで、「Heavy」は「Push It」と同じ雰囲気を保っていますが、間違いなくキャッチーで、少しロックな感じがします。
ちなみに、この企画を始めるまでこの曲を聴いたことはありませんでしたが、これからはもっと聴くでしょう。
NHL 2002 – Gob「I Hear You Calling」13
次点候補:なし
ゲームのチープな感じとなぜか曲がマッチしている。マジのPVみたいだ。
そして、ここでも、EA Sportsは、NHL 2002の中で私に非常に限られた選択肢しか与えてくれませんでした。今回は5曲に減少し、3曲がインストゥルメンタルでした。
真面目な話、この時代、EA SportsはRom Di Prisco14という人物の曲が大好きだったようで、NHL 2000、2001、2002で合計8曲も彼の曲が収録されています。
しかし、NHL 2002はシリーズの音楽スタイルが変化した時期でもあり、オルタナティブロックやポップパンクが中心になっていきました。そんな中で最終的に選ばれたのが、Gobの「I Hear You Calling」です。この曲と「Brand New Low15」が、この新しいサウンドの方向性を決定づけました。
パンク/ポップパンク路線へ!NHL 2003からNHL 2005まで
NHL 2003 – Jimmy Eat World「Sweetness」16
次点候補:なし
NHL 2003のサウンドトラックで、私の心の内にある「カオスアーティスト」が、あえて違う曲を選びたがったのですが、そうすることはできませんでした。
なぜなら、Jimmy Eat Worldの「Sweetness」は、このゲームを象徴する曲であり、一部の人にとっては「NHLの曲17」そのものだからです。そして、私は彼らを責めることはできません。
ゲームがパンクやポップパンクサウンドに傾倒し始めたこの時代において、この曲は間違いなく名曲です。Jimmy Eat Worldの代表的なヒット曲でもありますし、文句のつけようがありませんね。
NHL 2004 – Deftones「Minerva」18
次点候補:Bowling for Soup「Punk Rock 101」19、Brand New「The Quiet Things That No One Ever Knows」
この曲、この映像を選んだのは他でもない、スラッシャーズのユニがカッコ良すぎるから!
次にNHL 2004は、初めて幅広い曲が収録されました。当初はBowling for Soupの「Punk Rock 101」が私の中での候補曲でした。なぜなら、このNHL 2004グループの中で、私はこの曲しかまともに聴いたことがなかったからです(繰り返しになりますが、当時はゲームを継続的にプレイできるようになるには程遠い状態でした)。
しかし、私のDaily Faceoffの同僚たちが、いくつかの候補を送ってくれたのです。
そのうちの1つはゲームプレイ中にしか流れない曲だったので対象外でしたが、最終的にDeftonesの「Minerva」に軍配が上がりました。
私はDeftones(およびリードシンガーのChino Moreno20の他のプロジェクト)を聴いていましたが、この曲は以前に聴いたことがありませんでした。同僚の推薦で数回聴いた後、それは簡単に「Punk Rock 101」を上回ったそうです。
NHL 2005 – The Network「Roshambo」21
次点候補:Ash「Orpheus」、Sugarcult「Memory」、Franz Ferdinand「Take Me Out」22
そして、私は2010年代までNHLゲーマーではありませんでしたが、NHL 2005は筆者が初めてプレイしたゲームなので、このゲームのサウンドトラックには精通しています。
Franz Ferdinandの「Take Me Out」のような名曲も収録されていますが、「Roshambo」には何か私を引きつけるものがありました。
Green Dayのファンだった筆者にとって、The Networkが、Green Dayの当時まだ非公式だった彼らのニューウェーブ・サイドプロジェクトであることを知って、納得がいったとのこと。NHL 2005といえば、この曲が真っ先に頭に浮かぶ曲なので、私の選択はこれしかありませんでした。
まとめ
今回のブログ記事はいかがでしたでしょうか?🎮
EA SportsのNHLシリーズのサウンドトラックは、ゲームの世界観を形作る上で欠かせない要素だったことがお分かりいただけたかと思います。単なるBGMではなく、ゲームの時代や文化を反映した選曲は、私たちに多くの思い出と感動を与えてくれました。
もし、今回紹介した曲の中にあなたの思い出の曲がなかったとしても、このブログをきっかけに、もう一度聴き直してみてはいかがでしょうか。きっと、当時の熱い気持ちが蘇ってくるはずです。そして、新しいお気に入りの曲も発見できるかもしれませんね!

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- 「EA Sports’ NHL」シリーズは、エレクトロニック・アーツが開発したアイスホッケーをテーマにしたスポーツゲーム。1991年に初めて発売されて以来、毎年新作が登場し、実際のNHLチームや選手を再現している。
ゲームはリアルな氷上のプレイ、戦術、選手の動きが特徴で、グラフィックやAI、物理エンジンが年々進化している。
主要モードには、シングルプレイヤーのキャリアやフランチャイズモード、オンライン対戦が楽しめるHUT(Hockey Ultimate Team)などがあり、プレイヤーは選手カードを集めてチームを編成することも可能。シリーズは、PS4、PS5、Xbox、PCなど複数のプラットフォームで提供され、リアルなアイスホッケー体験を追求している。
↩︎ - 「EASHL」(EA Sports Hockey League)と「World of Chel」は、EA Sportsの「NHL」シリーズ内で提供されるオンラインマルチプレイヤーモードのこと。これらは特にコミュニティとの交流や競争を重視したモードで、プレイヤーが他のユーザーと一緒に楽しめる要素を提供している。
EASHL(EA Sports Hockey League)
EASHLは、プレイヤーが自分のカスタマイズしたキャラクターを使って、オンラインで他のプレイヤーとチームを組んで対戦するモード。チームごとに独自の戦略やプレースタイルを持ち、リーグ戦やカスタムトーナメントなど、さまざまな対戦形式でプレイできる。
このモードは、チームメンバーと協力し合いながら、勝利を目指してプレイするため、戦術的な要素も強くなる。
World of Chel
World of Chelは、EASHLを拡張した形で、さらに多くのモードを提供するオンラインプラットフォーム。このモードでは、個々のプレイヤーが自分のキャラクターを使い、他のプレイヤーと対戦したり、アイスホッケーのスキルを磨いたりすることができる。
また、「Pro-Am」モードや「Ones」などのミニゲームもあり、プレイヤーは自分のスタイルに合ったプレイが可能。さらに、キャラクターのカスタマイズや進行要素が強調されており、長期的なプレイが楽しめるようになっている。
これらのモードは、NHLシリーズの中でも特にオンライン体験に重点を置いた要素となっており、長時間プレイしても飽きがこないように設計されている。
↩︎ - EA Sportsの「NHL」シリーズのシングルプレイヤーモードで、プレイヤーがNHLチームのゼネラルマネージャー(GM)としてチームを運営する役割を担う。このモードでは、選手のトレードや契約交渉、ドラフト選手の選定などを行い、チームの成績向上を目指していく。
また、サラリーキャップや予算管理も重要な要素で、リアルな経営シミュレーションを体験できる。プレイヤーは、選手育成や戦術の調整を通じて、チームを勝利に導くための戦略的な決断を下すことが求められる。
↩︎ - 2010年に発売されたEA Sportsのアイスホッケーゲームで、主にWii向けに開発された。リアルなシミュレーションよりも、カジュアルでアーケードスタイルのゲームプレイが特徴。伝説的な選手たちを操作できるほか、スラップショットモードやストーリーモードも搭載。特にファミリー向けにデザインされ、複数人で楽しめる対戦やミニゲームも豊富。
↩︎ - ゲームのメインメニューやインターフェースで流れる音楽のこと。ゲームの本編が始まる前や、メニュー画面を操作している際にバックグラウンドで流れる音楽で、プレイヤーがゲームに入る前の雰囲気作りや、ゲームのテーマを反映させる役割がある。
特にスポーツゲームでは、ゲームの印象を強くするために、エネルギッシュでダイナミックな曲が使われることが多い。
↩︎ - カナダのパンク・ロックバンド Sum 41 の代表曲の一つで、2001年にリリースされたアルバム『All Killer No Filler』に収録されている。この曲は、バンドの商業的成功を確立したヒット曲で、軽快で反抗的な歌詞が特徴。
特に若者文化を反映した歌詞とエネルギッシュなメロディが評価され、広く人気を博した。この曲は、NHLゲームシリーズにおいても使用されており、特に「NHL 03」におけるメニュー音楽として知名度が高い。
↩︎ - アメリカのロックバンド Queens of the Stone Age の代表曲で、2002年にリリースされたアルバム『Songs for the Deaf』に収録。この曲は、グルーヴィーなリフとサイケデリックな要素が特徴的なロックソングで、バンドの最大のヒット曲となり、音楽シーンに大きな影響を与えた。
特にこの曲は、NHLゲームシリーズで人気のあるメニュー音楽の一つとして登場し、アイスホッケーゲームの激しい試合感を引き立てる役割を果たした。
↩︎ - In-arena musicは、アイスホッケーや他のスポーツイベントで試合中に会場内で流れる音楽。観客の興奮を高めるため、選手の登場や得点後、試合の重要な瞬間に合わせて流れる。音楽のジャンルはロックやポップ、エレクトロニックなど多岐にわたり、観客のエネルギーを引き出す役割を果たしている。特に選手ごとに専用の登場曲が設定されることもある。
↩︎ - デヴィッド・ボウイが1977年にリリースした曲で、アルバム『Heroes』のタイトル曲。歌詞は愛と勇気、逆境に立ち向かう英雄をテーマにしており、ボウイ自身が「何かを変える力を持つ人物」として描いている。
音楽は、力強いギターリフとシンセサイザーを特徴に、ボウイの革新的な音楽スタイルを象徴している。広く評価され、映画やスポーツイベントなどでも使われるなど、文化的な影響を持つ名曲。
↩︎ - 1998年にリリースされたGarbageのシングル「Push It」は、2枚目のアルバム『Version 2.0』からのリードシングルであり、バンドの音楽的進化と実験精神を象徴する作品。オルタナティブロックやインダストリアルの要素を取り入れたこの楽曲は、ボーカルのシャーリー・マンソンによる内面の葛藤や欲望、社会的適応への揺れをテーマにしている。
歌詞中の「Don’t worry, baby」というフレーズは、ビーチ・ボーイズの同名楽曲からの引用で、原曲の作者にもクレジットが与えられている。
シングルはヨーロッパや北米を中心に好成績を収め、イギリスではトップ10入り、アメリカではモダンロックチャートで5位に達するなど、商業的にも成功を収めた。特に注目されたのは音楽ビデオで、白黒や偽色を多用した前衛的でシュールな映像表現が高く評価され、MTVビデオ・ミュージック・アワードでは8部門にノミネートされた。
「Push It」は、サウンド、歌詞、映像すべてにおいてGarbageの創造性が詰め込まれた代表作であり、ポップとアンダーグラウンドの境界を押し広げた意欲的な一曲として位置づけられている。
↩︎ - トランスとポップを融合させたエレクトロニック・ダンス・ミュージックで、エネルギッシュでキャッチーなビートが特徴。映画『マトリックス』や1990年代のビデオゲームに使われ、未来的で幻想的な雰囲気を醸し出す。この音楽スタイルは、アクションやテンポ感のあるシーンに適しており、プレイヤーや観客を引き込む効果がある。
↩︎ - 1999年にリリースされたCollective Soulの代表曲のひとつで、アルバム『Dosage』からのセカンドシングル。「重圧」や「被圧力的な疲れ」をテーマとし、力強いギターリフと中速のテンポが印象的。
Billboardのロックチャートで15週連続1位という記録を樹立し、バンドのキャリアで最後のHot 100チャート入り曲にもなった。Ed Rolandは、楽曲タイトルを含め構成やプロダクションを直感的に決め、レコード完成後の追加収録だったとしている。シンプルながらも深い共感を呼ぶ歌詞と、緻密な音作りで、多くのリスナーに今なお支持される名曲。
↩︎ - カナダのパンクロックバンドGobが2000年にリリースしたサード・スタジオアルバム『The World According to Gob』からのファースト・シングルで、バンドの代表曲の一つとして広く知られている。
楽曲の長さは約3分12秒で、キャッチーなメロディとパンクロックらしいエネルギッシュなリズムが印象的。
歌詞には、魅力的な人物に何度も遭遇しながらも言葉が出ず、深く惹かれつつもそれに応えられない内面的な葛藤が描かれている。「I hear you calling, calling for me out in the night / But it’s all bad and I know that(夜に君が俺を呼んでいるのは聞こえる…でもそれは良くないと俺は知っている)」というコーラスフレーズが、心の葛藤を象徴的に表現。
歌詞の背景には、会うたびに惹かれる相手との関係に足を踏み入れることに対する抵抗や、迷いの感情が込められており、切ないながらも強い共感を呼ぶ内容。
この楽曲は、2002年に発売されたEAスポーツのビデオゲーム『NHL 2002』のサウンドトラックにも収録されており、多くのファンに知られるきっかけとなった。一部ファンレビュアーからは、ゲームで耳にしたのがGobを知るきっかけだったという声もある。
↩︎ - エレクトロニック・ゲーム音楽のパイオニアの一人であり、アダプティブかつ革新的な音楽制作を通じて、数多くの人気ゲームに深く関わってきた。その多才さと献身的な制作姿勢は、業界関係者のみならず、ファンからも広く高く評価されている。
↩︎ - カナダのポップパンク/オルタナティブロックバンド、Treble Charger(トレブル・チャージャー)の楽曲「Brand New Low」は、2000年にリリースされた4枚目のスタジオアルバム『Wide Awake Bored』に収録されており、2001年にシングルとして発表された。キャッチーでメロディアスなサウンドとエモーショナルな歌詞を特徴とし、バンドの代表曲のひとつとして評価されている。
この曲は、アルバム収録の他、EA Sportsの人気ゲーム『NHL 2002』のメニューBGMとしても使用され、Gobの「I Hear You Calling」と並んでゲームサウンドの印象を決定づけた。結果として、ゲーマー層にも強く印象づけられ、ゲームと音楽の両面から多くの支持を集めることとなった。
「Brand New Low」は、Treble Chargerの音楽性がより洗練された時期の楽曲であり、商業的にも成功を収めたアルバム『Wide Awake Bored』を象徴する一曲として、現在でも語り継がれている。
↩︎ - アメリカのロックバンド Jimmy Eat World の代表曲「Sweetness」は、2002年6月にリリースされたシングルで、2001年のアルバム『Bleed American』に収録されている。
実はこの曲は、前作『Clarity』の制作後に書かれたもので、ツアー中にライブ演奏されていたが、アルバムには未収録となり、後に再録音されて『Bleed American』に収められた。
楽曲の特徴は、勢いのあるギターリフと、観客との一体感を生む“Whoa-oh-oh”のコーラスにあり、ライブでも非常に盛り上がる曲として知られている。その中毒性のあるメロディと感情的な展開から、ファンや音楽メディアから高く評価されている。
歌詞では、人とのつながりを求めながらも、言葉にできないもどかしさや、感情の波に飲まれそうになる内面が描かれており、「甘さ(Sweetness)」は一時的な安心や逃避として象徴的に使われている。
また、この曲は文化的にも広く知られており、EA Sportsの人気ゲーム『NHL 2003』 のサウンドトラックに起用されたほか、NFLのフロリダ・パンサーズやアナハイム・ダックスなどのスポーツチームにもゴールソングとして使用されていた。音楽ゲーム『Rock Band 2』にも収録されるなど、その影響は音楽ファン以外にも広がっている。
「Sweetness」は、Billboard Hot 100で75位、モダンロックチャートで2位を記録しており、Jimmy Eat Worldのキャリアにおける代表的なヒット曲のひとつとなっている。
↩︎ - その理由の一つとして、『NHL 2003』がこれまでのシリーズから音楽の方向性を変え、パンクやポップパンク、オルタナティブロックを中心に据えたサウンドトラックを採用し、その中で「Sweetness」が代表曲として際立っていたこと。
また、この曲のキャッチーなメロディとライブ感あふれるコーラスは、ゲームのプレイ体験と強く結びつき、プレイヤーの間でノスタルジックな思い出を呼び起こしている。
さらに、SNSでも「NHL 2003のBGMといえば『Sweetness』」という意見が多く、ファンの間でゲームと切っても切り離せない曲として認識されている。このように、「Sweetness」は音楽的な魅力だけでなく、ゲームの文化やプレイヤーの思い出に深く根付いたため、『NHL 2003』の象徴的な曲として長く愛されている。
↩︎ - 2003年にリリースされたセルフタイトルアルバム『Deftones』からのリードシングルであり、バンドを代表する楽曲の一つ。この曲はオルタナティブメタルとシューゲイザーの要素を融合させた独特のサウンドが特徴で、音楽評論家からも「シューゲイザーをメインストリームのオルタナティブメタルに持ち込んだ作品」と高く評価されている。
「Minerva」のミュージックビデオは、カリフォルニア州の砂漠で過酷な環境下で撮影され、ピンク・フロイドの映像作品『Live at Pompeii』を思わせる幻想的でトリッピーな映像が話題となった。バンドメンバー自身も撮影の大変さを語りつつ、完成した映像には満足していると述べている。
また、この曲は映画『ハウス・オブ・ワックス』やゲーム『True Crime: Streets of LA』『NHL 2004』など、多くのメディアで使用され、広く知られている。近年では、2025年に行われたライブでParamoreのヘイリー・ウィリアムスがゲスト参加し共演するなど、ライブパフォーマンスでもファンに人気の高い楽曲。
総じて「Minerva」は、Deftonesの音楽的進化を象徴し、多彩な音楽性と映像表現で多くのリスナーから支持を得ている代表曲。
↩︎ - 2003年にリリースされたシングルで、同年のアルバム『Drunk Enough to Dance』に収録。この曲は、ポップ・パンクのジャンルにおける典型的な若者文化や反抗的な態度、ファッション、恋愛模様をユーモラスに風刺した楽曲。
歌詞には、NOFXのFat MikeやBon Joviの「Livin’ on a Prayer」などへの言及が含まれ、若者の成長や変化をコミカルに描いている。楽曲は、軽快なメロディとポップ・パンク特有のエネルギーで、多くのファンから支持を受けた。
チャートではイギリスのシングルチャートで最高43位を記録し、ロック系のインディーズやオルタナティブチャートでも上位に入るなど一定の成功を収めている。ミュージックビデオでは、学校の教室を舞台に「Punk Rock 101」という授業が展開される演出で、曲のテーマを視覚的に表現。
総じて、「Punk Rock 101」はBowling for Soupのユーモアと批評性が融合した代表曲のひとつであり、ポップ・パンクの魅力をわかりやすく伝える楽曲として評価されている
。 ↩︎ - チノ・モレノ(本名:Camilo Wong Moreno、1973年6月20日生まれ)は、アメリカ・カリフォルニア州出身のミュージシャンで、オルタナティブメタルバンドDeftonesのリードボーカリスト。彼の独特な歌声と多彩な表現力は、バンドのサウンドの核となっており、ヘヴィメタル、シューゲイザー、エモ、ポストロックなど様々なジャンルの要素を融合させるDeftonesの音楽性に大きく寄与している。
また、Chinoはサイドプロジェクトにも積極的で、チカーノ・グレインズ(Team Sleep)、クロススケープ(Crosses / †††)、Palmsなど多様な音楽活動を展開。彼の実験的で繊細なアプローチは、多くのファンや批評家から高く評価されている。
↩︎ - 2003年のアルバム『Money Money 2020』に収録された楽曲で、Green Dayのメンバーが別名義で活動するバンドによる作品。曲名の「Roshambo」は「じゃんけん(ロック・ペーパー・シザーズ)」を意味し、人生の偶然性や予測できない出来事を象徴している。
この曲は、シンプルでエネルギッシュなパンクロックサウンドが特徴で、歌詞は社会的な規範や期待に対する懐疑的な視点を持ちながら、個人の信念や価値観、愛情をテーマに描いている。Green Dayの影響を色濃く反映しつつも、異なる角度からの表現がファンから支持されている。
また、「Roshambo」はスポーツゲーム『NHL 2005』のサウンドトラックにも採用され、ゲームを通じて幅広いリスナーに知られるようになった。全体として、この楽曲はThe Networkの代表作の一つであり、シンプルなサウンドと深いメッセージ性を兼ね備えた作品として評価されている。
↩︎ - 2004年にリリースされたデビューアルバムの代表曲で、インディーロックシーンを象徴する楽曲のひとつ。スコットランド・グラスゴー出身のバンドによるこの曲は、ボーカルのアレックス・カプラノスが作詞を担当し、戦争映画『敵の敵』のスナイパー対決からインスピレーションを受けている。
歌詞の「Take Me Out」にはデートに誘う意味とスナイパーが排除するという二重の解釈があり、恋愛の駆け引きや緊張感を表現。音楽的には、特徴的なギターリフとダンサブルなリズムで、インディーロックとダンス・パンクを融合させたサウンドが魅力。
商業的にも成功し、イギリスのシングルチャートで3位、オーストラリアのTriple J Hottest 100で1位を獲得。グラミー賞にもノミネートされるなど高い評価を受けた。ミュージックビデオはダダイズムやソビエトのプロパガンダ風の独特な映像美で注目され、MTVの賞も獲得。
さらに、『NHL 2005』や『Guitar Hero』などのゲームにも収録され、幅広い層に知られる楽曲となった。 ↩︎