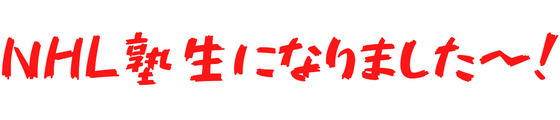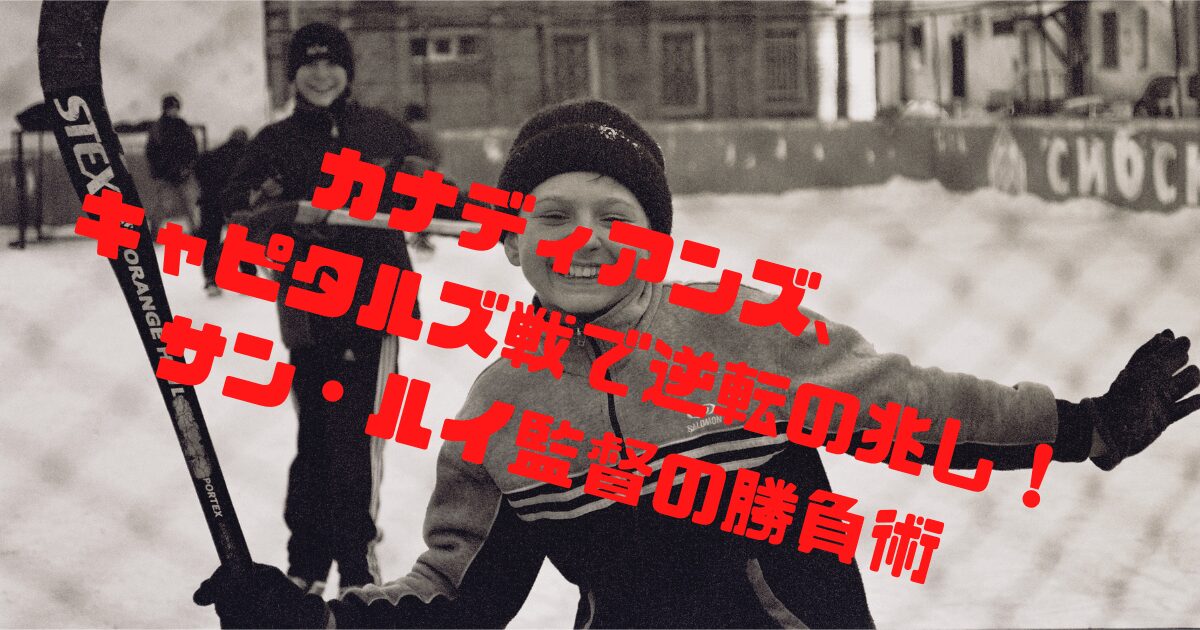はじめに
NHLのプレーオフは、世界最高峰のアイスホッケーリーグで行われる、まさに「氷上の総力戦」❄️。そんななか、モントリオール・カナディアンズが、現在とても厳しい状況に立たされています。
シリーズは「最大7戦」の形式で、先に4勝したチームが次に進めるルール。今、カナディアンズはワシントン・キャピタルズとの1回戦で1勝3敗と追い込まれており、次の試合に負ければその時点で敗退となります。
参照記事:N.Y.Times「Canadiens playoff notebook: Being counted out feels familiar, line matchups and calm」
カナディアンズ、崖っぷちの戦いに挑む🔥
でも、これは彼らにとって初めての試練ではありません。今シーズンの序盤、あるいは4 Nations Face-off(国際大会)のための中断期間に入ったとき、プレーオフに出場することすら難しいと言われていたカナディアンズは、自力でその可能性を引き寄せました💪。
今度の水曜日(4月30日)、ワシントン・キャピタルズとのシリーズ第5戦で敗退の危機に直面する中、その経験を頼りにしようとしています。だからこそ、選手たちは今回も「またやれる」と信じて戦っているのです。
フォワードのブレンダン・ギャラガーは「今年は、ロッカールームの外にいる人たちから何度も見放されてきた。でも、この状況も特別じゃない。俺たちは厳しい時期を乗り越えてきたし、そのたびに必要な対応をしてきた。今回も同じさ。同じ課題に向き合っているだけだ」と語っています。
その言葉からも、チーム全体がこの状況を「前にも似たようなことがあった」と捉えていることが伝わってきますね。
ギャラガーの言葉には、実体験に基づいた重みがあります。彼は、2021年プレーオフ1回戦でトロント・メープルリーフス相手に1勝3敗からの逆転を果たし、スタンレーカップ決勝に進出した際の6人のカナディアンズ選手のうちの1人だからです。
「勢い」が勝負を左右する⚡
プレーオフでは実力だけでなく、“流れ”や“勢い(モメンタム)”が勝負を決める大きなカギになります。カナディアンズの監督、マルタン・サン・ルイは「3連勝することを考えるんじゃない。必要なのはモメンタムをつかむことなんだ」と語りました。
実はサン・ルイ監督自身も、現役時代に3回1も「1勝3敗からの大逆転」を経験したツワモノ🏒。選手としてのその経験が、今の指導に活きています。しかもそのうち2回は、今対戦しているキャピタルズ相手なんです😳!
このシリーズは、極めて僅差の中で進んでいます。第1戦は延長戦の末にキャピタルズが勝利、第2戦もギリギリの戦いで敗れ(1点リードの状態からエンプティネット〈無人のゴール〉で追加点を入れて、キャピタルズ勝利)、第3戦と第4戦はどちらも第3ピリオドの終盤まで同点。つまり、カナディアンズが「全然通用していない」なんてことはないんです。
「このシリーズ、2勝2敗でもおかしくなかった。あるいは、こちらが3勝1敗でリードしていた可能性もある」とサン・ルイ監督が言うように、ちょっとしたきっかけで流れが変わる可能性は十分あります。
「我々の若いチームは、非常に良いホッケーをしている。それを続けることが重要だ……どうやってモメンタムを得て、それを長く保てるか? それを奪い、保ち続けなければならないんだ」。
ギャラガーも「大きな視点で見ると、確かに難しく感じるかもしれない。でも、小さな視点に絞れば、アウェーで1勝すれば流れはひっくり返る。相手の心に“負けるかも”っていう疑いを植え付けられる」と話していて、チーム全体が“勝つ”というより“流れを取り戻す”ことを意識しているのがわかります✨。
第4戦のハイライト映像です!
戦術のカギは“マッチアップ”🎯
アイスホッケーでは、どの選手をどのタイミングで氷上に出すかが勝負の分かれ目になることもあります。これを「マッチアップ」と呼びます。
今回のシリーズでは、キャピタルズのスパンセル・カーベリー監督が、モントリオールのエースラインであるニック・スズキ、コール・コーフィールド、ユライ・スラフコフスキーの3人を抑えるために、(攻守両面好調な)ピエール=リュック・デュボワのラインを徹底的にぶつけてきました。
これはシリーズの中で大きな要素となっています。なぜなら、スズキのラインはそれほどまでに破壊力があるから。このスズキたちのライン、4試合で7ゴールも挙げていて、他のメンバー全体の得点(4点)を大きく上回っています🔥。このことから、相手が徹底的にマークしてくるのも納得ですね。
ホームとアウェイで選手交代のタイミング2を選べるチームが変わるため、モントリオールでの第3・第4戦ではサン・ルイ監督が有利な状況をつくろうと工夫を凝らしました。監督は、できるだけスズキのラインを(やや守備力の落ちるセンター)ディラン・ストロームのラインとマッチアップさせようとしています。
でも、第4戦ではカーベリー監督がちょっとした“トリック”で、希望するマッチアップを再現してきたとのこと😮。
「何度か、コーフィールドが出てきたのが見えたので、そのラインの1人がリンクに出たタイミングで、(プレーが止まると)すぐにデュボワを投入したんだ。そうすると相手は交代するしかなくなる」とカーベリー監督は第4戦後に語りました。
「そうなると、コーフィールドはベンチに戻るか、スズキやスラフコフスキーと一緒にプレーするかの判断を迫られる。これは、両監督による“猫とネズミ”のような駆け引きの一瞬だ。君はそれに乗って、スズキをデュボワにぶつけるのか?
それともスズキを何ターンか温存して、私がその対策を練らなければならないようにするのか?理想的ではない状況に陥ったこともあったが、選手たちはうまく対応してくれたと思う」——こうした監督同士の読み合いも、プレーオフの見どころなんです👀。
今度はサン・ルイ監督の番です。第1戦・第2戦よりも、カーベリー監督の意図するマッチアップを崩す役割を担う必要があります。
「シリーズの大部分で、彼はホームの利を活かして、望む形に持ち込んできた。今度はこっちがホームでそれをやれる。私はそれを崩しに行くし、彼にとって難しくするつもりだ。それが私の仕事だからね」と語っていて、次戦ではさらに戦術バトルが白熱しそうです!
プレッシャーの中で見せる冷静さ❄️
プレーオフの厳しい試合を乗り越えるためには、選手たちが冷静さを保つことが大切です。特に審判の判定に対する反応が、試合の流れに大きな影響を与えることがあります。
第4戦では、キャピタルズの選手が誇張した演技をしたと感じており、またキャピタルズのトム・ウィルソンがアレクサンドル・キャリエに強烈なヒットをかましたシーンが話題になりました。
キャリエはそのヒットでゲームを離脱してしまい、その直後にキャピタルズが同点ゴールを決めたこともあり、カナディアンズの選手たちからは不満の声が上がりました。
これが問題のシーン。ハードなヒットがウィルソンの売りとはいえ、ちょっとなぁ…。
しかし、ギャラガーは「確かに判定は僕らに不利だったけど、それは言うまでもないこと。だけど、それは僕らがコントロールできることじゃない。リーグが判断することであり、信じて任せるしかない。そこに囚われずに自分たちのプレーに集中しないといけない」と冷静にコメント。
第4戦から30分以上が経過した時点でも、サン・ルイ監督は感情的な状態でメディア対応に臨んでいましたが、月曜日には一晩の睡眠で冷静さを取り戻したと認めています。
監督は「そのときは感情的だった。チームはよく戦ったのに、結果はついてこなかった。選手たちは体を張って戦って、ケガ人も出た。監督としては、本当に辛いものがある。でも、今朝目覚めてみると、気持ちはもう整理できていた。ここからまた進んでいくだけだ」と述べています。
「キャピタルズ相手に自分たちのホッケーを押し付けられていることには満足している。これを続けていくだけだ。正しい意図、正しい態度、そして正しい準備を持って、このシリーズを長い戦いにしていきたい」。逆境の中で冷静に前を向く姿勢は、まさに強いチームの証です💪。
サン・ルイ監督、ゴーリー交代のタイミングを説明⚖️
第4戦の終盤、残り2分47秒のタイミング(テレビタイムアウト3明け)で、サン・ルイ監督がゴーリーをベンチに下げて、6人攻撃に切り替える場面がありました。
この決定に対して一部では「早すぎたのでは?」と疑問の声も上がりましたが、監督はそのタイミングについてこう説明しています。「ゴールが必要だ。残り時間が32秒でも2分32秒でも、点を決めないといけないんだよ」と語り、状況を冷静に見極めていたことを強調しました💥。
サン・ルイ監督は、オフェンスゾーンでのフェイスオフを活かし、タイムアウトを残している状況でメンバーを上手く組み合わせて攻撃を続けられると考えたようです。ゴーリーを下げることで、攻撃の組み立てがよりスムーズに行えると同時に、相手に圧倒されるリスクを減らすことができます。
さらに、数的有利を得ることができるため、仮にフェイスオフに負けてもパックを回収しやすくなり、相手がポゼッションを維持して自陣を脱出しにくくなると言います。確かに、カナディアンズにもミスがあったものの、この交代は妥当だったと言えます💡。

テレビタイムアウトに近いのは、NFLの「ツーミニッツ・ウォーニング」かにゃ。ゲーム終盤でクライマックスとなる残り2分間の前に、CMを入れたいテレビメディアの要請で導入されたもので、日本では考えられないルール。それだけNHLもNFLもメディアからショービジネスの重要なコンテンツと思われているわけ。
ラース・エラーが語る、自分のNHLでの役割との向き合い方🏒
ラース・エラーは、カナディアンズ時代に攻撃的な選手としてトップ6(1st&2ndライン)に入ることを目指していました。当初、NHLで自分がどのように活躍するかを強くイメージしており、彼はその自信を持っていたのです。
しかし、彼のキャリアが進むにつれて、役割は変わり、セントルイス・ブルースとのトレードでカナディアンズに加わった後は(2010-11)、期待していたポジションから外れることになりました。最初はトップ6を目指していましたが、ワシントン・キャピタルズに移籍後(16-17)は第3ラインのセンターとしてプレーすることに💭。
「当時はそれも、ここに至るまでの過程だったんだと思う」とシリーズ序盤にエラーは振り返ります。
「自分のアイデンティティを確立しようとしていたけど、ラインナップの中でいろいろな場所に移されたね。もちろん、当時は他の選手もそうだったけど。自分はパズルの1ピースに過ぎなかった。それを乗り越え続けて、時には最高の自分を出せたし、時にはうまくいかなかったこともあった」と語っています。
「ワシントンに来てからは、『君は第3ラインの選手だ』と言われた。でも、クズネツォフとバックストロームの後ろでプレーするなら、それを受け入れるのは簡単だったよ。ただそこにフィットして、ベストを尽くせばよかった」。その結果、スタンレーカップを獲得し、通算1,100試合を超える素晴らしいキャリアを築きました🏆。
もし若い自分にアドバイスができるとしたら、エラーは「自分に厳しくしすぎるな、そして試合を楽しむことを忘れるな」と伝えたいと話しています。
「NHLに来る前の選手って、ほぼ全員が“自分が主役”だった経験をしている。ずっとそうやって育ってきているからね。だからみんな、それを続けたいと思うし、それを目標にしている。でもその目標が重荷になり、逆に自分を苦しめてしまうんだ。
楽しむことを忘れてしまって、誇りとか、期待とか、あれこれ考えすぎて、今この瞬間に集中できなくなる。過去や未来のことばかり考えて、今を生きていない。それって、自分自身を傷つけているんだよ」💭。
アレックス・ニューフックが見習うべき存在🏒
ラース・エラーの経験は、現在のカナディアンズの若手選手アレックス・ニューフックにも大いに参考になるでしょう✨。
ニューフックは(コロラド・アバランチから)トレードで加入した若い1巡目指名(2019年、全体16位)の攻撃的な選手で、自分がNHLでトップ6に入ることを目指してきました。しかし、現実にはチーム内での役割変更に直面することが多く、その役割に対して柔軟に対応することが求められます。
エラーが示したように、自分の役割を“質の高い第3ライン選手”として受け入れ、そこに全力を尽くす姿勢が重要です💪。エラーのように、多くの試合を重ねて成長していけば、彼もまた素晴らしいキャリアを手に入れることができるはずです👏。
まとめ
カナディアンズはプレーオフで苦境に立たされているが、過去の逆転劇から自信を持ち、勢いをつかむことが大切だと考えています⚡。監督は戦術的な駆け引きに注力し、選手たちは冷静さを保ちつつ戦っています💪。
プレーオフはモメンタムが鍵となり、若手選手も自分の役割に順応し、成長することが求められます✨。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- サン・ルイは、2011年にタンパベイ・ライトニングでピッツバーグ・ペンギンズ相手に1勝3敗からの逆転勝利を果たし、その後ニューヨーク・レンジャーズで2014年に再びペンギンズを、2015年にはアレックス・オベチキン率いるワシントン・キャピタルズを相手に同じように逆転劇を演じている。
↩︎ - ホームチームには、選手交代のタイミングをコントロールする優位性がある。ホームチームのベンチは、自分たちが試合を支配している状況でライン変更を行うことができる。
具体的には、ホームチームのコーチがどの選手をいつ氷に出すかを自由に決めることができ、相手チームのラインとマッチアップを有利にすることが可能。例えば、ホームチームのコーチは攻撃的な選手を攻めの時間帯に出したり、守備的な選手を守りの時間帯に出すなど、状況に応じた最適な選手を投入できる。
一方、アウェーチームはホームチームのライン変更に合わせて選手交代をする必要があり、これが戦術的に制約を与えることになる。例えば、アウェーチームが意図しないタイミングで強力な攻撃ラインに対応しなければならない場合、そのマッチアップが不利になることがある。
このように、ホームチームは選手交代を計画的に行うことができるため、戦術的な自由度が高くなり、ライン変更において優位性を持つのである。
↩︎ - NHLでは1ピリオドに最大3回のテレビタイムアウト(各約90秒)が設けられており、主にテレビ中継やスポンサー広告のために使用される。
タイムアウトはプレーが止まったタイミング(例:ゴール後やアイシング時)で挿入されるが、パワープレー中など特定の状況では行われない。これはチームが使える「チームタイムアウト(1試合1回)」とは別のもの。 ↩︎