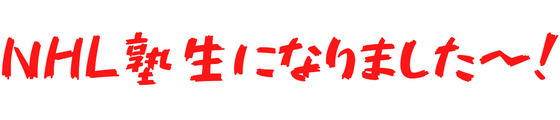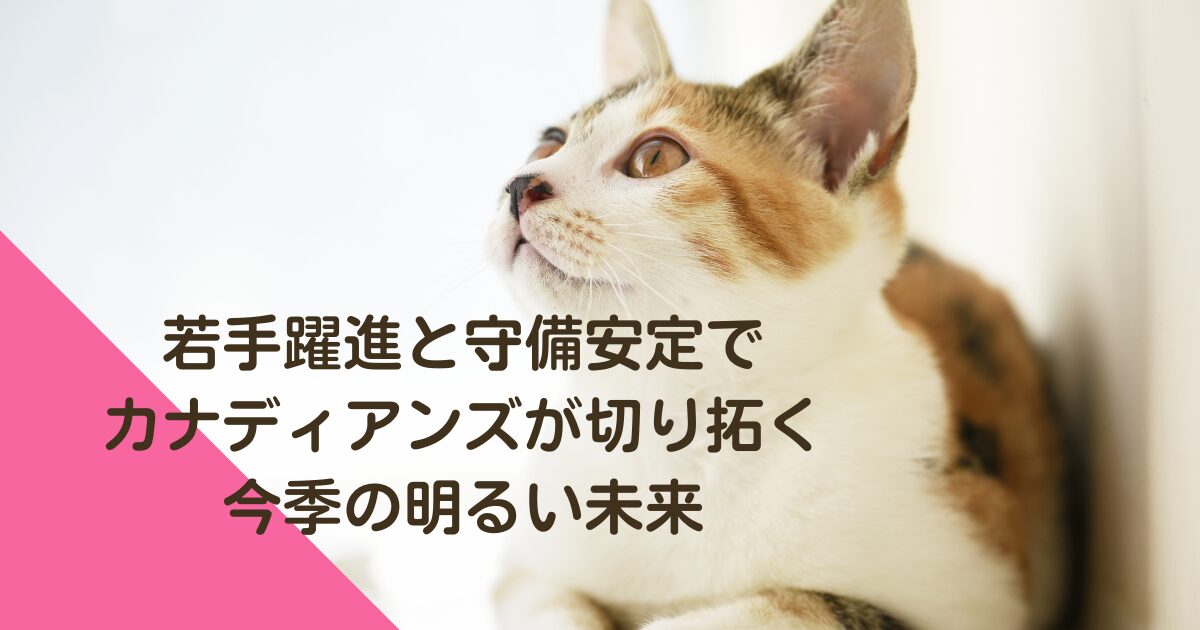はじめに
モントリオール・カナディアンズは守備の安定と攻撃力で開幕8試合6勝と好スタートを切った🏒。しかし、コナー・マクデイビッド率いるオイラーズ戦では審判やパワープレーで苦戦。
それでも若手のスズキやデミドフ、コールフィールドの活躍と、セントルイス監督の巧みな指導で逆境を跳ね返す姿は必見です🔥。チームの成長と未来に期待が高まる一戦を徹底解説します。
参照記事:Global News(ウェブサイト:globalnews.ca)1「Call of the Wilde: Montreal Canadiens fall to the Edmonton Oilers」
🏒モントリオール・カナディアンズ、守備の安定が勝利の鍵
今シーズンのモントリオール・カナディアンズは、自陣のゴールを守る力がチームの強みになっています🏒。開幕から8試合で6勝2を挙げられたのは、守備の安定が大きな要因です。
しかし、コナー・マクデイビッド率いるエドモントン・オイラーズは、その流れを簡単にひっくり返せるだけの力を持っています。
モントリオールは、ここまでで最も厳しい守備の試練に直面しましたが、5対5のプレーではオイラーズを圧倒し、見事に合格点を出しました。ただし、審判がオイラーズに5回連続でパワープレー(数的有利)を与えてしまったことまでは止められなかったようです。
激しい点の取り合いの結果、試合は6対5でオイラーズが勝利しました。
🐎攻撃陣の光と課題🐎
カナディアンズはチャンスをもっと確実に決める必要があります。水曜のカルガリー戦では、カパネンのラインが期待ゴール率で91%、スズキのラインが第1ピリオドで89%と圧倒的な数字を記録したにもかかわらず、リードはわずか1点だけ3でした。
翌日のエドモントン戦でも、スズキのラインは100%、カパネンのラインは96%と、データ上では完全に支配していたにもかかわらず、スコアは1対1の同点でした。
アルバータでの2試合、どちらの第1ピリオドも本来なら3点、4点とリードしていてもおかしくなかったはず。しかし実際には、自分たちで試合を難しくしてしまいました。
水曜のカルガリー戦では、ダスティン・ウルフ相手にシュートがゴールマウスの中央ばかりに当たり、翌日のエドモントン戦では、カルヴィン・ピカード相手に絶好機でもガラス板(ゴール上部)に当ててしまう場面が目立っていたのです。
カナディアンズは試合の中で一方的に主導権を握る時間帯もありますが、ホッケーというスポーツでは「決め切ること」が重要です。なのに、チャンスを十分に得ているにもかかわらず決めきれていない選手がいます。
ニック・スズキは、今季これまで1ゴールしか挙げていませんが、本来なら試合ごとに1点は取れてもおかしくありません。イワン・デミドフも今季まだ1ゴールしかなく、彼の攻撃力と、あれほど容易にチャンスを作り出している姿を考えれば、それが信じられないほどであり、もっと点を重ねられるはずです。
🚨攻撃陣の爆発力とコールフィールドの活躍
もしカナディアンズがこれほどまでに相手ディフェンスの裏でプレーを続けられるなら、間違いなくゴールは自然と増えていくでしょう🚨。特に、チームでこの夜唯一のパワープレーで第1ユニットに昇格したデミドフにとっては、その大きなチャンスです。
第1ピリオドでは、本来なら4点は取れていたはずの場面で、実際に決まったのはレーン・ハットソンがゴール前に放ったパックのリバウンドを、アレックス・ニューフックが押し込んだ1点のみでした。
このゴールでオリヴァー・カパネンがアシストを記録し、このラインは今季のサプライズと言える存在になっています。
カパネンはNHLで第3ラインのセンタークラス4かもしれませんが、彼とマッチアップする相手選手たちにそれを言わないほうがいいでしょう。なぜなら、彼のラインはトップクラスの攻撃陣を相手にしても、互角以上に渡り合っているからです。
第2ピリオド終盤、オイラーズが3対1とリードしたときは、もう勝負あったかに見えました。しかし、モントリオールは諦めませんでした。
カナディアンズはわずか1分50秒の間に3ゴールを奪い、第2ピリオドを締めくくったのです。最初はジョシュ・アンダーソン、そして続くのはコール・コールフィールドによるまさに“マジック”のようなプレーでした。
コールフィールドの最初のゴールは、ゴールエリア目前で鋭く切り返し、ニアポストに完璧にパックを押し込む動きを見せ、ピカードにセーブの余地を与えませんでした。
そのわずか数十秒後、同じシフトで右ウイングを駆け抜けた彼は、遠いサイドのポストぎりぎりに突き刺すシュートを決め、この結果、コールフィールドは今季通算7ゴールとなりリーグトップに並びました。
スズキもアシスト数でリーグトップに並び、データ上でも第2ピリオド終了時点で、カナディアンズのトップ2ラインは“期待ゴール率95%”という圧倒的な支配を見せていたのです。
第3ピリオドでは、カパネンのラインがオイラーズの5人をまるで見物人のように翻弄し、自由自在にパックを回す姿が印象的でした。
🐐Wilde Goats:デミドフとモンタンボーの課題
チーム5点目は、カパネンからニューフックへの見事なパスで決まり、ニューフックはこの日2点目を挙げました。しかし、ここで少し厳しい指摘があります。あえて言うなら、カルダー記念トロフィー(新人王)の有力候補であるイワン・デミドフは、そろそろシュートを打つべき時です🐐。
ルーキーがベテランへの敬意からシュートを譲るのは普通のことですが、デミドフは今、ためらわずに撃つタイミングが来ています。彼はより簡単に決められるシュートを自分で打つのではなく、難しい位置の味方へのパスを選んでしまうことが目立ちます。
デミドフは今季9試合でわずか7本しかシュートを放っていません。これだけパックを長く保持している選手としては異常なほど少なすぎます。通常、トップ選手でもシュート成功率は20%程度、デミドフのような新人の場合、だいたい10%程度に落ち着くのが一般的です。
つまり、30ゴールを狙うなら、82試合で300本――1試合に約4本のシュートが必要ですが、現時点では1試合に1本にも満たない状況です。デミドフには素晴らしいシュート力があり、ゴール前でのポジショニングも完璧。今こそシュートを打つべきタイミングです。
また、ゴーリーのサミュエル・モンタンボーにも、この夜の明確な課題がありました。この試合では最初の11本のシュートで3失点し、序盤からリズムを崩しました。モンタンボーの試合前のセーブ率は.857と苦しい数字でしたが、この敗戦で.842に低下。
期待失点差でも、チームメイトのヤクブ・ドベスがリーグ3位と好調な一方、モンタンボーは65人中4番目に悪い数字に沈んでいます。彼のキャリア平均は.900。そろそろ調子を取り戻す必要があります5。
カナディアンズvs.オイラーズ戦のダイジェスト映像です!両チームのゴーリーが…(以下自粛)。
そして、この夜最大の「ヤギ(反省点)」は――審判団でした。
⚖️Wilde Cards:審判と試合を左右したもう一つの要素
この試合でカナディアンズは、後半に5回連続でマイナーペナルティを取られるという不運に見舞われました⚖️。
その中には、ユーライ・スラフコフスキーへの「ボーディング」判定(相手を危険に押し込む反則)や、マイク・マシューソンの軽いトリッピング(足掛け)、さらにジョシュ・アンダーソンへの「アンスポーツマンライク・ペナルティ」(非紳士的行為)などがありました。アンダーソンはゴール後にパックを氷上に打ち下ろしただけでしたが、反則とされてしまったのです。
NHLの審判は、試合を接戦に保つことに個人的に関与しすぎる傾向があります。他のスポーツでは見られない独特な裁定で、観る側としてはフラストレーションが溜まる場面もあります。この夜の審判への苦言6は、そのシーズンで一度あるかないかの出来事でした。批判は正当です。
選手も監督も審判団に猛抗議!「何であれが?」と信じられない様子。

スピード感あふれるスポーツな上に、バトルの多いスポーツなんで、審判団もなかなか大変だとは思うんだけど、この試合のジャッジは酷すぎたにゃ。オイラーズが絡むと、審判団は何かに魅入られたように(?)オイラーズ寄りのジャッジをするのは、今に始まったことじゃない。カナディアンズの監督も選手もたまりに溜まった不満を爆発させたんだな。
🧠若手育成の名将:マーティン・セントルイス
NHL全体でも十分に評価されていないのが不思議なくらい、セントルイス監督は、リーグで最も若いチームを率いるには理想的な指導者です🧠。
ヘッドコーチにとって重要なのはバランスです。若手に自由を与えすぎるとミスが増え、自信を失い創造性を抑えられてしまいます。だからこそ、ルーキーに「完全な自由」を与えるのではなく、段階的に、適切なタイミングで機会を与えることが良いコーチングなのです。彼はそれを知っています。
ミスは避けられませんが、それを叱る材料とするのではなく、学ぶ機会に変えるのがセントルイス流です。
今でこそ成熟した選手に見えるコール・コールフィールドは以前、ドミニク・デュシャルム前監督7の時代にはベンチに下げられ、評価を落としていましたが、今では見違えるほど成長し、攻守に優れた完全な選手として開花しました。
セントルイスの指導下では、一度も選手を潰すのではなく、才能を伸ばすことが徹底されています。それが、以前のミシェル・テリエン8政権とは決定的に違うところです。
🌟ハットソンとデミドフの成長
ヘッドコーチのセントルイスは、レーン・ハットソンに対しても根気強く指導を続けました🌟。デビューシーズン初期には素晴らしい攻撃センスを見せながらも、プラスマイナス評価マイナス14という厳しい数字を背負っていましたが、多くのコーチなら出場時間を制限し、場合によってはAHL(下部リーグ)に降格させていたかもしれません。
このヘッドコーチが適切なチャレンジを与え続けた結果、70試合後にハットソンはカルダー賞(新人王)を獲得しました。
今シーズンも同じことが起きています。
イワン・デミドフはスティックさばきや「コンピュータのような」ゲーム処理能力で高く評価されていますが、守備面にまだ改善の余地があります。昨シーズンはバックチェックで手を抜く場面もありましたが、今年は全力で戻って奇襲攻撃を阻止するために160フィート(48.8メートル)全力で戻るプレー9を見せ、守備力向上にも取り組んでいます。
デミドフは攻撃の才能を失わずに、守備も学びながら成長中です。これもセントルイスの指導による賜物です。
🏒選手をさらに輝かせる指導法
アルベール・ジェカイのように、一部では監督に抑えられていると感じる選手10もいますが、本人はセントルイスの指導を高く評価しています。彼は監督のおかげでより良い選手になれると心から尊敬しています。
また、ゴール数が減少傾向にある選手でも、セントルイスの下では新しいプレースタイルを学び、再び輝きを取り戻しています。ジョシュ・アンダーソンやブレンダン・ギャラガーも、他の監督なら見放されていたかもしれませんが、今ではNHLで活躍し続けています。
オリヴァー・カパネンも例外ではありません。かつては控えめでしたが、今年は果敢にパックを奪いに行くプレースタイルを見せています。セントルイスの指導によって、選手は学びながら成長し、より強い選手に変わっていくのです。
🌟カナディアンズの未来と名将セントルイス
自分のプレーを学び、成長させたい選手にとって、マーティン・セントルイスは理想的な監督です。どこが間違っているかを示してくれるだけでなく、改善の方法も教えてくれます。選手たちは、自分の課題を知ることで前向きに取り組むことができるのです。
難しい変化をチームのために遂行しながら、選手のモチベーションを引き出すことができる特別なコーチ――モントリオール・カナディアンズには、戦術家としても優れ、選手を鼓舞する力も抜群な、まさにそんな監督がいます。そして、まだその旅は始まったばかりです🏒🔥。
まとめ
カナディアンズは守備の安定、攻撃力、若手育成という3つの柱で成長中🏒。特にセントルイス監督の指導のもと、ハットソンやデミドフ、カパネンらが能力を伸ばし、チームの戦術理解も深まっています。
課題はまだあるものの、選手個々の成長とチーム戦術の進化で、今後さらに強くなる可能性は大。次戦以降の活躍に期待が高まります🔥。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- カナダのテレビネットワークGlobal Television Networkのニュース・時事部門が運営するオンラインニュースポータルで、ケベック州ブリティッシュコロンビア州バンクーバーに本拠地を置く通信企業Corus Entertainmentが所有・管理している。
このメディアは、全国21か所以上に配置されたローカルニュースルームを活用し、地域ニュースから国際ニュースまで、「コミュニティから世界へ」という視野で速報・特集・分析コンテンツを提供。
ウェブサイトの「About」ページには、「全国のカナダ人に向け、地域発の速報から複雑な世界問題を深く掘り下げたエンゲージングなコンテンツまで幅広く発信する」と記されている。
信頼性・バイアスに関しては、メディアバイアス/ファクトチェックを行う独立機関による評価では、Global Newsは「Lean Left(やや左寄り)」とされている。すなわち報道内容においてリベラルまたは進歩的な傾向がやや見られるという評価がある。
↩︎ - 北米メディアは総じて、モントリオールの今季の好調を「若手コアの台頭」と「セントルイス体制によるシステムの適合力」に帰して高く評価している。
新加入組や若手が短期間でチーム戦術にフィットしている点が繰り返し指摘され、守備面で安定感を示していることが勝利数につながっていると分析。
一方で、特にスペシャルチーム(パワープレー)の改善や決定力の問題、ゴールテンディングの不安定さは依然として懸念材料とされ、そこをどう修正するかが今後の焦点だと報じられている。
加えて、オイラーズのような超攻撃力チームは一瞬で流れを変えられる脅威であり、モントリオールの守備力が本当に試される相手だという見方が強まっている。
↩︎ - 北米では、Montreal Canadiensが「期待ゴール(xG)で圧倒的な数値を出しているにもかかわらず得点が伸び悩んでいる」点に対し、やや冷静な評価が見られる。
たとえば、分析記事では「モントリオールはxGや高危険度チャンス数で改善傾向にあるが、実ゴールまで結びついていない」と指摘されており、攻撃の質は上がっているとしても“仕留める力”の不足が勝負時にはっきり出ると報じられている。
また、「期待ゴールの数値が高くても、そのままゴール数に反映されないのはホッケーの性質上、ゴールテンディングや運、パックのこぼれ、ポストの当たりなど予測不能な要因が絡むため」といった解説も散見され、数値を評価しつつも“実数(ゴール)”との乖離に注意を促す論調が多い。
このため、モントリオールの攻撃陣が今後「チャンスをもう少し確実に決める」ことが、今シーズンの成否を左右する鍵になるという見方が、北米分析陣の共通認識となっている。
↩︎ - NHLにおける「第3ラインのセンター(3C)」は、チームの中核となるトップ2ラインの次に位置する役割で、攻守ともにバランスの取れたプレーが求められる。具体的には、第一・第二ラインの激しい攻防を支えるために、相手の上位ラインを抑えつつ、自チームのカウンター機会を創出する役割を担う。
例えば、Mika Zibanejad(ニューヨーク・レンジャーズ)についての記事では、ここ数年で攻撃面が下降傾向にあるため、「第三ラインのセンターとして、より有利なマッチアップを与えられれば彼の強みが活きる」と評された。
また、Lars Eller(オタワ・セネターズ)などベテラン選手が3C役を受け入れる事例も多く、「ゴールを量産するタイプではないが、様々な状況(フォアチェック、ゾーン開始、ペナルティキル)で安定して機能できる“深さ”において価値がある」との評価もある。
つまり、3Cは派手な数字を残すポジションではないものの、「チームが安定した戦いを継続するための潤滑油」としての役割が大きいと、北米の解説者たちは見ている。
↩︎ - 北米メディアでは、Samuel Montembeaultについて「今季の立ち上がりは非常に厳しい」との評価が一般的。試合序盤から失点が重なり、最新のセーブ率はリーグ下位に位置。
「GSAx(期待失点差)の観点でも65人中4番目に低い」というデータが報じられ、昨シーズンまで平均を上回っていた“キャリア.900”近辺の数字からの後退が懸念されている。
一方で、若手Gとして台頭中のJakub Dobesには明るい未来が予測されている。今シーズンの5対5セーブ率が.970超と“驚異的”な数字を記録し、解説では「彼こそカナディアンズの次代の正G」とも。
このため、モントリオール勢は「守護神交代の岐路」に立っているという見方が浮上しており、モンタンボーの復調とドベスの台頭、二人のゴーリーをめぐる“駆け引き”が注目されている状況。
↩︎ - 北米のメディアやファンは、NHLの審判運営に対して「試合を接戦に保つための“ゲーム管理”が過剰になっている」と批判的な見方を示している。特に「明らかな反則を見逃す」「同じプレーなのに試合ごとに判定が異なる」といった一貫性の欠如が問題視され、あるインサイダーは「今期の審判はひどすぎる」とまで言及している。
また、プレーオフにおける判定ミスの影響を受け、複数のレフェリーが同シリーズで除外されたという報道もあり、リーグ自身が審判制度の信頼性を問われている状況。
↩︎ - Dominique Ducharme(1973年生まれ)は、カナダ・ケベック州出身の元選手で、コーチとして活躍してきた人物。選手としては米国のバーモント大学で在学中に得点を重ね、北米マイナーリーグおよびフランスリーグでプレー。
コーチ転身後は、ジュニアリーグであるHalifax Mooseheadsを率いて2013年にチャンピオンとなり、カナダU20代表を世界ジュニアで優勝に導くなど実績を築いた。2018年にMontreal Canadiensのアシスタントコーチに就任し、2021~22シーズンには同チームのヘッドコーチも務めたが、成績不振により2022年2月に交代。
↩︎ - Michel Therrien(1963年生まれ)は、カナダ出身のベテランNHLコーチで、選手時代はAHLでディフェンスとしてプレーし、1985年にはカルダー・カップ優勝を経験。コーチとしてはジュニアリーグでの優勝を皮切りに、2000年にMontreal Canadiensのヘッドコーチに抜擢。チームを1シーズンで16ポイント改善し、2002年にはプレーオフ1回戦で上位シードを撃破する快進撃を演じた。
その後、Pittsburgh Penguinsでは2006-07シーズンに105ポイントと歴代屈指の改善を達成し、ジャック・アダムズ賞候補に挙がるなど高く評価された。しかしながら、「序盤の好スタート後に失速」「プレーオフでの不満足な結果」が繰り返され、2017年にはモントリオールでの2度目の監督就任中に解任。
Therrienは守備重視の戦術スタイルで知られる一方、選手の自主性や創造性では賛否を呼び、指導方法が議論の的になった監督。
↩︎ - アイスホッケーのリンクは、全長200フィート(約61メートル)。そのため、「160フィート(約48.8メートル)」という距離は、ほぼリンク全体の4分の3ほどの長さ。具体的には、相手ゴール前のコーナーあたりから、自陣ゴール前までほぼ全力で戻る距離になる。
たとえば、相手の攻撃ゾーン(オフェンシブゾーン)の深い位置でパックを失い、そのまま自陣のゴール前まで全力で戻って守る「バックチェック(守備への戻り)」をする場面となる。つまり「160フィート全力で戻って守った」という表現は、「リンクのほぼ端から端までを全速力で戻った」という意味で、非常に献身的でチームプレーを重視した守備行動を示している。
↩︎ - 北米メディアによれば、Arber Xhekaj と Martin St. Louis の関係は、当初“緊張”と“疑問”で語られることもあったが、現在では「師弟関係に近い信頼感を伴うコーチ‐選手関係」に発展していると報じられている。Xhekaj自身が「監督はまるで父親のように接してくれる。
自分の可能性を信じて、時には厳しく、時には褒めてくれる」と語る一方、St. Louisも「彼の身体能力だけでなく、判断力やポジショニングなど“それ以外の部分”も成長させたい」と明言。
また、St. LouisがXhekajに対して「毎シフト喧嘩を仕掛けることばかりが役割ではない」「適切な攻撃と守備のバランスを取るように」と繰り返し指導しており、この過程でXhekajのスタイルは“単なるファイター”から“多機能ディフェンダー”へと進化しつつあるという評価が出ている。
このように、二人の関係は「厳しさと信頼」の両輪で構築されており、Xhekajの成熟とチーム内での役割定着が期待されているという点が、北米における共通した見解。
↩︎