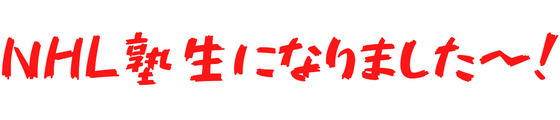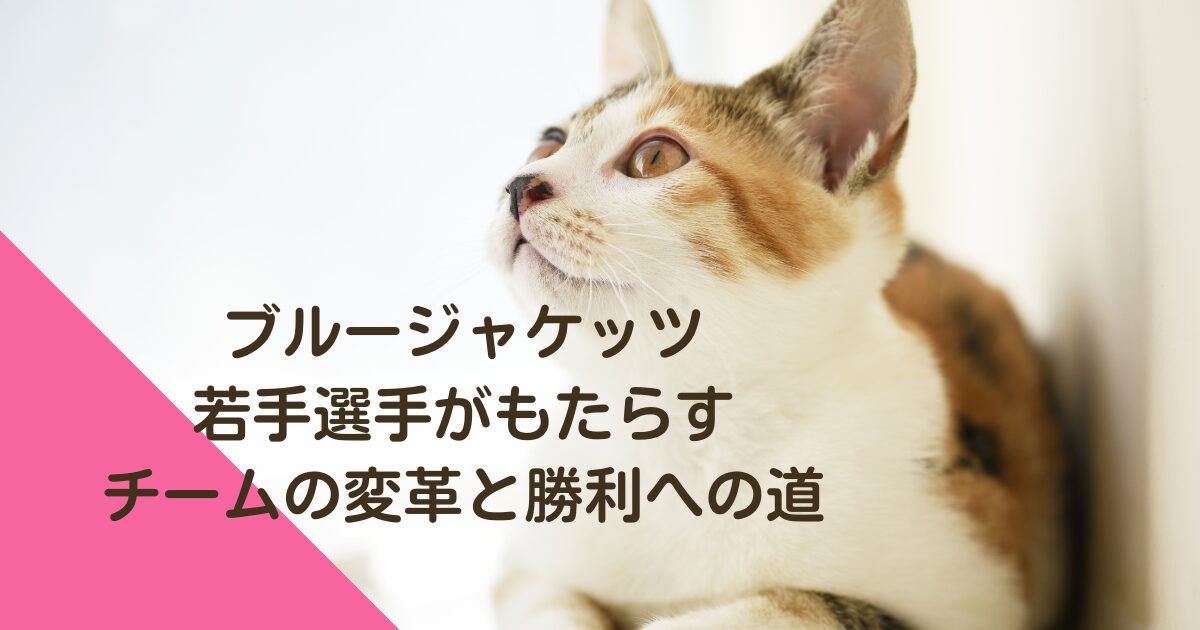はじめに
若手選手が躍動するNHL・ブルージャケッツ。ファンティリやジョンソン、シリンジャーといった注目の若手が、氷上での活躍だけでなくロッカールームでも存在感を増し、チームの空気を一変させています。
彼らはただの新人ではなく、ベテランと肩を並べて意見を交わし、チームの未来を担うリーダーへと成長中。今シーズン、この世代交代がどんな新しい化学反応を生み出すのか、期待が高まっています。続きを読んで、その理由を見ていきましょう!
参照記事:NHL公式サイト「Blue Jackets young stars finding their voice」
若手がチームを動かす時代へ!ブルージャケッツのロッカールームに変化の風🌬️
NHLの中でも注目を集める、最もダイナミックな若手軍団——それがコロンバス・ブルージャケッツ。
才能ある若手選手たちは、リンクの上だけでなく、リンクの外でも、チームの文化そのものにも新しい風を吹き込んでいます。
かつての「若手は黙って先輩に従え」なんて時代はもう昔の話。それでも、チームとしてのケミストリーをうまく築くためには、様々な性格や経験レベルのバランスが必要とされます。これは、どんな職場でも同じことです。
今、ブルージャケッツでは若手たちが声を上げ、仲間と対等に意見を交わし、チームの中で確かな存在感を示しています✨
副キャプテンのザック・ワレンスキーも、「彼らは今やロッカールームのリーダーなんだ」と太鼓判。「それは僕たちベテランにとってもワクワクすることだし、彼ら自身にとっても同じように刺激的なことだと思うよ」。
結束力が強まるロッカールーム💪
確かに、アダム・ファンティリやケント・ジョンソン、コール・シリンジャーといった新進気鋭の若手たちは、さらには少し年上のキリル・マルチェンコやドミトリ・ヴォロンコフ、そして昨シーズンのルーキーとして目覚ましい活躍を見せたデントン・マテイチャクにとっても、大きな前進の時1です。
彼らはいずれも才能ある選手であり、プロキャリア最高のシーズンを終え、今季さらにステップアップする準備万端。もちろん、それはプロセスではありますが、若手たちはその一員でいられることをありがたく思っています。
ディフェンスマンでありながら、抜群の攻撃センスを持つデントン・マテイチャク。この男、フリーでパック持たせると、かなりヤバい。
特にファンティリは、「ベテランが自分の意見に耳を傾けてくれて、それが最善のアイデアでない時でさえ会話してくれるっていうのは、若手にとって本当に意味のあることなんだ。一緒に意見を出し合って、それを氷上で実行しようとする
——それができるのはとても大きなことだよ」と語っていて、若手とベテランが本音で語り合える関係性がチームに根付きつつあることが伝わってきます。
もちろん、ブルージャケッツには経験豊富な選手も多く在籍しており、ワレンスキーやキャプテンのブーン・ジェンナーのようにチーム生え抜きの選手もいれば、さらにはエリック・グドブランソン(2022-23シーズン、カルガリー・フレームスから移籍)やショーン・モナハン(2024-25シーズン、ウィニペグ・ジェッツから移籍)のように他チームを渡り歩いてきた顔ぶれも健在。
ベテラン選手たちは、NHLで直面するあらゆることに若手が慣れるのを助けつつ、同時に高い基準を設定し、それを守るというバランスを取らなければなりません。こうしたベテランと若手が化学反応を起こしながら、チームとしてのまとまりを深めているのです。
「声を上げる」ことへの抵抗がない環境🗣️
一方で、キャリア初期の選手たちは、自分がまだ経験不足だと感じている中で、遠慮して発言を控えてしまうこともあるでしょう。若手選手が積極的に発言できるようになるには、時間と信頼の積み重ねが必要です。このグループにとって時間が経つにつれて、物事はうまくかみ合ってきているのは確かです。
ケント・ジョンソンは「ルーキーや若手の時は、あまり目立ちすぎないようにしたいと思うものなんだ。敬意を持って行動する必要があるし、学ぶこともたくさんある。でも、少しずつもっと発言できるようになってきたと思う。
今はすごく居心地が良くて、Z(ワレンスキーの愛称)のような年上の選手に対しても、自分の意見を言えるようになったし、それが尊重されてると感じてるんだ。すごくクールなことだよ」と話します。
新シーズン、ケント・ジョンソンにも期待してほしい。スティックさばきは一見の価値あり。
こうした発言の自由は、単なる「話す勇気」だけではなく、彼らが早い段階で成熟した態度、強いワークエシック(勤勉さ)、そしてスキルを持っているからこそで、トレーニングや日々の取り組みの中で、ベテランから認められている証でもあります🔥
例えば、ファンティリの夏のトレーニング姿勢について2、ワレンスキーは「毎回驚かされる」と語り、彼と一緒にオフシーズンにトレーニングをしている中で、確かな手応えがある様子。他の若手たちも、それぞれが努力し、実力と信頼を積み重ねてきたからこそ、今の関係性が築けているのです。
プレースタイルだけじゃない!「考えるホッケー」への成長🧠🏒
氷上でも、ファンティリ、ジョンソン、シリンジャー、マテイチャクは、いずれもNHLドラフトの上位12位以内3で指名された選手であり、初年度からその能力を十分に示しています。さらに、マルチェンコとヴォロンコフも、ロシアからやってきた当初から即戦力としてのインパクトを見せてきました。
ブルージャケッツの若手たちは、単にプレーが上手いだけではありません。彼らはホッケーというゲームを“深く考える力”も持ち始めています。
チームの月曜のメディアデーで、ワレンスキーは「今では、彼らのことをちゃんと理解できている。何が彼らの原動力なのかもね。彼らが単にプレーするだけでなく、ホッケーを“どう考えるか”という点でも感心している」と語り、特にパワープレー時のケント・ジョンソンの動き方や意図が理解できるようになってきたと感じているようです。
これによって、リーダーとしての振る舞いにも変化が。「どのタイミングで厳しく接し、いつは引くべきか」——そうした判断をしながら、若手たちにもっと発言のチャンスを与えるようにしているとのこと。
実際に若手たちが自分の考えを共有し始めると、選手たちが自分らしくいられて、思ったことを率直に言えるようになると、戦術的な話し合いが活発になります。
例えば、パワープレーについてでも、ブレイクアウト4(守備から攻撃への切り替え)についてでも、アイデアがより豊かに。こうしたやりとりが、チーム全体をより良い方向へと進むスピードも加速しているのです✨
「僕たちのロッカールームには、ホッケーについての明晰な頭脳を持つ選手がたくさんいて、その多くは若手なんだと思う」とワレンスキーは言います。「大事なのは、みんなが同じ方向を向いていて、それぞれが声を出せること、そしてお互いを信頼していること。今の僕たちは、それができていると感じているよ」
キャプテン・ジェンナーの理想のロッカールーム🧢
チームの中心にいるキャプテン、ブーン・ジェンナーも、若手の発言を大いに歓迎しています。彼にとって大切なのは、選手たちが「自分の最高のバージョン」であることです。キャプテンとしての彼の役割のひとつは、ロッカールーム内の様々な個性をうまくまとめること。
ジェンナーは、その役割を自分なりに受け入れていると語ります。
また、コーチたちはよく「本当に強いチームは5、スタッフの指示ではなく、選手主導で動く」と言います。
「まず第一に、ロッカールームの中で選手たちが自分らしくいられることが大事だと思ってる。本当の自分でいて、自分の考えを自由に言える——そんな快適な環境を作ること。それがこのリーグで成長していく上での一部なんだ」と語るジェンナー。
リンク上で結果を出すだけでなく、ロッカールームという「見えない場所」での成長も重視している姿勢がうかがえます。
昨シーズン、若手たちの発言が以前より増えてきたことも、彼にとってはうれしい変化だったようです。
「昨シーズンは、数年前と比べてずっと声を出すようになってきたし、それを見ているのは本当に嬉しいよ。これからも、彼らはその面でも成長していくだろうし、ロッカールームの中でリーダーシップの面でも様々なものをもたらしてくれるはず。
今は2年目、3年目、4年目といったタイミングで、次のステップを踏み出す時期なんだ。僕たちはそれを後押ししていくよ」と語るその表情は、とても頼もしいものでした💬
ブルージャケッツが前進を続けていく中で、次世代の選手たちはますます大きな役割を担うことになるでしょう。そのプロセスはすでに始まっており、今の若手選手たちと、築かれてきたチーム文化の中で進行中です。

昨シーズン開幕前に不慮の事故により、この世を去ったジョニー・ゴードローが天国で大喜びしていると思わせるくらい、ブルージャケッツは大躍進を遂げたにゃ。ドラフト同期のコナー・ベダード(シカゴ・ブラックホークス)を上回るファンティリの力強いプレーは、もうチームのエース格と言ってもいい。彼が本当の「王様」になる意味でも、今シーズン、期するものがある筈だ。
「みんながリーダー」そんなチームづくりへ🚀
最後に紹介したいのは、コール・シリンジャーの言葉です。
「うちのロッカールームには素晴らしいリーダーたちがいる。いいリーダーは、誰でもリーダーになれるってわかってるんだ」と語ったシリンジャー。
誰かが何か意見を言ったときに、みんなそれを自然に受け止めて、普段通りの一日を過ごす——この発言は、今のブルージャケッツの雰囲気を象徴していると言えるでしょう。
「僕たちは本当に仲が良くて、若手も自分の意見を言いたいときには言えるし、それが必要なら遠慮せずにできるんだ。逆に、静かに行動でリードするのもOK。自然にできている。とにかく、全体として、僕たちはとても結束したグループだし、みんなが自分の“素”でいられていると感じてるよ」と締めくくりました。
まとめ
ブルージャケッツは、若手の成長だけでなくチーム文化の変革も進行中。若手が主体的に発言し、リーダーシップを発揮することで、ベテランも刺激を受けています。互いの強みを活かし合いながら築く新たなチーム力は、今後の勝負どころで大きな武器となるでしょう。
ファン必見の進化が続きます。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- Adam Fantilliはフルシーズン出場(82試合)で31ゴール/23アシスト/合計54ポイントを記録。プラス/マイナスは+4。ゴール数・ポイントともにキャリアベスト。
Kent Johnsonは68試合に出場し、24ゴール/33アシスト/57ポイント。プラス/マイナスは+2。シーズンを通じて得点・アシストの両方で成長を見せた。
Kirill Marchenkoは79試合で31ゴール/43アシスト/74ポイントをマーク。プラス/マイナスは+29と非常に高く、チーム内でも最上位クラスの貢献を示した。
Dmitri Voronkovは73試合出場で23ゴール/24アシスト/47ポイント。プラス/マイナスは+17。ゴールとアシストともに二桁を維持。
Cole Sillingerは66試合に出て11ゴール/22アシスト/33ポイント。プラス/マイナスは−11。成績としては“ステップアップ”とは言い切れないものの、一定の出場機会をもらい、安定した貢献を見せている。
Denton Mateychukはディフェンスマンとして、AHLとNHLを行き来しながら“ルーキー”としての一歩を踏み出した。2024-25シーズン前半はAHL(Cleveland Monsters)で27試合を戦い9ゴール/16アシストを記録。
NHLデビュー後はBlue Jacketsの残りの48試合中45試合に出場し、NHLルーキー・ディフェンスマンとしての試合時間ではチーム内で2番目に多いものの一つであった。NHLでは初ポイントを1月9日の試合で、NHL初アシストは12月31日。シーズン終了後、NHLオールルーキーチームに選出。
↩︎ - NHL公式/Blue Jacketsのサイトの記事“Fantilli, Werenski push each other through offseason training”(2025年8月18日付)がある。
記事の概要要約
この記事は、コロンバス・ブルージャケッツのベテランディフェンスマン、ザック・ワレンスキーと若手注目株のアダム・ファンティリが、オフシーズン中に共にトレーニングを重ね、お互いを高めあっている様子を描いている。
二人はアリーナ(USA Hockey Arena in Plymouth, Michigan)で朝練から始め、氷上トレーニングやジムでのワークアウトをこなしており、ワレンスキーは「自分がFantilliに道を示しているというより、彼はすでに道をわかっていて知っている」と評しており、Fantilliの自主性・勤勉さを強く称賛。
Fantilliも、ワレンスキーとトレーニングを共にすることを喜んでおり、「ただジョークを言ったり、会話したり、一緒にやることでいい刺激になる」と語っている。彼にとってワレンスキーはチームのリーダーであるだけでなく、ロールモデルでもあり、その存在が自身の成長に大きく影響しているとのこと。
また、記事では夏のトレーニング環境についても触れられており、Fantilliは大学時代の拠点に近いデトロイト郊外を夏季の拠点として選んでおり、その理由として「質の高い練習相手がそろっていること」「大学時代のつながりを保てること」などを挙げている。アイスと陸上(ジム)での両方を重視し、毎日コツコツと努力を積み重ねている様子が強調されている。
ワレンスキーは、Fantilliのこうしたトレーニング姿勢を評価し、「彼には夏に取り組むべきことが何かがわかっており、それをしっかりやっている」「毎日来て、本気で取り組んでいる(grind)」と述べており、Fantilliの成熟性、仕事ぶり、課題認識の高さが、彼を“尊敬される若手”にしているという観点が繰り返し表れている。
↩︎ - Adam Fantilliは2023年のNHLドラフトで全体3位(1巡目)指名。
Kent Johnsonは2021年のNHLドラフトで全体5位(1巡目)指名。
Cole Sillingerは2021年のNHLドラフトで全体12位(1巡目)指名。
Denton Mateychukは2022年のNHLドラフトで全体12位(1巡目)指名。
なお、Kirill Marchenkoは2018年ドラフトで第2ラウンド全体49位指名。
Dmitri Voronkovは2019年ドラフトで第4ラウンド全体114位指名。
↩︎ - 自陣でパックを持ったところから安全かつ効果的に中立ゾーンへ運び出し、攻撃へつなげるための基本戦術を指す。単なるクリアとは違い、味方との連携やパスワークを重視するのが特徴。成功すれば相手のフォアチェックをかわして主導権を握れるが、失敗すればターンオーバーから失点につながる危険もある。
ディフェンスは冷静にパスコースを探し、ウィングは壁際で受ける準備を整え、センターは低い位置から的確にサポートするなど、それぞれの役割が重要。また声掛けなどのコミュニケーションが不可欠で、練習では実戦さながらのプレッシャーを加えながら繰り返し行うことで精度を高めていく。
↩︎ - アメリカンフットボールのコーチであるP.J. Fleck氏(現・ミネソタ大学監督)は、「Bad teams, no one leads. Average teams, coaches lead. But elite teams, players lead.」と述べている。また、バスケットボールのコーチであるFrank Vogel氏(インディアナ・ペイサーズやロスアンゼルス・レイカーズ監督などを歴任)も、「A player-led team is better than a coach-led team, no doubt.」と語っている。
このように、選手が自らリーダーシップを発揮し、互いに責任を持ち合うことで、チームの結束力やパフォーマンスが向上するとされている。
↩︎