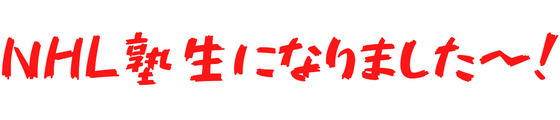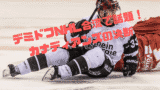はじめに
モントリオール・カナディアンズに、未来を変える新星が現れました。その名はレーン・ハトソン。卓越したスキルと成長意欲でチームをけん引し、ついに栄えあるカルダー賞を受賞――NHL新人王の登場です🌍!
数字だけでは語れない彼の魅力と飛躍の理由を、詳しく紐解きます。
参照記事:The Athletic「Why Canadiens rookie Lane Hutson’s Calder Trophy win is just the beginning」
🏒レーン・ハトソン、数字以上の価値を持つルーキー
モントリオール・カナディアンズのルーキー、レーン・ハトソンがNHLのカルダー・トロフィー1(年間最優秀新人賞)を受賞したニュースは、ファンにとっても嬉しい出来事でした✨ 彼の成績は確かに素晴らしく、パソコンの画面に表示される数字だけを見ても納得の受賞です。
でも、モントリオール・カナディアンズにとっての彼の真の価値は、その「数字の裏側」にある「情熱」と「動機」です。それはカルダー・トロフィーとは関係なく、別のトロフィーに関係しているのです✅。
6月10日・火曜日、ハトソンがNHLの新人シーズンで最も誇りに思っていることを尋ねられたとき、自分のスタッツは話題に上りませんでした。 「チームとして、最後まで戦ったことだね」とハトソンは言いました。「第82戦まで戦って、プレーオフ圏に入ることができた」。まさに「勝利への執念」が詰まった1年だったんですね🔥
受賞時の映像。ホームパーティーの場所に、わざわざでっかいトロフィーを持ってくるんですね。
彼がメディアの取材に応じた日、ハトソンがホッケーリンクからメディアに対応していたのは、非常に象徴的でした。
彼は次のシーズンに向けて新しいスティックやギアを試すため、ボストンで行われたバウアー・コンバイン2という用具の展示会場から、Zoomを通して語ってくれました。リンクの横に並ぶホッケースティック、背景には無機質な壁、まさに選手の典型的な“日常”を象徴する光景の中でのインタビューでした。
こんな感じで新しいスティックの試し打ちをしています。
🧊オフの日もスケートリンクへ通う理由
象徴的だったのは、それが彼の今シーズンの毎日を反映していたからです。ハトソンは、オフの日でもチームのトレーニング施設に足を運んでいました。スケートをし、自分だけの課題に取り組んでから帰宅していました。
なぜって?シーズン中、彼が語ったところによると、その理由は主に「他にすることがないから」なんて冗談交じりに語っていましたが、それがすべてではありません。実はそれ以上に「成長したい」という気持ちが強かったんです😊。
「趣味?特にないんですよね」と笑う彼ですが、ホッケーが何よりも大好き。それは、カルダー賞を獲得した感想を尋ねられたときの彼の最初の答えからも明らかです。
「毎日、自分の好きなことをして、それがモントリオール・カナディアンズでのプレーだなんて、本当に恵まれていると思います。1日1日を大切にしています」と、彼はその喜びを噛みしめていました😊
ハトソンはカルダー賞の投票3で圧倒的な支持を得て、191票中165票の1位票を獲得し、残り26票ではすべて2位にランクされました。
5位票以上を得た13人の新人の中で、スタンリーカップ・プレーオフに出場したのは、ハトソン、ローガン・スタンコーベン、ジャクソン・ブレイク(以上カロライナ・ハリケーンズ)、マッキー・サモスケヴィッチ(以上フロリダ・パンサーズ)の4人だけ。その中でも、チームをポストシーズンに導いた貢献度で、ハトソンは群を抜いていました。
📈プレーオフで見せた急成長
今季のハトソンは、ただ数字を積み上げただけの選手ではありません。実はプレーオフでの経験が、彼にとって大きな転機となりました。出場は短期間にとどまりましたが、ハトソンにとっては今オフシーズンにわたって記憶に残る経験となり、それは秋のトレーニングキャンプへとつながっていきます。
カナディアンズがワシントン・キャピタルズに5試合で敗れてプレーオフから姿を消した後、5月2日に「第1戦と第5戦4では、まるで別人のように感じた。自信を持って、何ができて何ができないのかが分かるようになった。
レギュラーシーズン序盤でも同じように調整が必要だったけど、プレーオフでその変化を体感できたのは面白かった。自分がチームに影響を与えられると分かるようになったし、でもまだまだ学ぶべきことはたくさんあると思う🌍」とハトソンは語っています。
初戦ではまだNHLの流れに慣れていない様子もありましたが、試合を重ねるごとに“このレベルでどう戦うか”をしっかりと吸収していったのです。
言い換えれば、このシリーズはハトソンにとって「情報源」となったのです。そして彼の大きな武器のひとつは、その情報を活用して、自分を阻む障壁を乗り越える方法を見つける能力です。小柄なディフェンスマンとして、これまでずっとそれで勝負してきました。
自分よりも大きな相手にどう立ち向かうか、守備の穴をどう突くか、どんな場面でどう判断するか──。それらを理解し、対応する力が彼の武器です💡
⏱「タイミング」を知ったルーキーイヤー
彼が今季(24-25シーズン)開幕時に持っていたNHLの実戦経験はわずか2試合分。それでも彼が言及した「レギュラーシーズン序盤の調整」は特筆すべきものでした。プレーオフでのハトソンは、レギュラーシーズン初期の彼とはまったく違っていました。
シーズン序盤、ハトソンはパックを持てば即アタック!というようなプレースタイルでした。でもNHLの世界では、それだけでは通用しない場面も多いんです。彼はすぐに、スケートの切り返しよりも「いつ攻めるべきか」という“タイミング”の重要性を理解していきました✍️。
「試合のテンポ、どれだけ早く物事が起こるか、そして1試合ごとにまったく違う展開になること、そのすべてにどう備えるかを、少しずつ理解し始めたと思う。何度も経験すれば、次に何が来るかある程度予想がつくようになる。でも、同時に試合中に何が起こるか分からないという備えも必要かな」と彼は話してくれました。
そうした気づきを経て、プレーオフでは“判断力とタイミング”を武器に成長を遂げたのです。数字以上に、未来への財産になる経験だったのは間違いありません🌟
一方で、NHLの他のチームも彼のプレースタイルを分析し、彼がこれまで見つけてきた守備の穴や隙を封じようと対策してくるはずです。これは、才能ある若手選手がNHLで必ず通る“チェスのような駆け引き”です。
そして、今季のカナディアンズの成功においてハトソンがどれほど重要な存在だったかを考えると、来季は対戦相手の集中マークがさらに厳しくなることが予想されます。それは、プレーオフでキャピタルズの指揮官スペンサー・カーベリーが実際に示した通りです🌍。
📊データが示す、ハトソンの真価と課題
今季、ハトソンとニック・スズキが一緒に氷上にいた5対5の時間は552分。その間、カナディアンズは相手を40-19で上回る得点力を発揮し、シュート試行5でも57.7%の支配率を記録しました(※データ提供:Natural Stat Trick6)📈しかし、彼らが氷上にいないときは、93-54で相手に得点され、シュート試行数の支配率も44.45%に低下しています。
でも、数字には裏側もあります。実は彼らが氷上にいたときの攻撃開始地点の約75%が「オフェンシブゾーン」だったんです。それでもなお、ハイリスクなチャンスをやや多く相手に許していたり、期待値に対して実際の得点率が高すぎたり7──といった「運に支えられた部分」も見え隠れしています。
つまり、まだ改善の余地はあるということです。だからこそ、ハトソンはオフの日にもリンクへ通って努力を続ける。
「ホッケーの試合に勝つという感覚、それを最高レベルで、何度でも、正しい方法で実現する。それが、自分に必要なモチベーションになっている。そしてそれは、チームの仲間みんなが持っている思いじゃないかな」とハトソンは語ります。「ただ勝ちたい、それだけなんです」と話すその瞳は、キラリと光っていました✨
レギュラー・シーズンでのゴール数は6。アシスト60が光る。来シーズン、ゴールがもっと増えそうな予感。
🔁“レーンらしく”育てた指導者の存在
ハトソンの成長には、カナディアンズのマーティン・セントルイス8監督の影響も大きかったようです。監督は「レーンにはレーンらしくやらせる」と繰り返していました。これは決して、ハトソンの改善点に目をつぶっていたという意味ではありません。むしろ、彼の学習能力を信じて「自分で気づく経験」を重視していたんですね✅。
殿堂入り選手として、セントルイス自身も、現役時代は“自己成長力”が最大の武器だったと語っています。そして今、その「成長力」をハトソンも確かに持っていることが明らかになりました。
カルダートロフィーを受賞したことで、2年目のシーズンには高い期待が寄せられますが、これまでの彼のキャリアを見れば、その期待に応える、あるいはそれを上回る可能性が十分あると感じさせます💪

シャークスのマックリン・セレブリーニにケガがなかったら、どうなっていたか分からないけど、ほぼコンスタントに新人らしからぬ活躍をしていたのが評価されたんだろうにゃ。昨シーズン、2試合とはいえ、雰囲気を経験できたのも大きい。来シーズン、ロシアから強力な相棒も来るし、さらなる成長曲線を描くのではなかろうか。
🌟カルダーの先へ、新たな希望と仲間
ハトソンは、1972年のケン・ドライデン9以来、実に半世紀ぶりとなるカナディアンズからのカルダー賞受賞者となりました😊。ちなみにその年、ハトソンの父ロブさんが生まれたばかりだったそうです。
さらに来季は、新たなスター候補であり有力なカルダー候補イワン・デミドフの加入も控えています。シーズン終了時、ハトソン自身が「彼はスターになる」と太鼓判を押すほどの逸材✨
デミドフについては、以前記事にしました!
「大事な場面でのパックさばき、そしてあの落ち着きと自信。あれは教えられるものじゃない。スター選手になる素質があると思う。そうなってほしいし、見るのが楽しみだ」と語るほどです。着実に、モントリオール・カナディアンズは明るい未来へと歩みを進めています。ハトソンという若き才能が、その中心にいることは間違いありません🏒🔥
まとめ
レーン・ハトソンの1年目は、努力と成長に満ちた濃密なシーズンでした。数字の裏にある姿勢や学びの力こそ、彼の真価。来季はさらなる飛躍が期待される中、カナディアンズの未来を背負う存在として、ますます目が離せません。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- Calder Memorial Trophyは、そのシーズンで最も優れた新人選手に贈られる名誉ある賞。1936-37シーズンに始まり、NHLの初代会長フランク・カルダーにちなんで名付けられた。
受賞資格のポイント:
○過去のレギュラーシーズンで25試合以上、または過去2シーズンでそれぞれ6試合以上出場経験がないこと。
○受賞対象シーズンの9月15日時点で26歳以下であること(これは「マカロフ・ルール」として知られています)。
○選考はプロホッケー記者協会による投票で行われる。
↩︎ - Bauer Combineは、大手ホッケー用具メーカーBauerが開催するイベントで、一般的な展示会とは少し異なっている。これは主にプロや有望な若手選手を対象とした、パフォーマンス測定や最新製品のテストイベントを指す。
ボストンなどのホッケーが盛んな地域で不定期に開催され、選手はシュート速度やスケート能力などを測定したり、開発中の新しいスティックやスケートなどを試したりする。NHL選手が参加することもあり、次世代のホッケープレーヤーの育成と用具開発の両面に関わる、重要なイベント。
↩︎ - 投票結果は以下の通り。
2024-25 Calder Trophy Voting
Pts (1st-2nd-3rd-4th-5th)
Lane Hutson, MTL 1832 (165-26-0-0-0)
Dustin Wolf, CGY 1169 (15-96-59-17-1)
Macklin Celebrini, SJS 1104 (11-61-106-12-1)
Matvei Michkov, PHI 645 (0-8-26-151-6)
Cutter Gauthier, ANA 92 (0-0-0-6-74)
Will Smith, SJS 62 (0-0-0-2-56)
Logan Stankoven, CAR 22 (0-0-0-2-16)
Zack Bolduc, STL 20 (0-0-0-1-17)
Jackson Blake, CAR 9 (0-0-0-0-9)
Marco Kasper, DET 7 (0-0-0-0-7)
Mackie Samoskevich, FLA 2 (0-0-0-0-2)
t-12. Drew Helleson, ANA 1 (0-0-0-0-1)
t-12. Denton Mateychuk, CBJ 1 (0-0-0-0-1)
(10-7-5-3-1 points allocation)
↩︎ - プレーオフ5試合に出場し、5アシストを記録したがノー・ゴール。プラス/マイナス評価が−5となっていて、攻撃面でレギュラー・シーズンのように貢献できなかった。シュート数を見ると、第1〜3戦はゼロで、第4、5戦合計で5本。ハトソン個人がどうにかプレーオフの感覚を掴んできた所で、チームは終戦となってしまったのである。
↩︎ - The Shot Attemptsは、単なるゴールを狙ったシュート数ではなく、より高度なスタッツ分析(アドバンスド・スタッツ)で使われる重要な指標。これは、ゴール枠内シュート(SOG)、枠外シュート、そして相手にブロックされたシュートのすべてを含む。
チームがどれだけ積極的に攻撃を仕掛け、相手ゴールにプレッシャーをかけているか、つまり試合の主導権やゾーン支配の度合いを測るのに役立つ。このスタッツが多いチームは、長期的に見てより多くの得点を挙げ、勝利する傾向があるため、現代ホッケー分析において非常に重視されている。
↩︎ - NHLの詳細な高度統計データ(アドバンスド・スタッツ)を提供する主要なウェブサイト。従来のゴール数やアシスト数だけでは分からない、試合の「質」や選手の「貢献度」を深く分析するために利用される。
特に、チームのシュート試行数や、期待ゴール数といった指標を通じて、チームがどれだけ攻撃の主導権を握り、質の高いチャンスを作っていたかを客観的に評価できる。ファンやアナリストが、データに基づいたより深いホッケーの分析を行う上で不可欠なツール。
↩︎ - ゴール期待値(xG: Expected Goals)は「どれだけ質の高い得点チャンスを作ったか」を示す指標。これに対して、実際の得点率がxGを大きく上回ることは、一見すると素晴らしいパフォーマンスに見える。
しかし、これは選手やチームの卓越した決定力を示す一方で、一時的な「運」や好調期に支えられている可能性も指摘される。スポーツアナリティクスでは、このような「高すぎる得点率」は、長期的には平均値に「回帰」していく傾向があると考えられている。
つまり、現状は好調でも、それが持続可能かどうかという視点が重要。チームや選手を評価する際には、単なる得点数だけでなく、その裏にあるxGとの関係性も考慮することで、より本質的なパフォーマンスが見えてくる。
ハトソンの場合、期待ゴール率(xG%)は52.51%だったのに対して、実際のゴール率(GF%)は67.8%と大きく上回っていた。
↩︎ - カナダ出身、ドラフト外選手ながらも、NHLで1,134試合に出場し1,033ポイントを獲得するなど、輝かしいキャリアを築いた。
特にタンパベイ・ライトニングでの活躍が知られており、2004年にはスタンレーカップ優勝に貢献。個人タイトルも多く、2003-04シーズンにはレスター・B・ピアソン賞(現テッド・リンジー賞)とハート記念賞を受賞。レディ・バイング記念賞を3回、アート・ロス記念賞を2回獲得し、2013年にはNHL最年長得点王にも輝いている。
国際舞台でもカナダ代表として活躍し、2004年ホッケーワールドカップ優勝、2014年ソチオリンピック金メダル獲得に貢献。2018年にはホッケーの殿堂入りを果たし、NHL史上最高のドラフト外選手の一人としてその名を刻んでいる。
↩︎ - カナダ出身、ゴールキーパーとして、NHLモントリオール・カナディアンズで歴史的な活躍を見せた。1964年のドラフトでボストン・ブルーインズに指名された後、モントリオール・カナディアンズへトレード。
1971年から1979年までカナディアンズでプレーし、その間に6度のスタンレーカップ優勝という偉業を達成。個人としても、1971年にコーン・スマイス賞(プレーオフMVP)、1972年にはカルダー・トロフィー(最優秀新人賞)を受賞している。
レギュラーシーズンでは勝率74.3%、平均失点2.24という驚異的な成績を残し、1983年にホッケーの殿堂入り。2007年にはカナディアンズによって背番号29が永久欠番となった。 ↩︎