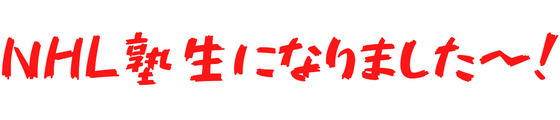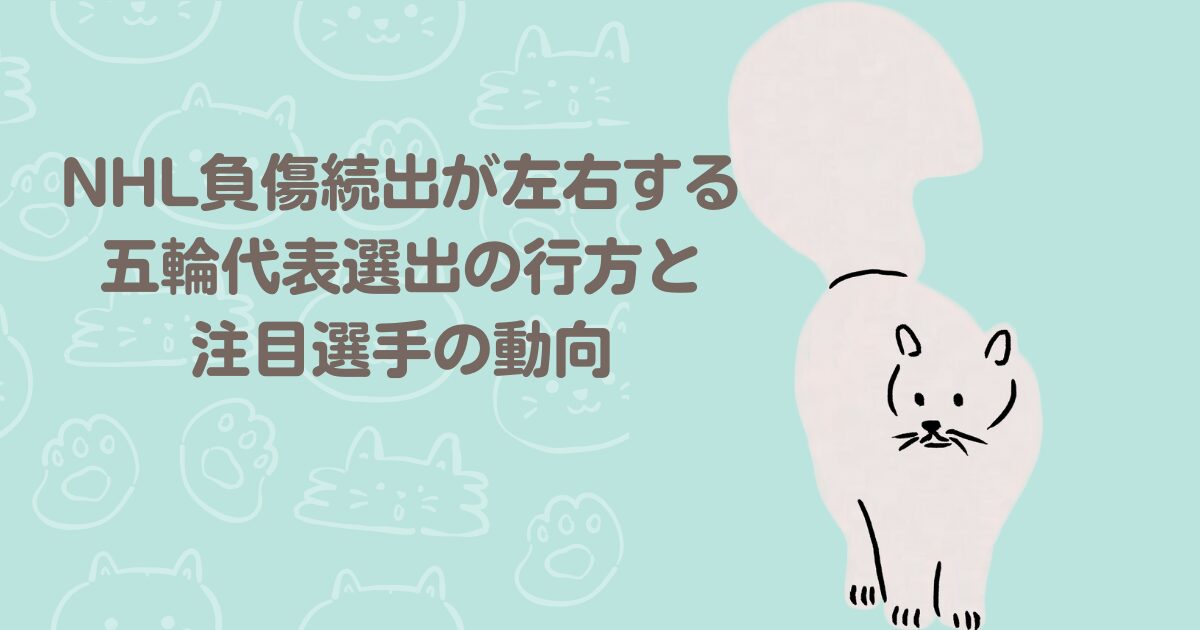はじめに
NHLでは大物選手の負傷が相次ぎ、五輪代表チームのロスター編成も流動的です⚡️。しかし、復帰するクイン・ヒューズやブレイディ・カチャック、活躍が目覚ましいジェイソン・ロバートソンやコナー・ベダードなど、注目選手の動向に期待が高まります🏒。
2010年バンクーバー五輪でのクロスビーのゴールや、プライスやベルジュロンの金メダル経験が示すように、五輪は選手たちのレガシーを刻む舞台。2026年ミラノ・コルティナ五輪も熱戦必至です✨。
参照記事:NHL公式サイト「Zizing ‘Em Up: Injuries becoming alarming trend ahead of Olympics」
大物選手の負傷が続くNHLと五輪への影響⚡️
NHL.comのスタッフライター、マイク・ザイズバーガーは1999年からNHLを取材しているベテラン記者。毎週月曜日には、長年培ってきたホッケー関係者との幅広いネットワークを活かし、「Zizing ‘Em Up」というウィークリーコラムで、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた展望を届けています📄。
最近、ロサンゼルス・キングスのドリュー・ダウティが土曜日、オタワのカナディアン・タイヤ・センターで歩行用ブーツ姿で退場1したことが話題になりました。この出来事は、大物選手の負傷が相次ぐ不安な流れをさらに強調するものでした。
そして2026年ミラノ・コルティナ五輪に向けてチームを編成する、アメリカ代表のビル・ゲリンGMやカナダ代表のダグ・アームストロングGMといった人物にとって、ロスターを埋めるためのバックアッププランがより重要になっています。
試合の2日前、ダウティは「カナダ代表入りは常に頭にある」と語っていましたが、オタワ・セネターズ戦で足にシュートを受けた下半身の怪我により、1-0の勝利の途中で戦列を離れることになったのです。
ダウティの守備とチームへの影響🛡️
先週木曜日、ダウティ自身も語っている通り、「そもそも自分は攻撃力で代表に選ばれるタイプじゃない。重要なのは守備だ」とのことです。ここまで19試合で8ポイント(2ゴール・6アシスト)、プラス/マイナス評価でプラス6を記録しており、キングスのジム・ヒラー監督からも堅実な守備が高く評価されています。
しかし怪我の程度はまだ明らかではなく、現時点では「日々の状態次第」とされています。それでも彼の名前は、すでに各国代表候補に挙がっている、あるいは代表入りを争っているNHL選手たちの“負傷者リスト”に加わることになりました。
アメリカ代表のゲリンGM2とスタッフにとっても、今の状況は容易ではありません。アメリカ人選手の中には負傷や故障者リスト入りが相次いでいるからです。
主な選手を挙げると、ニュージャージー・デビルスのジャック・ヒューズ(指・故障者リスト)、フロリダ・パンサーズのマシュー・カチャック(鼠径部・故障者リスト)、オタワ・セネターズのブレイディ・カチャック(親指・故障者リスト)の3人のフォワード。
さらに、ボストン・ブルーインズのチャーリー・マクアヴォイ(上半身・日々の状態次第)、カロライナ・ハリケーンズのヤコブ・スレイヴィン(下半身・故障者リスト)という2人のディフェンス。
そして、バンクーバー・カナックスのサッチャー・デムコ(下半身・週単位の離脱)と、シアトル・クラーケンのジョーイ・ダコード(上半身・故障者リスト)という2人のゴールテンダーです。多くの選手が戦列離脱や状態不安定の中にあると言えます。
希望の兆しも見える選手たち🌟
とはいえ、全てが暗いわけではありません。カナックスのクイン・ヒューズやセネターズのブレイディ・カチャックには、明るい兆しも見えています。
ヒューズは日曜日に復帰すると、いきなり存在感を発揮3。ライトニング戦で4アシストを記録し、チームは6-2で勝利しました⚡️。一方、セネターズのキャプテン、ブレイディは金曜日にスケートを再開し、次の7連戦のロードトリップに帯同する予定です。
カナダ代表でも、ライトニングのアンソニー・シレリ(上半身・日々の状態次第)やゴールデンナイツのマーク・ストーン(手首・故障者リスト)といったフォワードや、ディフェンスのトーマス・ハーレイ(下半身・週単位で様子見)、ゴールテンダーのエイデン・ヒル(下半身・故障者リスト)が負傷中です。それでも、ライトニングのブランドン・ヘイグルは、上半身の怪我で1試合を欠場した後に、カナックス戦に出場しました。
怪我の影響とロスター調整の重要性🏒
ゲリンGMにとって、リーグ全体で負傷者が増えている現状は、各国がロスターを確定する期限が1月1日前後まで延長されたことの重要性をより高めています。これは昨年2月の「4 Nations Face-Off」より約1か月遅い時期です📅。
「追加の時間は本当に重要だ。単にその時調子が良い選手を見極められるだけでなく、誰が健康で、誰がそうでないのか判断できるから」とゲリンは先週NHL.comに語っています。
特に気になるのはジャック・ヒューズの状況です。デビルスによれば、ホッケーとは無関係の怪我で手術を受け、6週間後に再評価される予定。もし8週間で復帰できれば、2月の五輪でアメリカ代表としてプレーできる可能性があります。ただし、それはあくまで「大きなもし」です。
五輪代表選手の現状と期待🌍
現時点で、USAホッケーは“ついていない”と言われても仕方ありません。6月に発表された最初の代表入り6選手のうち、比較的健康なのはゴールデンナイツのジャック・アイケルだけ。他の5人――クイン・ヒューズ、マクアヴォイ、マシューズ、そしてカチャック兄弟――はいずれも負傷中です。
しかし、後者2人については希望が見えてきました。ブレイディは前に述べた通り、一方、マシューはオフシーズンの手術から順調に回復しており、2週間後にはオンアイス練習を開始できる可能性があるとパンサーズのポール・モーリス監督が明かしています。マシューは8月に内転筋断裂とスポーツヘルニアの修復手術を受けています。
ただし、同僚でパンサーズのキャプテン、アレクサンダー・バーコフはトレーニングキャンプでの深刻な膝の怪我により、フィンランド代表として五輪を欠場することになっています。これは、今年に入って続いている“異常なほどの怪我の多さ”の最初のケース4であり、五輪ロスターは年明けギリギリまで揺れ続けることになりそうです。

USAホッケーの現状は、正直かなり厳しいと言わざるを得ないにゃ。フィンランドも最もキーマンとなる選手が不在では、先行きが厳しい。主力クラスが次々と離脱し、五輪を目前に控えたこのタイミングでの負傷ラッシュは、まさに“何かに試されている”状況。このまま年明けまで落ち着くのかどうか、まさに天に祈るような思いだ。
五輪実況アナウンサーの思い出🎤
今回の五輪でカナダとアメリカでの中継を担当する実況アナウンサー、クリス・カスバートとケニー・アルバートにインタビューを実施予定です。今回はまず、カナダ・Sportsnetのカスバートに話を聞きました。
――まず最初に、クリスさんにとって最高の五輪の思い出は何ですか?
「2010年バンクーバー五輪でシドニー・クロスビーの“ゴールデンゴール”を実況した瞬間かな。カナダがアメリカを3-2で延長勝利したあの試合5さ✨。うん、間違いなくキャリア最大のハイライトだね。もし他にそういう瞬間があるなら、喜んで加わりたいよ。
クロスビーの「ゴールデンゴール」のシーンについて、世界各国のスポーツニュースがどう伝えたのか、を集めた映像。意外と面白い企画。五輪がそれだけ注目されている証。
ただ、昨冬の『4 Nations』でのコナー・マクデイヴィッドの延長ゴールも素晴らしかった。その試合、トーナメント、そして“ベスト対ベスト”の対決という状況を考えると、本当に特別だった。今はあのシドの瞬間に匹敵する瞬間を見られるか楽しみにしているよ」。
――あのシドの瞬間はどれほど非現実的に感じましたか?
「実況で大事なのは、とにかく正確に伝えること。五輪の実況席からの視界は概ね完璧だけど、イグラ・イグナラからクロスビーへのパスが通った遠いコーナーだけは少し見えにくかったんだ。僕は完璧主義者なので、大事なプレーがあの場所で起きたらどうしようと心配していた。でも結果的にうまくいったし、不満はないよ」。
――その日について他に覚えていることはありますか?
「あの試合を最初から最後まで通して見たことは一度もない。実況には満足していたし、それがキャリア最大の試合だったから。ゴールシーンはSNSとかで聞いたことあるけど、試合全体は見ていないんだ」と振り返ります。
イタリア大会の展望と注目選手🇮🇹
――将来的に、イタリアで行われるトーナメントの優勝予想は?
「負けるまではカナダを推すが、確実というわけじゃない。次世代の選手たちが迫っているからね。2010年の試合のゲームシートを見返してみると、クロスビーはまだ22歳だった。今はコナー・ベダードやマックリン・セレブリーニといった若手が台頭している。彼らが代表入りするかどうか、注目だ👀」。
――『4 Nations』の現実は、アメリカがあと1本のシュートで優勝を逃したというものです。今回のアメリカ選手層は過去最高と言えるでしょうか?
「つい最近、1996年にワールドカップで優勝したアメリカ代表を振り返るドキュメンタリー6に参加したんだ。あのチームも相当な選手層だった。マイク・モダノ、キース・タカチュク、ブレット・ハル、ブライアン・リーチ…と、挙げればキリがない。
あの時が初めて、アメリカが『カナダを倒すぞ』と意識して臨んだ大会だったと思う。そしてその世代は今、イタリアに向かう新たな選手たちに引き継がれている。本当に実力があるから、彼らなら堂々と戦えるだろう」。
――最後に、過去の五輪では大きなアイスリンクで行われていましたが、今回はNHL規格のリンク7です。大会への影響は?
「大きく影響があるね。これでNHL大会と言える形になる。ただしルールは異なる。もしトム・ウィルソンのような選手が選ばれれば、フィジカルプレーに注意しなければならない。そういう点では、スタンレーカッププレーオフとは違った戦いになるだろう」。
注目株:ジェイソン・ロバートソン🔥
五輪代表入りを目指す選手の注目株として、ダラス・スターズのフォワード、アメリカのジェイソン・ロバートソンが挙げられます。
26歳の彼は、チームの5連勝に大きく貢献。特に土曜日のフィラデルフィア・フライヤーズ戦では、ナチュラルハットトリックを達成し、アメリカン・エアラインズ・センターで5-1の勝利に導きました🏒。
リーグ通算6回目のハットトリック(レギュラーシーズン5回、プレーオフ1回)で、この素晴らしい活躍はアメリカ代表関係者の目にも留まったはずです。直近3試合で9ポイント(6ゴール・3アシスト)を記録しており、過去8試合中7試合で少なくとも1ポイントを獲得しています。
4 Nationsで代表入りを逃した悔しさをバネに、現在は五輪代表入りに向けて強力なアピールを続けています。
ロバートソンが五輪代表に選ばれ、このような感じで喜びを爆発させる日が来るのか。国際舞台に立てば、この男は必ずやってくれる!
若手注目選手へのグレツキーの評価🌟
シカゴ・ブラックホークスのフォワード、コナー・ベダードは、最近のTNT放送でウェイン・グレツキーから「カナダ代表入りに向けてプレーしている8」とコメントされたことについて語りました。
「彼がそう言ってくれるのは嬉しいね。ホッケー界で最も偉大な人物のひとりだから。もし彼が自分のことを話してくれるなら、それは明らかに良いことさ。自分のプレーを気に入ってくれているのは本当に嬉しい」とベダードはコメントしています。
若手選手にとって、グレツキーの言葉は大きな励みとなり、五輪代表入りへのモチベーションをさらに高める要素となっています💪。
五輪レガシーを築いた選手たち🏅
先週行われたホッケー殿堂入り式典も大成功に終わり、2026年クラスの有力候補を見てみると、五輪で確かな足跡を残した2人の選手がいます。
1人目は元モントリオール・カナディアンズのゴールテンダー、ケアリー・プライス。2014年ソチ五輪でカナダの金メダル獲得を支えました。5試合で平均失点0.59、2度のシャットアウトを記録するなど、五輪史上でも屈指の堅守を見せました。
2人目はボストン・ブルーインズのフォワード、パトリス・ベルジュロン。史上屈指の2ウェイプレーヤーとされ、相手国のトップラインを封じる役割を担いました。2010年と2014年の金メダル獲得時には3アシスト、プラス2でチームに貢献しました。
プライスもベルジュロンもNHLでの輝かしい実績は当然評価されるべきですが、五輪での活躍がそれぞれのレガシーをさらに際立たせています✨。
まとめ
NHLの負傷者が増える中、代表選考は最後まで状況が変わり続けそうです。それでも、各国は追加期間を活かし、選手の状態やパフォーマンスを慎重に見極めています。復帰が近づく選手、調子を上げている選手、それぞれの動向がロスターを左右する鍵になります。
また、五輪🇨🇦🇺🇸で輝いたプライスやベルジュロンのように🏒✨、この大会は選手のキャリアを語る上で欠かせない場所でもあります。ミラノ・コルティナ五輪🏅では、どんなドラマが生まれるのか注目です。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- 11月15日のオタワ・セネターズ戦で、ブロックしたシュートがブーツ部分に当たり下半身を痛め、ウォーキングブーツ姿で退場。その後ロサンゼルス・キングスのジム・ヒラー監督は「週単位(week-to-week)」の離脱と発表している。
この怪我は以前の足首骨折とは別のものとされ、監督は「しっかり治る」と楽観視。なお、2024年9月には左足首を骨折し手術を受けており、今季復帰後も安定した戦列復帰が課題となっていた。
今回の離脱が五輪代表(カナダ代表候補)への影響も懸念されており、年明けまでロスターの構成に不確定要素を残す可能性がある。
↩︎ - 代表GM(General Manager)は、クラブチームのGMと同様に「チームの中枢」を担う役割だが、五輪や国際大会では任務の幅がさらに広がる。まず最も重要なのはロスター編成──候補選手のスカウティングや選考基準の設定、最終メンバーの決定を主導することである(現場のコーチや選手係と密に連携しながら進行)。
また、代表チームの管理グループやコーチングスタッフの任命、選手との窓口役(選手の健康状態や意向の把握)もGMの重要な仕事で、長期的な大会計画に沿って複数の大会で一貫した体制を築くことが求められる。
国際大会特有の業務としては、NHLや各クラブとの調整(選手招集のタイミングや保険・医療面の確認)、渡航・ビザやチーム運営(移動・宿泊・トレーニング計画)の取りまとめ、そして万一の負傷や離脱に備えた代替案(コンティンジェンシー)の準備が挙げられる。
これらは大会直前まで流動的な判断を迫られるため、GMには迅速な意思決定力と広い人脈・交渉力が不可欠。
↩︎ - クイン・ヒューズは直近の復帰戦で存在感を示し、3試合ぶりに出場した試合で4アシストを記録するなど復調の兆しが明白。復帰前は“試合を欠場”する場面もありましたが、コーチ陣は彼の状態を慎重に見ながらも攻守での影響力を高く評価しており、ここ数試合でのパフォーマンスは代表候補としての評価を後押ししている。
一方、ブレイディ・カチャックは10月中旬の親指骨折で手術を受け、当初の見通しは6〜8週間の離脱だった。最近はチーム練習に合流して氷上での調整を開始しており、クラブ側は彼を今後の長期ロードトリップに帯同させる方針を示している。復帰タイミングは当初の見通しどおりであれば年内〜年明けが目安とされ、状態確認を経て実戦復帰が判断される見込み。
総じて言えば、ヒューズは即戦力としての復帰を果たしつつあり、代表選考にプラスに働く可能性が高いのに対し、カチャックは手術後の規定回復期間を踏まえた“段階的な復帰”という状況。両者ともに最終的な代表参加可否は医療スタッフの評価と実戦でのフィット感が鍵になり、GMらがロスター決定を先延ばしにする理由にもなっている。
↩︎ - マシュー・カチャックは今夏に内転筋断裂とスポーツヘルニアの修復手術を受けて以降、リハビリを順調に進めており、パンサーズのポール・モーリス監督は「今後2週間ほどで氷上トレーニングに復帰する見込み」とコメント。
復帰が予定どおり進めば、練習再開は11月後半〜12月初旬になり、実戦復帰は12月以降になる可能性があると報じられている。一方で、カチャックは当初、手術を選んだ場合2〜3か月の欠場も想定されており、復帰時期はリハビリの経過次第で前後する点に注意が必要。
対してアレクサンダー・バーコフはトレーニングキャンプ中の負傷で右膝の前十字靭帯(ACL)と内側側副靱帯(MCL)を損傷し、手術を受けており、復帰見込みは7〜9か月とされているため今季並びに2026年ミラノ・コルティナ五輪の出場はほぼ不可能と報じられている。
チームと現地報道はバーコフの長期離脱を公式に認めており、フィンランド代表の補充や戦術面での影響が避けられない状況。
↩︎ - 2010年バンクーバー五輪の男子アイスホッケー決勝は、開催国カナダと宿敵アメリカによる歴史的な一戦となった。カナダは序盤から主導権を握り、2-1とリードしたまま終盤を迎えたが、第3ピリオド残り24秒でアメリカのザック・パリーゼが同点ゴールを決め、会場は緊張に包まれた。
試合は延長戦にもつれ込み、“次に決めた方が勝ち”という絶対的なプレッシャーの中で生まれたのが、シドニー・クロスビーの「ゴールデンゴール」。延長開始からおよそ7分、クロスビーは左サイドからのパスを受け、そのままゴール右下へシュートを突き刺した。
この瞬間、カナダは金メダルを獲得し、国内はもちろん世界中のホッケーファンが熱狂。母国開催での勝利、劇的な決着、若きエースによる決定的な一撃という要素が重なり、このゴールは五輪史でも最も象徴的なプレーの一つとして語り継がれている。
↩︎ - 「Orchestrating an Upset: The 1996 World Cup of Hockey」(監督:ギャリー・バットマン)という作品。
この映画では、当時のチーム構成、予選リーグや決勝での激闘、そして大会を通じてアメリカが見せた“番狂わせ”の勝利を丁寧に描いている。ナレーションはメタリカのジェームズ・ヘットフィールドが担当し、監督ルー・ラモリッロの「オーケストラ」に例えるチーム作りの哲学や、選手たちの当時の心理状態、ライトな視点とともに深い背景を伝える構成。
また、USA Hockey公式サイトの振り返りでも、決勝第3戦でマイク・リクターが35セーブの活躍を見せ、残り3分18秒でトニー・アモンテが決勝ゴールを決め、アメリカが劇的な逆転優勝を果たしたという歴史的瞬間に焦点が当てられている。
このドキュメンタリーは、あまり広く語られることのない「米国が最強国に挑み、勝利した1980年以降最大の国際大会勝利」の裏側を、選手やGMらの証言を通じてリアルに掘り下げている。
↩︎ - まずアイス面の大きさだが、NHL規格リンクは「200フィート×85フィート(約60.6m×25.9m)」なのに対し、国際・五輪規格(IIHF)リンクは「197フィート×98.5フィート(約60m×30m)」と、幅がかなり広いのが特徴。
幅が広い分、IIHFリンクでは選手同士の距離が取りやすく、スペースを使ったパスやスピード重視の展開が可能になる一方、NHLサイズではフィジカル・接触プレーが活かされやすく、ボードプレーや高速展開が強調される傾向がある。
ではなぜ、ミラノ・コルティナ2026五輪ではNHL規格を使うのか。その背景には、NHL選手が久々に五輪に参加することが決まった事情と、試合の方向性をNHLスタイル寄りにしたい思惑がある。
NHLと選手会、国際アイスホッケー連盟(IIHF)、IOCが合意してNHL所属選手のオリンピック復帰が正式決定しており、NHL選手が慣れ親しんだリンクでプレーさせることでパフォーマンスを最大化し、視覚的・戦略的にも“NHLらしい”激しいホッケーを五輪で見せる狙いがあると分析されている。
ただし、一方で開催地のリンク建設が遅れており、主競技会場であるミラノのSantagiuliaアイスホッケーアリーナは完成がギリギリで、テストイベントさえ開催が流動的という報道もある。
↩︎ - ウェイン・グレツキーは最近のTNT中継で、コナー・ベダードについて非常に高く評価し、「彼はカナダ代表の五輪チームにふさわしい」との見方を示した。具体的には、18歳でブラックホークスに加入したベダードについて、「若さとプレッシャーの中でもひるまず、オフシーズンに懸命に努力して今のレベルに到達している。彼なら代表入りを勝ち取れる」とコメント。
さらに「彼はチームメイトやメディアの注目でも怯まず、自分のプレーを貫いている」と、その精神面も称賛した。
また、グレツキーは「彼を五輪代表から外すのは難しくなってきている」とも付け加え、ベダードが国際舞台でも主力級としての活躍を見せる可能性を強く示唆。この発言は、ホッケー界の“史上最高”が次世代スターに対して抱く期待を表しており、ベダード自身も「代表入りを強く望んでいる」と語っていることから、五輪ロスター争いにおいて非常に重要な意味を持つ評価である。 ↩︎