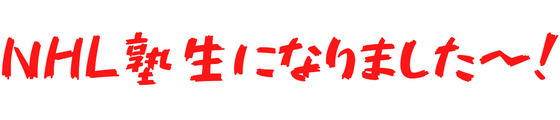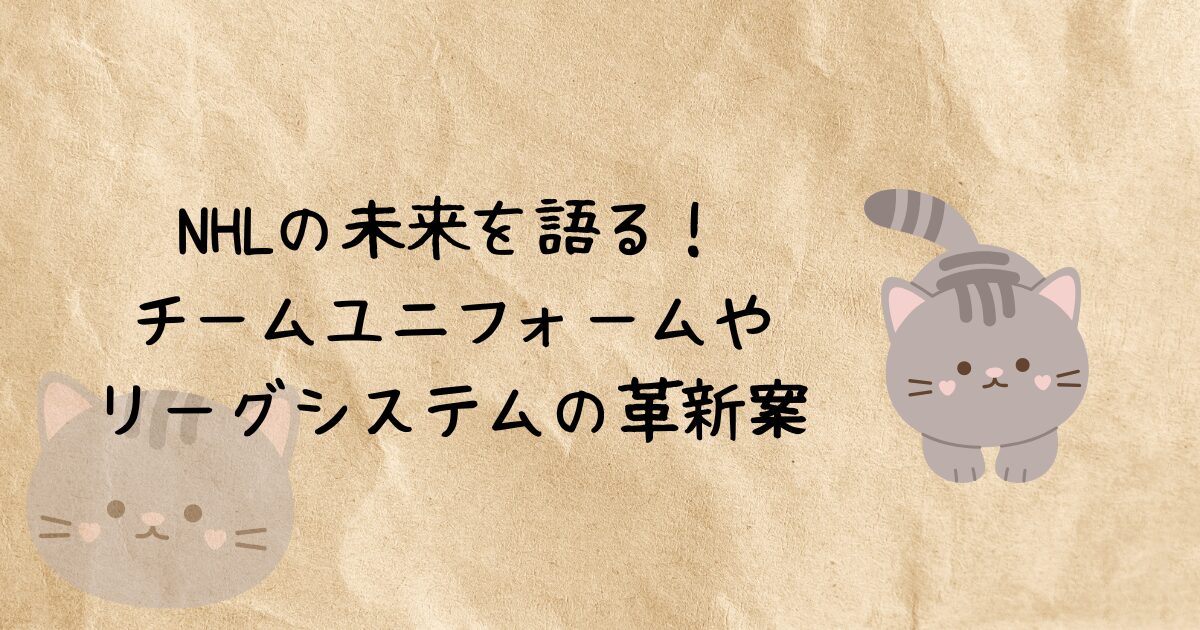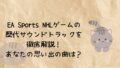はじめに〜ホッケー界に革命を!🔥ファンが夢見るNHL改革案✨
アイスホッケーファンの皆さん、10月開幕までの時間、どうお過ごしですか?🏒✨今日は、ちょっと面白い話題についてお話ししたいと思います。
もし私たちがNHLのルールを自由に決められるとしたら…?そんな夢のような「もしも」を、ホッケー好きの有識者たちが語り合っているのです!その中から、特に「これは面白い!」と思った提案をいくつかご紹介しますね。どれもホッケーを愛するファンならではの、情熱あふれるアイデアばかりですよ!💖
※本記事は、「2025年版NHL改革ドラフト!ホッケーの未来を変えるアイデア」の続編です。
参照記事:The Athletic「‘Fix The NHL’ draft: Non-standard rinks, fun uniforms, 3-point games — and relegation?」
ユニフォームで個性を爆発させよう!🎨
第2ラウンド
ピック2.1.ロブの意見:ユニフォームで楽しもう
アイスホッケーのジャージって、本当にカッコ良くて、最高のものばかりです!😍でも、NHLはチームがユニフォームで何か面白いことをするのをあまり許していません。
もっとチームの個性を活かしたユニフォームが見たい!というファンの思いに応えて、ロブは「チームがいつもと違うユニフォームを着て、ホームゲームを4試合行えるようにする」ことを提案しています。
これなら、その過程で追加の収益を生み出すことができるし、ファンもきっと大喜びですよね!💸✨例えば、ペンギンズがセントパトリックデーのパレードがある日にちなんで、ピッツバーグで特別なジャージ1を着たりすると、よく売れるでしょう。
ペンギンズのセントパトリックデー用ジャージ。オシャレなのに、なぜか非売品だそうです。
カルガリー・スタンピード2というお祭りに合わせてデザインされた、フレームスのジャージもぜひ見てみたいです。
カルガリー・スタンピードは、こんな感じです。
そして、ついでに言えば、選手はすべての試合で、色やデザインの異なるグローブやスケートブーツを着用できるようにすべきです。もっとカラフルに、自由なデザインにできたら最高だと思いませんか?試合がもっと華やかになって、見ているだけでワクワクしちゃいそうです!🤩
延長戦を延長し、シュートアウトを減らそう!⏱️
ピック2.2.ショーンの意見:延長戦を伸ばしてシュートアウトを減らす
続いての提案は、ショーンの「延長戦の時間を伸ばしてシュートアウト(PK戦)を減らす」というアイデアです。ホッケーファンなら誰もが知っているように、3対3の延長戦はめちゃくちゃ面白いですよね!私たちは皆、この延長戦が大好きです。
でも、シュートアウトは…正直、あまり好きじゃないという人3も、逆に多いのではないでしょうか?
「なぜNHLはこんな単純な問題を解決できないんだ?」って、みんな不思議に思っています。リーグが直面しているほとんどの問題とは異なり、この件については(リーグ・コミッショナーの)ベットマンや(各チームの)GMを責めることはできません。
どうやらこれは選手側の問題で、特にスター選手たちは、延長戦で疲れ果ててしまうのではないかと心配されているんですね。
でも、ショーンは「チームには6人以上の選手がいるんだから、スター選手の疲労をそれほど心配するなら、延長戦で他の選手を起用すればいいじゃないか」と突拍子もない提案しています。たしかに!普段あまり活躍の場がない第3ラインの選手たちが、広い氷の上で輝く姿を見るのも面白そうですよね。
ショーンの提案には「延長戦を10分にする」というものもあります。これならほとんどの試合が、ちゃんとホッケーのプレーで決着がつくはず。そうすれば、ほとんどの延長戦は、(ほとんど)本物のホッケーのプレーで決着がつきます。
シュートアウトまでもつれる試合が少なくなれば、たまにシュートアウトになっても、みんながチャンネルを変える原因になるのではなく、「おお、めずらしい!」って新鮮な気持ちで楽しめそうです。

Jリーグを見てきた影響なのか、シュートアウト=PK戦(のような感じのもの)は結構楽しめるんだがにゃ。逆に延長戦が長いと「たりぃなぁ」みたいな時もある。NHLの場合、延長戦やシュートアウトまでもつれ込んだ時、両チームへの勝ち点制度と抱き合わせで改革していかないといけないので、ちょっとややこしいかもしれない。
試合数を減らして、プレーイン・トーナメントを導入しよう!🏆
ピック2.3.シェイナの意見:シーズンを短縮し、プレーインワイルドカードを追加する!
次は、シェイナの「レギュラーシーズンの試合数を減らし、プレーイン・ワイルドカードを追加する」という提案です。
(正当な理由で)延長戦が長くなると、選手の負担も増えますよね。選手の余分な消耗を避けるための一つの方法は、レギュラーシーズンの試合数を減らすことです(70試合程度に)。試合数が減った分の収益は、プレーイントーナメント4で補填しようというアイデアなんです。
シェイナはプレーオフの出場枠は16チームにすべきだという意見ですが、どの16チームが出場するかを決定するために、わずかに拡大することは可能です。
レギュラーシーズンの成績で、シード1位から6位までは確定すべきです。そして、ワイルドカードの出場権をかけて、7位対10位、8位対9位の3試合のプレーインを行うんです。これでスケジュールに12試合追加されることになります。
これはレギュラーシーズンよりもチケット代が高くなる5から、収益もバッチリですね。
新しい8位シードはカンファレンスリーダーと対戦し、7位は2位(もう一方のディビジョン優勝者)、3位対4位、5位対6位となります。
世界のチームが対戦するグローバルな大会が見たい!🌍
ピック2.4.マークの意見:チャンピオンズリーグ形式のグローバルトーナメントを開催する!🌍
彼は、UEFAチャンピオンズリーグやクラブワールドカップのような、世界中のチームが対戦するトーナメントをやりたいと考えています。マークは、子供の頃、オリンピックでチームUSAを応援することはなく、私はジギー・パルフィー6というお気に入りのアイランダーズの選手を応援していたので、スロバキアを応援していたそうです。
だから、「愛国心も楽しいですが、ファンの真の忠誠心は、自国の代表チームではなくて、自分のNHLチームだ!」という考えなんです。
そこで、シェイナの賢明な選択であるスケジュールの短縮に乗っかりますが、プレーイントーナメントの代わりに、UEFAチャンピオンズリーグやクラブワールドカップのような、国ではなくチーム同士で行う世界的なシーズン半ばのトーナメントを開催しよう、というわけです。
フロリダ・パンサーズがフレルンダ7と、エドモントン・オイラーズがSKAサンクトペテルブルク8と、ダラス・スターズがカルパ9と対戦するのを見たいです。
そんな夢のような試合が見られるなんて、想像しただけで鳥肌が立ちますよね!🤩そして、それが意味のあるものであることを望みます。4カ国対抗戦が私たちに何かを示したとすれば、マークさんいわく、世界には高品質な国際ホッケーを求めている人がたくさんいるそうです。
ヨーロッパのサッカー大会であるチャンピオンズリーグの決勝は、毎年1億人以上が観ているんです。ホッケーがそこまでの数字を出すのは難しいかもしれませんが、シーズンの閑散期にケーブルテレビでレギュラーシーズンの試合を観る60万人よりは、確実に多くの人が観てくれるはず。
この大会をオリンピックの間の2月ごとに開催すれば、NHLチームは自国の、そして国際的な知名度を、そして収益を急上昇させるでしょう。
何よりも、めちゃくちゃ楽しいですよね!
降格制度で「タンキング」をなくそう!🙅♀️
第3ラウンド
ピック3.1.マークの意見:NHLとAHLの間に降格制度を設置
マークが提案するのは、「降格制度10」です。そう、サッカー⚽️の世界ではおなじみのシステムですね!
彼は「タンキング」が大嫌いなんだそうです😡。タンキングとは、わざと負けてドラフトで良い選手を指名しようとすること。
これは北米のスポーツ、特にNHLのようなハードキャップ制のリーグでは「必要な悪」とまで言われているそうですが、マークにとっては「気持ち悪くて、冷笑的で、何よりファンを侮辱するもの」なんだとか。
だって、勝つ気もないフランチャイズチームを見るために、4人家族で1,000ドル近くも払うことを要求されるなんて、ファンにとっては本当に辛いですよね…😭。
そして、タンキングをゲームから排除する唯一の方法は、世代を代表するドラフト指名で報いるのではなく、降格という罰を与えることです。もしあなたが所有または経営するチームが、リーグで32位または31位を2年、3年、4年連続で終えるなら、あなたが所有または経営するチームはNHLにいるに値しません。それでおしまいです。
代わりに下部リーグ(AHL)のチームをNHLに昇格させる。たとえば、ハーシー・ベアーズというチームが1年か2年昇格してくる…なんてことがあり得るわけです。
これは実現可能でしょうか?もちろん、これはロジスティクスの観点から、本当に手間がかかるでしょう。NHLとAHLの現在の提携協定11では無理ですし、おそらく多くのAHLのアリーナがマレット・アリーナ12と同じくらいのファンしか収容できないため、無理でしょう。
でも、もし「3年か4年連続して最下位に近い成績だと降格させられる」というルールができたら、チームは必死に勝とうとするはず。そうすれば、タンキングは二度と起こらなくなる、とマークは信じているんです。
まとめ
いかがでしたか?どのアイデアもアイスホッケーを愛する気持ちから生まれた、素晴らしいものばかりでしたね!ユニフォームの自由化から、試合形式の変更、さらにはリーグ全体のシステム改革まで…。
どれもすぐに実現するのは難しいかもしれませんが、いつかこんな風にホッケーがもっと楽しく、面白くなる日が来たら、ファンとしては最高に嬉しいですよね!💖
皆さんは、この中のどのアイデアが一番魅力的だと思いましたか?

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- 毎年3月17日(セントパトリックデー)の前後に、選手たちがウォームアップで着用する「緑色の特別ジャージ」が有名。これはアイリッシュ文化を祝うためにデザインされたもので、通常のチームカラー(黒・金・白)とは異なる鮮やかなケリーグリーンを基調としている。
このジャージはファンにとって非常に人気が高く、毎年チャリティーオークションにかけられ、多くの寄付金を生み出してきた。たとえば2019年には、試合前に着用されたジャージが2回に分けてオークションに出品され、合計で5万ドル以上の寄付金がペンギンズ財団に贈られている。
さらに、2015年にはアイルランド語(ゲール語)で選手名を表記した特別仕様のジャージも登場し、文化的な演出としても話題を呼んだ。
このような特別ジャージの存在は、単なるファッションや試合用ユニフォームの枠を超えて、チームと地元の祝祭文化との結びつきを象徴するものとなっている。ピッツバーグ市自体がセントパトリックデーの祝いに力を入れており、全米でも有数の規模を誇るパレードを開催していることからも、その背景がうかがえる。
街全体が緑に染まり、数十万人の観衆が集まるこのパレードは、ペンギンズの試合とも時期的に重なることが多く、イベント全体が一体感をもって盛り上がる。
ただし、ウォームアップ用の本格ジャージは限定生産で、一般販売はされないことが多いため、ファンの間では「ぜひ市販してほしい」といった声も多く聞かれる。コレクターズアイテムとしても価値が高く、Sidney CrosbyやEvgeni Malkinなど人気選手の着用モデルは、後に高額で取引される例もある。
↩︎ - 1886年の農業展示を起源とし、1912年に始まったロデオ・フェスティバルが母体となって確立された、世界有数のアウトドアフェスティバル。ロデオとチャックワゴンレース、華やかなパレード、インディジナス文化、美味しい屋台、地元住民との交流が融合し、毎年100万人以上を魅了している。
地域経済や社会にも深く根差したイベントとして、カルガリー市民の誇りの象徴ともいえる存在。
↩︎ - シュートアウトを好む人たちは、そのエンターテインメント性を評価している。試合の最後にスリリングな一対一の対決が展開されることで、観客の興奮は最高潮に達し、まるで映画のクライマックスのような瞬間が生まれる。
また、テレビ放送の時間管理もしやすく、演出としても優れていることから、リーグ側にとってもメリットが大きいと言えるだろう。選手にとっても、自分のスキルを際立たせる場として特別な意味があり、観客は普段あまり目立たない選手の意外な才能を見られる楽しさもある。
しかし一方で、シュートアウトを嫌う人たちは、これを「本来のホッケーとはかけ離れた決着方法」として捉えている。約60分間にわたるチーム全体の戦いの末に、最後の勝敗がたった数人の個人プレーによって左右されることに違和感を覚えるという意見は根強い。
中には、「野球でホームラン競争をして勝敗を決めるようなものだ」といった辛辣な比喩も。また、シュートアウトは運や偶然に左右されやすいため、真の実力を反映した結果にならないという批判もある。
このような批判を受けて、一部のファンや選手の間では「3対3のオーバータイムを延長して、より自然な形で決着をつけるべきだ」という意見も広まっている。実際、多くのスター選手たちがシュートアウトに否定的な意見を公にしており、リーグ側に対してルール改正を求める声も上がっている。
ファンの間でも、シュートアウトの廃止を望む人は少なくなく、過去のアンケートでは8割以上が「延長戦の延長」を支持したという結果も報じられている。
↩︎ - 現在、NHLがプレーイン・トーナメントの導入を真剣に検討しているという事実は、公式には存在していない。コミッショナーのゲーリー・ベットマンは、レギュラーシーズンの意義を守る観点から、プレーインやプレーオフ拡張には「全く関心がない」と明言している。
一方でファンや一部のアナリストからは、試合の興奮や収益拡大効果を期待して、NBA型のプレーイン大会を推す声もあるものの、公式見解としては導入には否定的な状況が続いている。
↩︎ - レギュラーシーズン平均:70~170ドル前後(座席やチームにより幅広い)
プレーオフ平均:250ドル前後(全体平均)、しかし人気チームでは400ドル以上、さらには数千ドルに達するケースも
価格上昇率:一般的に100%前後のプラス、強豪チームでは150%超にも
実際の購入例:ラウンドごとに段階的な値上げ。Finalsでは倍以上に
↩︎ - ジグムンド・「ジギー」・パルフィ、1972年5月5日、スロバキア・スカリツァ出身。右ウイングとして類稀なる得点能力を誇り、1990年から2013年まで活躍。
1991年のNHLドラフトでニューヨーク・アイランダースから2巡目(全体26位)で指名された後、1993‑94シーズンに北米へ渡り、主にアイランダースでキャリアをスタート。1995‑96シーズンには81試合87ポイント(ゴール+アシスト)を記録し、その後も90ポイント前後を安定して残すなど、スコアラーとしての地位を確立した。
その後ロサンゼルス・キングスに移籍し、2000‑01シーズンには38ゴール・51アシストの89ポイントでチームを牽引。2005‑06シーズンにはピッツバーグ・ペンギンズでプレーしたが、肩の故障を理由に2006年1月に一度引退を表明している。
しかし、彼のホッケーへの情熱は終わらず、2007‑08シーズンには自らの地元クラブHK36Skalicaへ現役復帰。以後、スロバキア・エクストラリーガで最も得点力のある選手として4シーズンにわたり活躍し、最終的に2013年7月に完全なる引退を発表。
国際舞台でも輝きを放ち、1994年リレハンメル冬季五輪ではトーナメントの最優秀ポイント記録を樹立。2002年世界選手権ではスロバキアに金メダルをもたらした決勝ゴールに関与し、2003年大会でも最優秀ポイント選手に。
また、2010年バンクーバー五輪ではスロバキア代表として出場し、開会式では国旗を掲げ入場する旗手も務めている。こうした功績が称えられ、2019年には国際アイスホッケー連盟(IIHF)の殿堂入りを果たした。
↩︎ - Frölunda HC(スウェーデン)
本拠地:イェーテボリ(Gothenburg)、スウェーデン
リーグ:スウェーデン最高峰のSHL(Swedish Hockey League)所属
創設:1938年にVästra Frölunda IFから独立して創設され、1984年に名称変更、その後2004年に現在のFrölunda HCに改名
戦績:スウェーデン王者としてリーグ優勝5回(1965、2003、2005、2016、2019)。CHL(チャンピオンズホッケーリーグ)優勝も4回(2016、2017、2019、2020)
観客動員:リーグ内で平均観客数が最も多く、堅実なファン基盤を誇る。
↩︎ - SKA Saint Petersburg(ロシア)
本拠地:サンクトペテルブルク、ロシア
リーグ:KHL(Kontinental Hockey League)所属
沿革:1946年創立以来、名前は時代とともに変遷。現在の名称は1991年から使用
栄誉:Gagarin Cup(KHLチャンピオン)2回優勝(2014–15、2016–17)。その他にも多数の国内外大会で優勝経験あり
特徴:エネルギー大手ガスプロムがオーナーであり、資金面で非常に潤沢。2018年平昌五輪のロシア代表が金メダルを獲得する一翼を担った選手たちの多くがSKA所属で、チームとしての完成度の高さを象徴。また、観客動員もロシアクラブとして初めて1万人を超える等、人気・実力ともに国内屈指。
↩︎ - KalPa(フィンランド)
本拠地:クオピオ(Kuopio)、フィンランド
リーグ:Liiga(フィンランド最高リーグ)所属
創設:1929年にSortavalan Palloseuraとして設立され、1945年以降クオピオで活動。1950年代にホッケー専門クラブへと進化
戦績:2025年にLiiga初優勝。過去にも銀メダル(1990–91、2016–17)、銅メダル(2008–09)を獲得。2018年にはスパンゲル杯(国際クラブトーナメント)優勝
特徴:元NHL選手、サミ・カパネン、キンモ・ティモネン、スコット・ハートネルらがオーナーや関係者として参画。地域密着で若手育成にも定評があり、欧州でも注目の存在。
↩︎ - 現在の議論の状況(要約)
論点と背景
レギュレーション(降格)制度は、欧州サッカーや一部のホッケーリーグ(例:スウェーデンのSHL)で採用されており、下位チームが降格、上位チームが昇格する形式。これはファンの試合への関心を最後まで高める効果がある。
しかし、北米のプロリーグは「フランチャイズ制」を採用しており、リーグへの参加権は所有権を伴っているため、降格によって収益や地位が著しく揺らぐ構造となっており、制度導入は現実的ではない。
メディア・アナリストの見解
一部メディアでは、拡大した将来のNHLでレギュレーションを導入するアイデアが提案されている(例:40チーム体制を想定)。ただし、現時点では非現実的で、経営面・リーグ運営面からも難しいとの意見が多数。
「The Hockey Writers」などの記事では、支持されていないチームの経営責任を厳しく問える可能性があるとして説得力あるという主張もあるが、導入には大きな課題が伴うとの見方が強い。
ファン・SNSでの声
多くのファンは「興味深いアイデアだが、現実には難しい」と現実を見据えた反応をしている。特に、AHL(下部リーグ)のチームが独立したNHLの一員として昇格する仕組みには実務上の大きな壁があるとの指摘が多く見られる。
ファン投稿の中には「AHLとNHLで昇降格を設ければ、シーズン終盤の無意味試合が減り、競争の質が上がる」といった期待コメントも見られるが、全体として「制度上・経済上の障壁が高い」という認識が共有されている。
↩︎ - NHLとAHLは、公式な下部リーグ・上部リーグという関係にあるわけではないが、NHLチームが若手選手の育成や控え選手の調整の場として、AHLチームと個別に「提携協定(アフィリエーション契約)」を結ぶのが一般的。
この提携には大きく分けて2つの形態がある。1つは、NHLチームとAHLチームが同じ企業やオーナーによって運営されている「単一所有型」。この場合、選手の移動や施設の管理、財務運営などがスムーズに行えるメリットがある。
もう1つは、それぞれが独立したオーナーによって運営されている「別所有型」で、この場合は提携契約に基づいて選手の派遣や指導方針の調整が行われる。
提携契約の内容はチームごとに異なるが、通常は数年間の期間が定められており、選手の移籍、コーチングスタッフの配置、費用負担の取り決めなどが盛り込まれている。たとえば、2024–25年からはカロライナ・ハリケーンズがAHLのシカゴ・ウルブスと3年契約を結び、またワシントン・キャピタルズはハーシー・ベアーズとの提携を2029–30年まで延長した。
このような協定により、NHL契約を持つ選手はAHLでのプレーを通じて実戦経験を積むことが可能になる。一方で、AHL独自契約の選手がNHLでプレーするには、新たにNHLとの契約を結ぶ必要がある。
ただし、この提携制度はNHLとAHLがあくまで独立したリーグであることを前提としているため、ヨーロッパのような「昇降格制度(レギュレーション)」とは制度的に両立しにくく、将来的な改革には大きなハードルがあるとされている
。 ↩︎ - アメリカ・アリゾナ州テンピにあるアリゾナ州立大学の屋内アリーナで、2022年に開業。収容人数は約5,000人と小規模ながら、大学スポーツやコンサートなど多目的に使われている。
2022~2024年には、NHLチームのアリゾナ・コヨーテズが仮の本拠地として使用したことでも注目を集めた。施設名は、寄付者であるマレット夫妻にちなんで名付けられている。 ↩︎