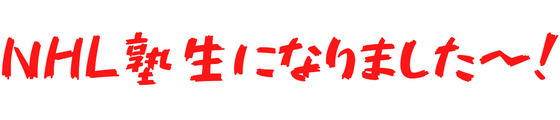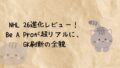はじめに
オタワ・セネターズのゴールテンダー、ウルマークが語った「ゴールテンダーへの妨害」や「シュートアウト」に対する独自の考え方に注目が集まる中、チームメイトとの絆や、精神的なサポートの重要性についても触れています。
さらに、アレックス・フォーメントンがスイスへ移籍した背景にも迫り、その未来にどんな影響があるのかを探ります。オタワ・セネターズの今後と、選手たちの成長を見守るポイントを紹介します。
参照記事:The Hockey News「Senators’ Linus Ullmark Calls For Longer OT And A New Way To Review Goalie Interference In The NHL」
NHLTradeRumor.com1「ALEX FORMENTON’S SWISS DETOUR: A STEPPING STONE OR A PERMANENT EXILE FROM THE OTTAWA SENATORS?」
NHLプレイヤーズ・ツアーで注目を浴びたウルマークの発言⚡
現在、ラスベガスで開催されているNHL年次「プレイヤーズ・ツアー」2では、リーグのスター選手たちがメディアに対応しながら、来シーズンに向けた準備をしています。その中でも、オタワ・セネターズのゴールテンダー、ライナス・ウルマークの発言が注目を集めました🎤。
ツアー初日を終えたばかりのウルマークは、ユニークな視点で多くの記者たちの注目を浴び、最優秀発言者(MVP候補)として名乗りを上げました。その中でも「オーバータイムの延長」と、それに伴うシュートアウトの減少という問題について、非常に興味深い考えを示しました。
オーバータイム延長の提案⏳
ウルマークは、NHLの試合で「オーバータイムをもっと延長するよう、変えるべきだと思う」と提案しています。現在の3対3の延長戦3は攻撃的なゲームを生み出していますが、ウルマークは「僕の考えとしては、4カ国対抗戦のように、オーバータイムをさらに5分延長すべきだ」と語っています。
理由としては、試合中、もっとプレーに集中できるようになり、シュートアウトに頼る必要がなくなるからだとしています。
「ゴールテンダーの視点から言うと、自分が人生で最も良いプレーをして無失点で抑えても、相手ゴーリーも素晴らしいプレーをしている中、シュートアウトで3点を取られると、自分が一番ダメなゴールキーパーだと感じてしまう。正直それが現実だよ、簡単に言うとね。そして、ほかのゴーリーも同じように感じていると思う」とウルマークはコメントしています。
その一方で、シュートアウトには「楽しんでいる部分もある。良くも悪くもね。もし全てのシュートを止めて勝つと、すごく興奮して、ライン上で自分とシュートする相手との戦いだから、とても嬉しい。でも、自分が原因で負けると、それは最悪だ」とも述べていて、やはり勝敗がシュートアウトにかかることには心理的なプレッシャーを感じるようです。
ウルマークのこの提案は、試合の進行にもっと余裕を持たせ、プレーそのものを重視する方向に向かう可能性があり、賛否を呼びそうですね👀。
ゴールテンダーへの妨害の問題を解決したいウルマーク🏒
彼はNHLの「War Room」4に対しても興味深い提案をしました。
ウルマークは、シュートアウトの問題だけでなく、ゴールテンダーへの妨害についても自らの考えを語りました。彼は「ゴールテンダーの視点を理解できるレフェリーを設け、ゴールテンダーインターフェアランス5(ゴールキーパーへの妨害)とそうでないものを、きちんと白黒つけられるようにするべきだ」と提案しています。
ゴールテンダーへの妨害の明確化🧐
ウルマークは「トロントに特定のゴールウォッチャー(審判)を設けて、ゴールテンダーの観点から妨害かどうかを判定できるようにするべきだと思います」と述べました。実際、ゴールテンダーとしてプレーしていると、しばしば「あれはゴールじゃないはずだ」と感じるシーンがあり、反対に、他のプレイヤー側から見ると「ゴールだ」と認識されることが多いのです。
「いろいろな意見や理由が行き交うんだ。それが問題で、どのタイミングでビデオチャレンジをするかが分からない。まるでギャンブルみたいなものだよ。できればオフサイドのように、はっきりと明確な基準を設けてほしい」。
「時には、それがほんの数インチの違い、そして視点の違いに帰着することがある」とウルマークは言いました。
「ゴーリーがクリースの外6に出て戻ろうとしているとき、相手選手とぶつかってしまうことがある。ルールブックには、クリースの外にいる場合は、技術的にはインターフェアレンスではないと書かれている。でも、実際には試合の流れで判断が難しい。
彼は戻ろうとしているけれど、間に合わないんだ。そうしたグレーゾーンをなくしたいと思っている」。ゴールテンダーとしては、常に最善を尽くしてプレーしているつもりでも、ルールが曖昧だとどうしても不公平に感じてしまうようです。
ゴールテンダーの役割における微妙な判断が試合結果に影響を与えることを、ウルマークは心配しており、その改善策を提案しているのです⚖️。
チームメイトを支えるウルマーク選手の人柄🤝
ウルマークはプレイヤーズ・ツアーで非常におしゃべりで、NHLメディア界では素晴らしいトークをする選手としての評判を得ています。彼はゴールテンダーとしてのパフォーマンスに関する意見だけでなく、自身のチームメイトや周囲の人々との関わり方、時にはそれが自分自身を助けてくれることにも触れました。
彼は自分自身について「非常におしゃべりでオープンなタイプ」だと語り、これが彼の精神的な安定に繋がっていると述べています。
チームメイトとの信頼関係💬
ウルマークは、長いシーズンを戦う中で、仲間たちとコミュニケーションを取ることの重要性を強調しました。「もし自分の感情を内にこもらせてしまったら、精神的に厳しくなってしまう」と語り、常にオープンでいることが自分のメンタルヘルスを保つ方法だと認識しています。
「82試合以上のシーズンに加えてプレーオフもある中で、周りの人々と話すことが楽しみなんだ。そうすることで、自分自身を保つことができるし、チームの一員としてもっと成長できる」とウルマークは言います。彼はチームメイトと良い関係を築くことが、最終的にチーム全体のパフォーマンスにも良い影響を与えると考えているようです。
ウルマークのオープンな性格は、チーム内での信頼関係を深め、他の選手たちにとっても心強い存在となっているのでしょう。
良い時も悪い時も、感情を共有することの大切さ💪
また、ウルマークは、「ポジティブなことだけでなく、ネガティブなことも話すことが大事だ」と強調しました。
「僕らは全員が人間で、時にはイライラしたり、悲しい気持ちになる日もある。でも、どんな時でも自分を表現することが大事だと思っています。感情を共有することが重要ってことさ。そうすることで、みんなが安心して自分の気持ちを話せるようになり、チーム全体の絆が深まるんじゃないかな。これは妻とも一緒に取り組んでいることでもある」と話しています。
ウルマークはセネターズでの初シーズン(2024-25)、オタワのプレーオフ進出の手助けをしました。2年目のシーズンでは、再びそれを成し遂げられるという自信を持って戦いに挑む一方で、プレーオフ進出がいかに難しいことかを理解した謙虚さも大切にしたいと考えています。
少なくとも、ウルマークがその卓越したスキルと素晴らしいロッカールームでの態度を、毎試合戦いに持ち込むこんでくれることで、オタワのファンは安心できるでしょう。
ボストンではスウェイマンの陰に隠れていたけど、実力は負けていなかったウルマーク。オタワでいよいよ本領発揮だ!
アレックス・フォーメントンのスイス移籍:再出発か、それとも永遠の追放か?🇨🇭
アレックス・フォーメントン7がスイスのアンブリ・ピオッタ8にサインしたというニュースは、ホッケー界に大きな波紋を広げました。表面的には、自己の都合でゲームから離れていた選手の復帰とも見えますが、その背景には複雑で高リスクな決断が隠されています。
復帰を試みる選手としての決断🤔
フォーメントンがプロホッケーの舞台に復帰することは一見驚くべきことかもしれません。数ヶ月前、彼は建設業に従事していたため、ホッケーから離れた後、フォーメントンのプロホッケーへの復帰は、少なくとも近い将来は考えにくいものに思えました。
しかし、スイスのアンブリ・ピオッタとの契約は、ホッケーの世界に再び戻るための試金石であり、彼自身の能力がまだ通用するかどうかを試す場とも言えます。
この選択は、単なる復帰を意味するだけではありません。それは一種の戦略的な賭けでもあります。
フォーメントンは、北米メディアからの厳しい注目を避けながら、自己のプレーがまだ通用するかどうかを試すことで、ひょっとしたらNHLのゼネラルマネージャーたちに「まだ十分にオプションとして利用可能な選手だ」とメッセージを送ることを目的としているのです。
しかし、誤解しないでください。これはただの選手が氷上に戻りたいというだけの話ではありません。贖罪、世間の目、そしてプロホッケーという常に動き続けるビジネスに関わることなのです。
オタワ・セネターズのファンにとって、最も気になるのは、フォーメントンがまだプレーできるかどうかだけではなく、リーグやファンが彼を迎え入れる準備ができているのか、という点です。
オタワ・セネターズにとっての問題点⚠️
オタワ・セネターズにとって、フォーメントンの復帰は簡単な問題ではありません。チームはまだ彼の権利を保持しており、前シーズン(2021-22)のパフォーマンス、特に18ゴール(NHL79試合出場、18ゴール・14アシスト)を挙げたことを考えると、無視できない存在です。
AHLでも名うてのスピードスターだったフォーメントン。これはオールスターでの映像。彼の前途に何が待ち受けるのだろうか…。
しかし、現在フォーメントンとともに付いてくる荷物は非常に重く、チームは彼のアイス上での可能性と、パブリックリレーションズの危機のリスクを天秤にかけなければなりません。これはただの選手一人の問題ではありません。
「ホッケー・カナダ・ファイブ」事件9はスポーツ全体に長い影を落とし、フォーメントンの復帰はその余波にホッケー界がどう対処するかを試す最初のケースとなります。この事件は、フォーメントンが関与していたもので、裁判では無罪となりましたが、公の意見はまったく異なるものです。

「人格者」ウルマークの後に、この事件を取り扱うのは気が引けるが、セネターズを含むNHLとしては、向き合っていくべき問題だと思う。カナダのホッケー協会が「口止め料」を支払っていたのでは?の疑念もあるし、被害者への不当な圧力も噂されている。これが真実なら、言語道断だ。今後のホッケーの隆盛を考えるなら、しっかりと膿を出してもらいたい。
フォーメントンのスイスでのパフォーマンスと未来🔮
スイスでの彼のパフォーマンスは、彼の成績だけでなく、後悔や成長の兆しも含めて注視されることになるでしょう。すべてのゴール、すべてのインタビューが分析され、分解されます。
これは、過去から学び、第二のチャンスを求めている若者の話なのでしょうか?それとも、ただ嵐が過ぎ去るのを待っている才能あるアスリートのケースなのでしょうか?その答えは、おそらくその中間にあると思われます。
彼のプレーが目立ち、成長を感じさせるものであれば、再びNHLの舞台に戻るチャンスが広がるかもしれません。しかし、逆に成績が振るわなければ、彼のキャリアは大きな岐路に立たされることになります。
このように、フォーメントンのスイス移籍は単なる復帰戦ではなく、未来に向けた大きな決断です。ホッケー界の人々、特にオタワ・セネターズのファンは、彼がどんなプレーを見せるのかを注視しています。
まとめ
ウルマークの提案するゴールテンダー妨害の明確化や、チームメイトとの積極的なコミュニケーションが、セネターズの成長にどう寄与するかが重要なポイントです。
一方で、フォーメントンのスイス移籍は、彼の未来に対する試金石となるでしょう。今後、オタワ・セネターズがどのように進化し、これらの選手たちがチームにどんな影響を与えるかが注目されます。

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- NHLのトレード噂、フリーエージェンシー、ドラフト、ファンタジーホッケーに関する最新情報を提供する専門的なウェブサイトである。サイトは、各チームの動向やリーグ全体の動きに関する詳細な分析を掲載し、ファンやアナリストにとって貴重な情報源となっている。
↩︎ -
「NHLのPlayers’ Tour」と呼ばれるイベントは、単一の公式行事ではなく、いくつかの形態が存在する。もっとも一般的なのはシーズン前にNHLと選手会が主催する「Player Media Tour」で、スター選手が集まってメディア対応やスポンサー活動を行い、開幕前の広報イベントとして定着している。
また、過去にはロックアウト時やオフシーズンに選手が地方を巡って試合やチャリティ活動を行うツアーもあり、ファンや地域社会との交流を目的として開催された。さらに、夏のチャリティゴルフ大会なども同様に「Players’ Tour」の一形態として扱われることがある。
いずれも共通するのは、選手がファンやメディア、地域とつながりを持ち、広報や社会貢献の場として機能している点である。
↩︎ - NHLにおける現行の3対3による5分間の延長戦は、2015-16シーズンから導入され、シュートアウト(シューアウトとも)による試合決着を減らすことを目的としており、試合の緊張感とスピード感を高める効果が確認されている(この方式はGM会議でも「うまく機能している」と評価されている)。
この延長戦に対しては、延長時間を10分に延ばす提案もあるが、選手の疲労や氷上のコンディションへの影響を懸念する意見も少なくない。
選手の間では意見が分かれている。例えば元サンノゼ・シャークスのパトリック・マルーは「延長は良いと思う。5分の後でも決着がつくだろう」と肯定的であるのに対し、カルガリーのナゼム・カドリは「シーズン82試合を通して延長をやるのは疲れる」と懸念を示している。
また、コナー・マクデイビィッドは「シューアウトは試合の終わり方としてイマイチ」としつつも、選手の健康への配慮が必要だと述べており、シドニー・クロスビーは「10分の3対3なら決着がつくかもしれない」とプレーでの決着を期待している。
GMの意見でも、興味深い視点が見られる。多くのGMは現行制度に大きな不満はなく、特に「ポゼッション重視の試合展開が減り、再び試合がシューアウトに行きそうになったら見直せばよい」といった慎重論が目立つである。
一部のGMが提案したように、オーバータイム中に自陣へ戻ることを制限したり(いわゆる「ハーフコート」ルール)、ショットクロックを導入したりするなど、工夫によって攻守の流れを早めようという議論もあるが、これも「意図せぬ結果を生む可能性がある」として慎重に検討されている。
選手側からも4カ国対抗戦(4 Nations)形式のように10分延長を望む声がある一方で、長すぎる延長は疲労蓄積の懸念につながるという声も根強い。さらに、延長戦を「もっと延ばす」ではなく、突然延長終了よりも再び3対3の延長を繰り返すことで試合を決めるという案を支持するメディアやファンもある。
↩︎ - 公式にはSituation Room。トロントに置かれたリーグの集中レビューセンターであり、複数会場で同時進行する試合の映像を一括して監視し、ゴール判定、オフサイド、ゴーリー干渉などのビデオレビューやコーチのチャレンジの最終判断を下す役割を担っている。
この集中審査体制は、過去のプレーオフでの物議を醸した判定を受けて機能拡大が行われ、より多くの種類のレビューを扱うようになった経緯があり、その結果として試合の一貫性を高める一方で、現場審判の裁量を後から覆すことやレビューによる試合中断の長さをめぐる批判も生じている。
運用面では、一夜に複数試合を監視するため専門の審査スタッフが配置され、オンアイスの審判と映像を突き合わせつつ最終結論を出す仕組みが定着しているが、近年はプレーオフ時に「内部からの舞台裏映像」が公開されるなど透明性の向上を図る動きも見られる。
なお「War Room」の呼称はチーム側がドラフト戦略を練る内部の“ドラフト・ウォールーム”(各球団のドラフト指令室)にも使われるため文脈に注意が必要であり、リーグのSituation Roomと球団のドラフトルームは目的と運用が異なる別物である。
↩︎ - Goaltender Interferenceはルール69で定められており、攻撃側の選手が体やスティックを使ってゴールテンダーの動きを妨害する行為を指すものである。特にゴールクリーズ内での接触によって得点が生じた場合は、そのゴールが取り消されることが明文化されている。
この反則は状況によって解釈の幅が大きく、判定が主観に左右されやすいため、リーグはコーチチャレンジやトロントのSituation Roomによるビデオレビュー制度を導入し、最終判断を統一的に扱う体制を整えてきた。
だが判定の一貫性をめぐる不満は依然として根強く、偶発的接触か意図的妨害か、あるいはセーブ機会が実際に奪われたのかといった点で物議を醸すことが少なくない。
プレーオフでも論争が繰り返されてきたことから、ルールの解釈や運用は徐々に明確化され、レビュー制度も拡充されてきた経緯がある。近年ではゼネラルマネジャー会議で改善が議題となり、リーグはビデオルールブックの公開や判定理由の説明を行うなど、透明性の向上に取り組んでいる。
↩︎ - インターフェアランスは、ゴールテンダーの移動やセーブ機会を妨げる行為を禁止するルールであり、主にルール69.1に基づいて適用される。このルールでは、攻撃側選手がゴーリーの動きを妨げるような接触を行った場合、得点が無効とされる。
特に、ゴーリーがクリース内で自由に動けることが求められ、その妨害があった場合にはゴールが取り消される。
しかし、ゴーリーがクリース外に出ている場合、ルールの適用が複雑になる。ゴーリーがクリース外にいる際の接触については、状況に応じて判断される。例えば、ゴーリーがクリース外でプレーしている際に、攻撃側選手がその動きを妨げるような行為を行った場合でも、得点が無効とされることがある。
一方で、ゴーリーがクリース外にいる際の接触が偶発的であり、ゴーリーのセーブ機会に実質的な影響を与えないと判断される場合、得点が有効とされることもある。
このように、インターフェアランスの判定は、ゴーリーの位置や接触の状況に応じて柔軟に適用される。そのため、試合中の判定は審判の判断に委ねられ、ビデオレビューなどで再確認されることが多い。このルールの適用に関しては、過去に物議を醸す場面もあり、今後の議論や改定が注目される。
↩︎ - 1999年9月13日、カナダ・オンタリオ州バリーで生まれ。左ウィング。2017年のNHLドラフトでオタワ・セネターズから2巡目全体47位で指名され、同年10月7日にNHLデビューを果たした。その後、セネターズでのプレーを経て、2022年にはスイスのHCアンブリ=ピオッタと契約し、スイスリーグで活躍した。
特に2022年のスパングラーカップでは、同チームの優勝に貢献し、注目を集めた。
しかし、2018年のカナダ・ワールドジュニア代表チームのメンバーとして関与したとされる性的暴行事件により、2024年1月にロンドン警察に出頭し、同年2月に性的暴行の容疑で起訴された。その後、2024年8月に無罪判決を受けたが、NHLは内部調査を理由に引き続き出場停止処分を維持している。
フォーメントンは2025年9月にスイスのHCアンブリ=ピオッタと再契約し、プロホッケー選手としてのキャリアを再開した。
フォーメントンは、スピードと攻撃力を兼ね備えたフォワードとして評価されており、特にペナルティキラーとしての役割でも知られている。また、家族の影響で自閉症やダウン症の支援活動にも関心を持ち、社会貢献活動にも積極的に関わっている。
↩︎ - HCアンブリ=ピオッタ(Hockey Club Ambrì-Piotta)は、スイス・ティチーノ州のレヴェンティーナ渓谷に位置する小さな村々、アンブリとピオッタを拠点とするプロアイスホッケークラブである。1937年に創設され、スイス・ナショナルリーグ(NL)に所属しており、愛称は「ビアンコブルー(白と青)」である。
ホームアリーナはゴッタルド・アリーナで、収容人数は6,775人。クラブはこれまでリーグ優勝は果たしていないが、1985年にスイスリーグから昇格して以来、降格することなくナショナルリーグに留まっている。
クラブの歴史には、1959年から自所有のヴァラシア・アリーナを本拠地として使用してきたことがある。また、2013年には財政難を乗り越えるため、ファンからの寄付を含む約500万スイスフランを集め、ナショナルリーグでのプレー継続を確保した。
クラブのファンは非常に熱心で、ヨーロッパ各地に40以上のファンクラブを有し、特にHCルガーノとのダービーマッチでは独自の応援スタイルが見られる。勝利後には「ラ・モンタナラ」という渓谷の賛歌を歌うことが伝統となっている。
クラブの主な国内タイトルには、1998–99シーズンのナショナルリーグ準優勝、1962年のスイスカップ優勝がある。国際大会では、IIHFコンチネンタルカップを1998–99、1999–2000シーズンに連覇し、1999年にはIIHFスーパーカップも制覇した。
↩︎ - 2018年6月19日にカナダ・オンタリオ州ロンドンのホテルで発生したとされる集団性的暴行事件に関連する裁判である。被告は、当時カナダ男子U20代表チームのメンバーであったマイケル・マクラウド、アレックス・フォーメントン、ディロン・デュベ、カーター・ハート、カラン・フートの5名である。
被害者は、同年6月に行われたホッケーカナダのガライベント後、ホテルの部屋で複数の選手に性的暴行を受けたと主張した。
2022年に事件が再捜査され、2024年1月に5名は性的暴行の容疑で起訴された。2025年4月に始まった裁判では、陪審員による審理が2度中止され、最終的に裁判官による単独審理に移行した。
2025年7月24日、オンタリオ州ロンドンの裁判所で、裁判官マリア・カロッチアは、検察側が被告人の有罪を合理的な疑いを超えて証明できなかったとして、5名全員に無罪判決を下した。判決は、被害者の証言が「信頼性も信用性もない」と評価されたことに基づいている。
この事件は、ホッケーカナダが選手登録料を使用して過去の性的暴行事件の和解金を支払っていたことが明らかとなり、2022年に政府からの資金提供が凍結されるなど、カナダ国内で大きな社会的議論を引き起こした。
また、裁判の過程で被害者の証言に対する厳しい審査が行われ、被害者が「試される側であるかのような印象」を与える結果となったことも、ホッケー界における文化的問題への関心を高める要因となった。
5名の選手は、無罪判決を受けた後もホッケーカナダやNHLからの処分を受け、2025年9月、フォーメントンはスイスのHCアンブリ=ピオッタと契約し、プロホッケー選手としてのキャリアを再開した。しかし、NHLからは出場停止処分が継続されており、今後の対応が注目されている。 ↩︎