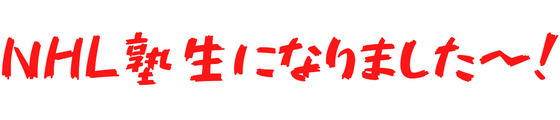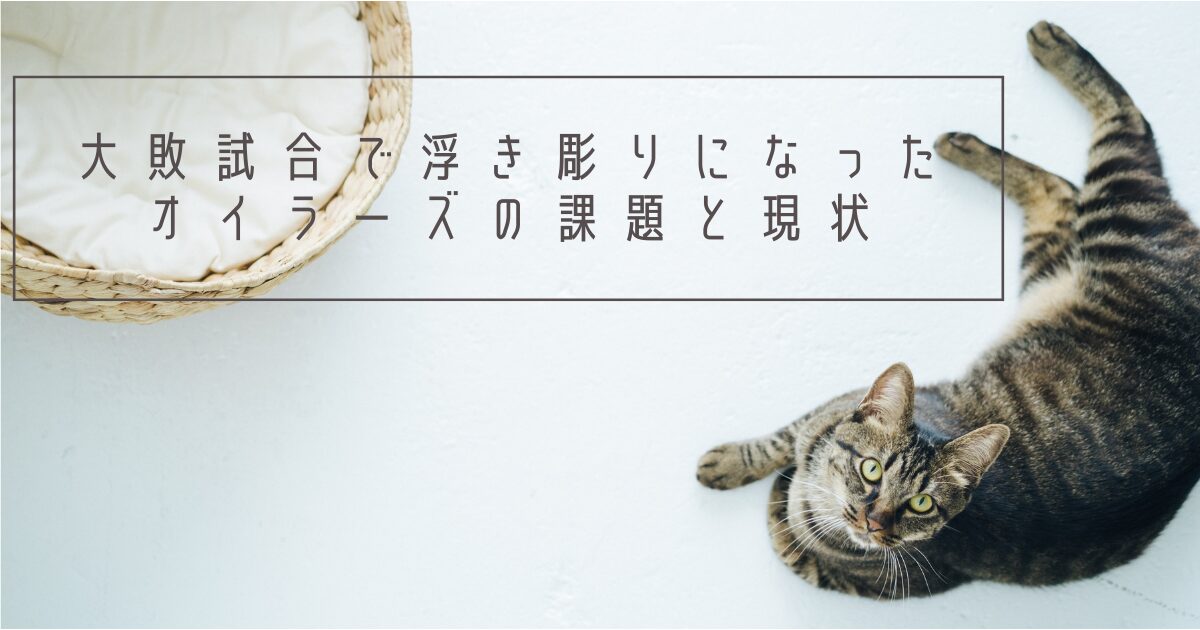はじめに
土曜夜のホームゲームで、エドモントン・オイラーズはコロラド・アバランチに大敗。2点先制された時点でチームの戦意は低下し、ゴーリー・スキナーを中心に全体が崩壊。
マカーの連続ゴール😊に象徴されるように、期待された選手たちも力を発揮できず、チーム全体が迷走する現状が浮き彫りになりました。😔💔
参照記事:Sportsnet1「Slumping Oilers full of excuses after blowout loss to Avalanche」
🏒崩れた夜——オイラーズが見せた“戦う姿勢”の欠如
土曜の夜、エドモントンのホーム「ロジャーズ・プレイス」で行われた試合🏒は、ファンにとってまさに悪夢のような時間2でした。😣そしてロッカールームから聞こえてくるのは、落胆というよりも“あきらめ”に近い空気だったのです。
コロラド・アバランチにホームで8点差をつけられて敗れたオイラーズは、途中からまるで戦意を失ったように見えました。2点を先制された後、ゴーリーがやわらかいシュートを許した瞬間、チーム全体が力を抜いてしまったように感じられたのです。
その後は反撃の気配もなく、アバランチが次々とゴールを重ねても、ラフプレーすらありませんでした。ボールのように丸くなって、アバランチに7点も追加を奪われるのをただ見ているだけ。
そんな中で名前が挙がったのが、トレント・フレデリック。昨季トレード期限で加入した彼は、チームに勢いをもたらす存在として期待されていましたが、今のところその存在感は「顕微鏡でも見えないほど」と言われてしまうほど😬。
「自分のプレーでなんとか流れを変えたい」と語った彼ですが、ロジャーズ・プレイスでアバランチが好き放題に攻めてくる間、彼はまるで“教会のネズミ”のように静かでした。今季ここまでの成績はわずか1ポイントと6分間のペナルティ。上位6人に入るフォワードのような技術も、下位ライン特有の泥臭さも感じられません。
「ケンカなんて相手が応じてくれなきゃできないよ。15試合で1ゴールしかない選手なんて、誰もやりたがらないさ。チームに勢いをつけたいけど、誰もそんな奴とはやりたがらない。俺だってそうさ」と言い訳するフレデリック💬。
“いや、普通ファイターは25点も取らないけどね”と皮肉を言いたくなる場面3でした。
もう一人、名前が挙がったのがアンドリュー・マンジアパーネ。彼のプレースタイルといえば、相手をイラッとさせるような“ヤスリのような荒さ”が持ち味のはず。相手をイライラさせる存在4じゃなかったのか?かつては“やりにくい相手”だったのでは?しかし、今季はそうした面影があまり見られません。
「そうだね、もっと粘り強く、ハードにプレーしないと」と本人も語ります。「もしそういうプレーが出せれば、それでいいんだ」。彼の言葉には、どこか自信のなさと迷いがにじんでいました。
「そういうプレーが出れば、それでいい」。
ファイターは得点できるまで戦わないようです。嫌がらせ役は、空から自分のゲームが降ってくるのをただ待っているのです。
💭チーム全体が迷走中?「これがどん底であってほしい」
「俺たちは“楽に勝てる”とでも思ってるんじゃないか?」——そう語ったのは、ディフェンスのジェイク・ウォールマン。今季は不用意な攻め上がりでピンチを招くことも多い彼ですが、言葉の重みはチームの現状をよく表していました🏒。
「結局のところ、そこから始まるんだよな。全員がチームの方針に従って、それぞれが持つ強度を発揮すること。それが大事なんだ。」プレーヤーごとに違いはあっても、全員が“本気で戦う姿勢”を取り戻さなければならない——そんなメッセージです🔥。
オイラーズはここ2シーズン、スタンレーカップ決勝までたどり着いてきましたが、その道のりはいつも同じパターン。シーズン序盤はスロースタート、やがて調子を崩し、シーズン中盤に“どん底”を迎える。まさに今がそのタイミングに見えます。
クリス・ナブロック監督は言いました。「今回が本当に我々の“どん底”であってほしい。この敗戦が多くの選手を目覚めさせてくれることを願っている。我々はまだ“本当に強いチーム”になるために、やるべきことが山ほどある」。
エドモントン・オイラーズのナブロック監督は、コロラド・アバランチに9対1で大敗した後、メディアの前でシーズン序盤の厳しい現状を語り、立て直しへの課題を説明しました。彼の言葉は、単なる敗戦コメントではありません。チームの中心が“勝ち方を忘れている”ことを示す警鐘5でもあります。😔
この日の試合、ゴーリーのスチュアート・スキナーはセーブ率.889と再び低迷。第1ピリオド13分39秒、コロラドのケール・マカーが放った正確なリストショットを許した瞬間、チームの集中力は一気に切れてしまいました。まるでその1点が、オイラーズ全体の心を折ったように見えたのです。
アバランチvs.オイラーズ戦のダイジェスト映像です。あまりにも無惨な負け方に、言葉なし…。
🥅スキナーへの信頼はもう限界?チーム全体の崩壊
試合開始わずか1分ちょっとの間に、マカーに2本目のゴールを許したスキナー🏒。今回のシュートは妨害もなく、視界も完璧、ブロッカーの下をすり抜けるような決して難しいショットではありませんでした。それでもチームは戦意を失い、まるで試合をあきらめたかのように見えました。😞
チームはスキナーに見切りをつけたのか、自分たちに失望したのか。そのどちらであっても、土曜の試合が示したのは、もはやスキナーを“絶対的な正ゴーリー”とは見ていないという現実です。
ナブロック監督は、選手たちがゴーリーへの信頼を失ったのではないかと尋ねられると、長い沈黙の後に「そうは思わない」と答えました。ですがその後の言葉は、昨季から繰り返されてきたスキナー擁護の弁解6にすぎませんでした。
もちろん、ゴール前でフリーの相手に決められる場面が多すぎることは問題です。しかし、2つのことが同時に真実である場合もあって、スキナーの課題だけではありません。チーム全体の守備や意識の問題も同時に存在しています。
そして、土曜の試合が示したのは——GMのスタン・ボウマンが、ゴーリー補強市場に本気で動くべき時が来たという現実です。チームの誰も、もはや“スキナーが男だ(The Guy)”とは思っていません。
ウォールマンも言います。「俺たちは間違った方向に進んでいる。今夜は完全にやられた。全員が自分の役割を理解して、それを果たす必要がある。誰もがだ」。
ゴーリーはセーブ、ディフェンスは守備、スコアラーは得点、下位ラインのフォワードは外回りばかりせずゴール前へパックを運ぶ。すべてはここから始まります。そしてコーチ陣も……スランプに陥っているようです。
⚡マカーの連続ゴールが象徴するオイラーズの現実
コロラド・アバランチのディフェンスマン、ケール・マカーがわずか1分6秒の間に2本連続でスナップショットを決め、オイラーズを早々に2点差に突き放しました🏒。どちらもオフェンスゾーンのサークル上部から放たれたシュートで、アバランチはこれで早々に2対0のリードを手にし、オイラーズにとっては大きな打撃となりました。🥶
この試合を見て、いつ気づくのでしょうか?
オイラーズが本当に手ごわい相手になるのは、コナー・マクデイビッドとレオン・ドライサイトルがそれぞれのラインでセンターを務めたときです。
それでも、オイラーズの監督はいつも同じ“罠”7にはまります。ベンチには汗もかいていないサポート役ばかり、背番号97と29が24分間氷上に立たされ、ほとんどの問題を彼ら2人だけで解決しようとする——そんなやり方がおかしいことに、いつになったら気づくのでしょう。
さらにペナルティキルまで担当させ、それによって、1試合10分しか出られない“裏方たち”の出番をさらに奪ってしまっている——そんな状況です。
疲れ切っているのか、不甲斐ないチームに嫌気がさしているのか、マクデイビッドがやさぐれています。

このチームにいずれ訪れる崩壊劇が、一気に表に出てしまったような試合だったにゃ。ここ数シーズンの監督は、判で押したように「戦術マクデイビッド&ドライサイトル」でどうにか勝ちを拾って、偶然なのか必然なのか、プレーオフを勝ち進んでいる。でも、そんなラッキーは長続きしない。なぜなら、ゴーリーのスキナーの役まで2人は担えないからだ。
そしていつになったら気づくのだろう。
デイヴィッド・トマセク、マット・サヴォワ、アイク・ハワードという、NHL通算49試合しか出場経験のない3人の技巧派選手を並べた第4ライン8を抱えたまま、どうやって“サイズも荒さも経験もない”チームがスタンレーカップを狙えるのかという現実に。
地元ラジオのアナウンサーがこう言っていました——「今夜のパフォーマンスは、自分たちが“どこにいないか”をはっきり示す試合だった」と。
あるいは、それはそのまま、オイラーズというチーム🇨🇦🏒が今どういう存在になってしまったのかを象徴しているのかもしれません💔。
まとめ
フレデリックやマンジアパーネら期待された選手たちは存在感を発揮できず、チーム全体の連動も欠けていたオイラーズ。ゴーリー・スキナーの守備に頼る構図や、第4ラインの経験不足も課題として浮き彫りに。
今後は各自の役割を理解し、全員で戦う姿勢を取り戻すことが、立て直しの鍵となりそうだ。💪🥅

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- カナダではトップクラスのスポーツメディアブランドで、テレビ・ラジオ・オンライン・モバイルといった複数プラットフォームを通じてスポーツファンとチーム・アスリートをつなぐ役割を担っている。
特に、同社が国内のNHLの全国放送権を保有しており、地域別チャンネルを通じて特定チーム(例えばEdmonton Oilersなど)の試合もカバーしている。また、多様なスポーツリーグ(MLB、NBA、サッカー、カーリングなど)を扱い、ニュース・ハイライト・ライブ配信・深掘り分析コンテンツを提供。
↩︎ - 北米メディアは、今回のEdmonton Oilers 対 Colorado Avalanche戦(9‑1大敗)について、次のように論評している。
まず「フランチャイズ最悪級のホーム敗戦」と指摘されており、両ゴーリーが計34本のシュートで9失点という数字から「守備・反応・メンタルすべてが崩壊した状態」だという評価が出ている。続いて、監督Kris Knoblauchが「“rock bottom(どん底)”だ」と認めた発言に触れて、「この敗戦をきっかけに組織として立て直さなければならない」という論調が強まっている。(参照記事:Athlon Sports「Oilers Coach Assigns Blame After Blowout Loss to Avalanche」)
さらにゴーリー陣への信頼が揺らいでいるとの声もあり、記事では「選手たちがスチュアート・スキナーやカルヴィン・ピカードに対して“彼らがやってくれる”という期待を持ち続けられていない」と分析。
最後に、ファン・ブロガー・SNS上では「チームが早々に崩れ、エネルギーも危機感も足りなかった」「勝てる体制ではない」との厳しい反応が相次ぎ、特に「リーダー層の口数が少ない」「選手が言い訳じみたコメントを出している」という批判が目立つ。
↩︎ - この文章が指摘しているのは、フレデリックの現状とアイスホッケー界で「ファイター(格闘・激しい当たり役)」に期待される役割のズレである。フレデリックは今季わずか1ゴールという成績で、「ファイターとしてチームに火をつける」「敵をけん制し、試合の流れを変える」というタイプには見えないという批判を受けている。
彼自身も「15試合で1ゴールの選手にケンカを仕掛ける人なんていない」という言い訳を口にしているが、文中の“普通ファイターは25点も取らないけどね”という皮肉は、「むしろファイター役の選手は得点も25点ぐらい取ることが多い」という背景的な期待値を示している。
言い換えれば、ホッケーでは「ファイター」役=当たりが強く、守備や体を張れ、またそこそこの得点能力も備えていることが多いという暗黙の常識がある。フレデリックの場合、その得点数も極めて低く、ファイターとしての役割も果たせておらず、そのギャップがこの皮肉表現につながっている。
このように、「ファイターなのに得点も少ない/戦いの姿勢も見えてこない」という現実が、彼への評価をさらに厳しくし、記事では“顕微鏡でも見えないほど”という形容までされているわけである。
↩︎ - アイスホッケーにおいて「相手をイライラさせる存在」を、“ペスト(pest)”と呼ぶことが多い。
ペストとは、単に得点を競う選手ではなく、相手チームのリズムを崩し、心理的に揺さぶることを役割とする選手。例えば、相手選手に「チャープ(trash talk)」で言葉を浴びせたり、見えないタイミングでシュリンクやフックといった境界線上のフィジカルプレーを仕掛けながら、審判の目をかいくぐって相手を苛立たせる。
また、彼らはしばしば「相手をファイトに誘発させてペナルティを取らせる」戦術を用い、自分自身は大きなファイトを仕掛けずに済ませることもある。さらに最近では、得点力とその“荒らし”役が両立したペストが高く評価されており、フィジカル+得点という組み合わせが「真のペスト像」として語られている。
↩︎ - 北米メディアは、Kris Knoblauch監督の発言やチーム状態を痛烈に分析している。例えば、ある報道では、ホームで9-1という大敗を喫したことで、オイラーズが“ただ話すだけ”の段階を終え、「本気で変わらなきゃいけない」というリアリティをついに受け入れた夜だと伝えられている。
また別の記事では、監督がゴーリー陣への信頼を問われた際に見せた長い沈黙が「答え以上のサイン」だと指摘され、示唆的なコメントを出しながらも、明確な肯定には至らなかった点が「組織の内情に『疑念』がある証」と受け取られている。(参照記事:hockeyfeed.com「Kris Knoblauch sounds off on the Oilers goaltending problems」)
さらに、チーム全体に言及した中で「努力しているが競っていない」「いいチームと平均的なチームの違いは、毎試合全力で“競争”できるかどうかだ」とした分析もあり、監督の“どん底”発言は、単なる敗戦ショックではなく、チームの根幹にある姿勢・意識・構造にメスを入れるべき時期が来たという警鐘として捉えられている。
↩︎ - 北米メディアの多くは、Kris Knoblauch監督によるStuart Skinner擁護の弁解に対して批判的な見方をしている。たとえば、「オイラーズのゴーリーに対する長い沈黙が意味していたのは、信頼が揺らいでいる証拠だ」という報道もある。
監督が「そうは思わない」と口にしたものの、その後に続いたのは過去数シーズンと変わらない「保護的な言い回し」であり、現状認識や具体的な変化を示す発言には至っていなかった。これが「言葉だけで終わらせていて、行動に移せていない」という論調を生んでいる。
特に、ファン・評論家の間には「チームがスキナーに“やってくれる”という期待をかけすぎてきた」との批判が根強く、守り切れない試合が続く度に監督とゴーリー双方への信頼が揺らいでいるという指摘がある。(『The Times of India』等、多数)
こうした背景から、今回の監督コメントは「組織全体の責任をゴーリー個人に転嫁してはいけない」という構造的な問題への“警鐘”としても読まれている。言葉を発しただけでは十分ではなく、実際に選手とシステムをどう変えるか、監督自身が行動を示す必要があるというのが、マスコミでの共通認識である。 ↩︎ - 北米メディアでは、Edmonton Oilersが背番号97(Connor McDavid)や29(Leon Draisaitl)らスター選手の出場時間を過度に頼り切り、その一方で“サポート役”の選手層を軽視してしまう指揮の問題点が根強く指摘されている。
例えば、「毎試合24分以上をスター2人に与え、実質10分しか出場しない役割選手が増えている」という指摘があり、この起用バランスの偏りこそ今季の低調スタートを招いていると分析されている。
記事では、オイラーズが連続して好成績を残せない原因として「第一ラインの顔ぶれは頂点級なのに、第三・第四ラインやペナルティキル(PK)要員の重用がなされておらず、相対的に疲弊しやすいトップラインの機能低下が目立つ」と論じられている。
試合後のファン・解説者からの声も、「チームの4ラインを均等に使えず、ベンチが場つなぎ化している」「24分出るスターがひたすら氷上にいて、列を成すサポート選手が機能していない」という批判に集中している。
また、「この起用スタイルこそ、今のホッケー環境では時代遅れだ」とする声もあり、他チームとの比較分析では「最強選手2名だけで突破を図る“ワン・トゥー・パンチ型”では、相手に研究・対応されると一気に歯車が狂う」「トップ2名が疲れた状態で最終盤を迎え、サポート役が疲労困憊で限定出場では勝ち続けるのは難しい」という指摘が出ている。(参照記事:Lowetide.ca「Both Sides Now」)
↩︎ - 北米メディアでは、Edmonton Oilersの第4ラインに若く経験の浅い3選手を起用する状況について、「スタンレーカップを視野に入れたチーム構成としてはリスクが高い」との分析が出ている。
具体的には、「NHL出場数が極めて少ない選手を複数同時に起用しても、試合終盤の物理的負担やプレッシャーに耐えられるとは言い難い」との見解や、「サイズ・荒さ・経験といった“粘り強さを求められる”要素が欠けており、トップラインやディフェンス陣に比べて明確に脆弱だ」とする指摘がある。
記事では「優秀な技巧派三人だが、4ライン目に配置された時点で『場数を踏んできた選手とのアドバンテージ』を失いかねない」とされており、さらに「深みある布陣を構築できないと、プレーオフや厳しい試合展開で“火種”になる可能性がある」と警鐘が鳴らされている。
↩︎