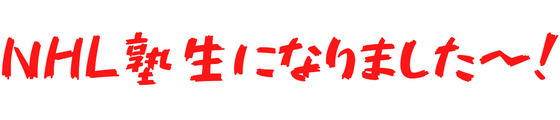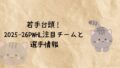はじめに
カリフォルニアの3チームが、今季とんでもないサプライズを起こしています。見限られていたキングスはアウェイで大躍進、ダックスは序盤の勢いから本気でプレーオフを狙える位置に。そして再建中のシャークスまでもが着実に前進。
予想をひっくり返す“西海岸の異変”をわかりやすくまとめました🏒✨
参照記事:The Athletic「What is going on with California’s confusing NHL teams? Let us explain」
🏒NHLナイトまとめ:カラフルユニフォーム対決と予想外の展開
「color‑on‑color jersey1」同士の対決をもう見たくない人以外のみなさん、おはようございます。あのレンジャーズ対レッドウィングスの試合を見てハッピーにならなかった人なんていませんよね?(1-2でレッドウィングスの勝利)まあ、(敗れたレンジャーズのゴーリー)ジョナサン・クイックはちょっとイラッとしていたようですが、それ以外は?
昨夜は「シックスパック2」を楽しみました、NHLの試合の話ですよ。もちろん他の意味でもいいですけど、あなたの人生に口を出すつもりはありません。でもホッケーは楽しかったです。
パンサーズとカナックスは点を取り合い(8-5でパンサーズの勝利)、ブルーインズとハリケーンズは昔ながらの守備戦を展開(3-1でハリケーンズの勝利)。そして、オイラーズ対セイバーズでは“ちょっとした大差”がついたと聞いたので、エドモントンが勝ったと勝手に思っていました。え、何?……はぁ(5-1でセイバーズの勝利)。
ほんと、このリーグは意味がわかりません。
🏒カリフォルニアのNHL事情が大混乱!?〜カリフォルニア・ラブ
ここ最近のNHLを見ると、いちばん“混乱”しているのは実はカリフォルニア州🌉かもしれません。友人のエリック・スティーブンス(The Athletic記者)は、完全に混乱状態にあります。いや、本当にそうなんです。エリックはカリフォルニア担当なのですが、今のホッケー界でここほど“混乱している州”はありません。
ロサンゼルス・キングス、アナハイム・ダックス、そしてサンノゼ・シャークス。この3チームが、シーズン前の予想とはまったく違う動きを見せています。
シーズン前、多くの人がキングスを「厳しい」と判断し、見限っていました。プレーオフで勝ち上がれず、さらにケン・ホーランドを迎えたことで、ディフェンス面が悪化3するんじゃないかと言われていたからです。
ダックスは長い再建中で、何かに本気で挑戦するにはあと数年かかるだろうと予想されていました。そしてサンノゼ・シャークスはおそらく“意図的に”ひどいまま4、また高順位指名を狙うだろうと思われていたのです。
でも、シーズンが始まって6週間。……ええと、はい、どれも起きてません。その予想……全部ひっくり返りました😳混乱しますよね。
そこで私はエリックに状況を説明してもらいました。ありがたいことに、彼は“東海岸メディアの私でもわかるように”丁寧に教えてくれたのです。ここからは、私の質問とエリックの回答です。
🔹キングスの予想外の躍進
Q:シーズン序盤、見限られていたキングスが、4連勝して一時的にパシフィック首位に浮上しました✨ここ数週間で何が変わったのでしょう?
A(エリック):一番クレイジーなのは、昨季とは真逆の現象が起きていることです。その背景には、ホームとアウェイでの極端な二面性があります。昨季のキングスは“ホーム最強・ロード普通”のチームでしたが、今季は“アウェイの巨人・ホームでは壊滅的”です。
最近の9勝3敗2OT負けという好調の中、勝ちのほとんどがアウェイで生まれています。なんと、ホームでは1勝4敗2OT負けなのに、アウェイでは9勝2敗2OT負けと絶好調です🏟️ニューヨーク・レンジャーズほど極端ではありませんが、かなり不思議な二面性現象5ですよね。
チームとしては、いつもの「ポゼッションホッケー」を徹底。堅実な守備に、ダーシー・クンペルの安定したゴーリーング、バックアップのアントン・フォースバーグも良い活躍を見せています。
そして要所で必要な点を取り、L.A.は昔から“チーム全体”の力で勝つチームですが、ブランド・クラークはDF陣で存在感を出し、ケヴィン・フィアラは得点ラッシュ状態、クエンティン・バイフィールドも上向きです。エイドリアン・ケンペも、チーム最高の選手として当然の報酬を受けています💰
8試合も延長戦に持っていき、ポイントを拾っていることも多く、細かい部分で勝利を積み重ねているのも大きな要因です。

まさかキングスが“ホームで苦戦・アウェイで無双”という真逆の姿になるなんて…本当にびっくりだにゃ😳‼️まるで別チームみたいな二面性に、ホッケーファンも思わず「どういうこと!?」と声が出るレベル。しかも、計算高く要所でしっかり勝ち点を積み上げているのがまた不思議で面白い…!昔から「キングス」という名のとおり、豪快に勝ち豪快に負ける印象だったのに意外な展開です。
🔹ダックスの好スタートと初めての逆風
Q:アナハイム・ダックスはシーズン序盤、7連勝を飾りリーグの話題をさらいました⚡しかしそのあと3連敗(すべて60分負け)、そして月曜に延長勝利。アナハイムを過大評価しすぎていたのでしょうか?
A:長年“ひどいダックスホッケー”を見てきた私ですが、正直、予想外の好スタートに少し浮かれていました。チームは「2026年にプレーオフ復帰!」と大胆な目標を掲げ、7年連続の不出場に終止符を打つ目標を掲げていました。
序盤の好スタートは、急な失速さえなければ、シーズン通して争い続ける力になるでしょう。
今回の“初めての本格的な逆風”は、むしろ彼らにとって良い経験になると思います。全試合で5点、6点、7点取れるわけではありません。相手チームも、この“空飛ぶような攻撃”6に対して対応し始め、若いスターたちにフィジカルなプレッシャーをかけてきます🏋️
守備面はまだ課題がありますが、長いホーム戦がこれから続くので、チームの継続力を示すチャンスでもあります。そしてゴーリーのルーカス・ドスタルは本物。彼の活躍が、チームに安定感をもたらしています。
本日行われたボストン・ブルーインズvs.アナハイム・ダックス戦のハイライト映像。開幕当初から躍動する若手の活躍でブルーインズを突き放した!
🔹シャークスも成長中
Q:サンノゼ・シャークスは「ひどいチーム」とは言えない状態になっています。開幕6連敗のあと、13試合中8勝と持ち直しています📈もう“リーグ最下位争い”の日々は終わったのでしょうか?
A:かつては“リーグ最下位争い”の常連でしたが、今は違います。再建を始めたチームとして“期待される成長”をしっかり見せています。これからの20試合で、本当にどれだけ前進しているのか、そしてリーグで尊敬を取り戻すまでの距離がどれくらい残っているのか、より明確になるでしょう。
ですが、マクリン・セレブリーニは毎試合“必見”レベルです。彼がウィル・スミスと見せるケミストリーは特別で、この二人のコンビは若さにも関わらず非常に完成度が高く、毎試合のプレーは必見です✨。
サンノゼ・シャークスvs.ユタ・マンモス戦のハイライト映像。セレブリーニのハットトリック、何度見ても素晴らしい!
(2026年ドラフト全体1位指名候補)ケビン・マッケナ争奪戦(=ドラフト上位争い)から完全に除外されるとは言いませんが、球団としては“その競争に加わる気はない”7とはっきり表明しています。サンノゼの周囲は「良い未来が来る」という希望から、「その未来は本当にやって来る」という確信へと変わり始めています。いくつかの“良い日”はすでに到来しています。
これからさらにベテラン選手が整理され、セレブリーニを中心に“本当の中核”を固めていく必要があります。しかし、彼らは昨季より明らかに競争力が増しており、ゴーリー陣も大幅に改善。ヤロスラフ・アスカロフはここ数試合、特に素晴らしい活躍を見せています。シャークスは確実に前進中なのです💪
🔹今後の展望と可能性
Q:最後の質問です。カリフォルニア3チームの今後の可能性について、以下の3つのシナリオを「最も起こりそうな順」に並べてください。
1.キングスがパシフィック首位で終える
2.ダックスがプレーオフに進む
3.シャークスが勝率5割を超える
A(エリック):私の予想として、最も現実的なシナリオは以下の順です。
1️⃣ダックスがプレーオフ進出
パリティ(リーグ全体の均衡)8があるため、プレーオフラインが下がる可能性もあります。もし94ポイントでワイルドカードに届くなら、アナハイムは残り試合で30勝23敗11OT負けならOK。勝率.555なら十分現実的です✨
2️⃣キングスがパシフィック首位で終える
L.A.の首位浮上は驚きでしたが、エドモントンの不振、またベガスはケガで主力を欠き、試合数も少なめです(ベガスは19試合消化で、パシフィック・ディヴィジョンでは最少)。キングスも上位争いには加わりますが、オイラーズやゴールデンナイツの方が“天井の高さ”では上。
これまで弱かった西のチームが上がっているので(ワイルドカード争いをしているシカゴ、シアトル、ユタ辺りか)、3チームともポイントを取りづらくなる試合も多く、最後まで気が抜けません🏒
3️⃣シャークスが勝率5割超え
これは実現したら大きな物語になりますが、アスカロフ(とアレックス・ネデルコビッチも少し)がさらに“試合を盗む”活躍9を続ける必要があります。
また、トレード期限でUFA選手を放出する可能性もあり、その一方で有望株がNHLに昇格して最初の経験を積む、あるいは既に少し経験した選手がさらに大きく成長する機会にもなるでしょう。安定性を欠くリスクもありますが。
カリフォルニアの3チームは、それぞれ異なる形で成長中。今後の動きから目が離せません👀 ぜひ、各チームの試合や注目選手に注目してみてください!
まとめ
今季のカリフォルニア勢は、それぞれが異なる形で存在感を示しています。キングスは堅実なスタイルで勝点を積み重ね、ダックスは初めての壁を乗り越えながら成長中。シャークスは若手のケミストリーと改善したゴーリー陣が前向きな流れを作っています。
予想外の展開が続く西海岸の動きから、今後も目が離せません🏒🔥

ここまで読んでくれて、サンキュー、じゃあね!
【註釈】
- NHLには公式ルールで、ホーム用とビジター用のユニフォームははっきり区別される“対照的なデザイン”でなければならないという規定がある。しかし、最近はリーグが「両チームとも濃い色のジャージ対決(color‑on‑color)」を積極的に取り入れるよう促していて、これは視覚的な鮮やかさやスタイルを重視した試み。
この試合、レッドウィングスもレンジャーズも、今シーズン限定のチーム100周年記念ジャージを着用しており、これが非常に色合いの濃い、鮮やかなデザインで普段以上に際立って見えていた。
とはいえ、このスタイルにはリスクもある。視認性はユニフォーム選びでも非常に重要で、照明やアイスの色、対戦相手のカラーなどによって、ユニフォーム同士のコントラストが見え方に大きく影響するとも言われている。
つまり、「color‑on‑color jersey」対決は見た目のインパクトを狙いつつも、”見やすさ・識別性”のバランスを取るのが難しい挑戦でもある、ということ。
↩︎ - 「We had a six‑pack last night. Of NHL games, I mean.」の“six‑pack”は、「6試合」があった、という意味合いの表現。英語で“six‑pack”と言えば、一般的にはビールなど6本入りセットを指す比喩だが、スポーツの文脈で使われるときは「6つ(6件・6試合など)のまとまり」を指すことがある。
例えば、NHLや他のスポーツのチームが「6試合のチケットパック(six‑game pack)」を販売する例もあり、これは“six‑pack of games”の言い回しと近い考え方である。
男性の体型を指して使われる場合もあり、例えば“He’s got a six‑pack”は腹筋の形(腹筋が割れていること)を言っていて、軽い性的・魅力的なニュアンスを込めて、体の引き締まった部分やセクシーさを褒める表現としても用いられることもある。
↩︎ - ロサンゼルス・キングスがGMにケン・ホーランドを迎えた際、一部ファンやメディアの間では「ディフェンス(ブルーライン)が悪化するのでは?」という懸念が出ていた。その理由は、ホーランドがオフシーズンの補強で、若手の成長より“年齢を重ねたベテラン”を優先したように見えるからである。
具体的には、キングスはヴラディスラフ・ガヴリコフ(以前の守備の柱)を残さず、代わりにブライアン・ダマリンとコディ・チェシーといった、実績はあるもののピークを過ぎたベテランディフェンダーと契約した。
こうした補強スタイルは、「長年はGM経験に優れるが、最新の給与キャップ下や若手育成の潮流にはあまり合っていないのではないか」という批判を招いている。さらに、ホーランド自身は就任後の記者会見でディフェンス戦力について「今は6人のディフェンダーで回す」と語り、すぐに若手全員を呼び戻すつもりはない可能性を示唆している。
↩︎ - サンノゼ・シャークスは再建期にあり、GMのマイク・グリエール体制下でドラフト資産を積極的に蓄えてきた。実際、彼らは1巡指名権を複数保有し、若手有望株(例えばマックリン・セレブリーニ)を中心にチームを再構築しようとしている。
このため、一部ファンやアナリストの間では、シャークスが試合で大敗を重ねても勝利よりも“高順位指名”を優先するタンク(意図的に負ける)戦略を採っているのではという声が出ている。
長期戦略としての再建を選ぶ一方で、彼らはドラフトを通じてチームの将来のコアを育てる構えを明確にしており、その“弱さ”は偶然ではなく計画的なものだと解釈されてきた。
↩︎ - 北米メディアは、このキングスの「ホームでは弱く、アウェイで強い」という奇妙な二面性を戦術・心理・環境面からいくつか解説している。
まず、NHL Insightは、ホームでの重圧が大きすぎて選手が自由にプレーできず、逆にアウェイでは「アンダードッグ」意識が高まり、集中力や緊張感が勝利を生んでいると指摘。さらに、長距離移動のスケジュールによってチームがアウェイで独自のルーティンを築き、それが“第二の本拠地”的な快適さを生んでいるという見方もある。
一方でThe Hockey Newsは、アウェイで支えになっているのはコア選手(ケヴィン・フィアラ、クイントン・バイフィールド、コーリー・ペリーなど)の落ち着いた存在感だと報じている。長旅を「疲れを言い訳にせず、むしろ集中の場として使っている」と分析されており、これはホームでは得られないアウェイ特有の精神的な強さにつながっているとのこと。
またThe Hockey Newsの別記事では、ホームでは守備のミスや立ち上がりの悪さが目立ち、防御面で安定しないことも指摘されている。
↩︎ - アナハイム・ダックスの攻撃力が「空飛ぶよう(high‑flying)」と評される背景には、若手コアとスピードを重視した非常にアグレッシブなスタイルがあると北米メディアは分析している。
ESPNは、彼らが今季平均ゴール数を大幅に伸ばし、5対5のプレーでも得点機会を作る頻度が昨季から大きく改善されていると指摘。特に「予想得点(expected goals)」や「高危険度(high‑danger)のシュート機会」の指標が向上しており、攻撃のクオリティが上がっている。
また、NHLのEDGEスタッツでも、メイソン・マクタヴィッシュやカッター・ゴーティエ、レオ・カールソンら若手フォワードが高速スケートや強力なショットを披露しており、チームの攻撃に勢いを与えている。
さらに、SSBCrack Newsなどは、クリス・クレイダーが高危険度シュート(high‑danger goals)をリードしている点に注目。これは彼らが単に“速く”攻めるだけでなく、質の高い得点チャンスを狙っていることの証拠でもある。
こうした若さ・スピード・得点力を兼ね備えた攻撃が、「空飛ぶ(高く翔けるような)」という表現で語られる所以である。
↩︎ - 北米メディア(特にオーナー発言や分析系)は、シャークスが「ケビン・マッケナ争奪戦(=将来性の高い若手選手をドラフトで獲得)」に本気で乗り出すつもりはない、という表明を非常に戦略的なものとして受け止めている。
PFSNは、オーナーのハッソ・プラットナーが「McKennaを狙う必要はない」「今の若いコアに十分な可能性がある」と語った点を報じており、これは単なるタンク(意図的敗北)ではなく、自信あるリビルド戦略だと分析。
また、Yardbarkerなど複数のメディアも、プラットナーが「No McKenna here now!(今はマッケナはいらない)」と明言したことを取り上げ、シャークス自身が無理にドラフト指名権を引き当てるのではなく、あくまで自前の若手(セレブリーニら)を軸に持続的な成長を狙っていると評価している。
さらに裏付けとして、The Hockey Writersはシャークスの再建過程で「若手フォワードは非常に有望だが、守備(ディフェンス陣)はまだ脆弱」という構造的な課題を指摘している。
このことから、メディアの見方としては「マッケナを無理に獲るよりも、既存の若いタレントを育てながら堅実な土台を築く方針」がオーナーおよびGMの中で支配的、という理解がされている。
↩︎ - NHLで言われる「パリティ(競争の均衡)」とは、チーム間の実力差が小さく、安定強豪よりも「勝敗や順位の変動」が起きやすいリーグ構造を指す。コミッショナーのゲーリー・ベットマンは、「経済制度(特にサラリーキャップと収益分配)」がこの競争力を支えており、どのチームも勝負できる土台があること、常にプレーオフ争いがもつれる点を“比類なき競争のバランス”として評価。
また、The Hockey Writersは、NHLの給与キャップが厳格であることで大企業や市場が小さいチームにも戦力を集めやすくなり、これが実力偏重になりすぎない健全な競争を生んでいると分析している。
加えて、最近のシーズンでは試合の決着が非常に接戦になる試合が増えており、「どのチームも勝つ/負ける可能性」が高い」という不確実性がファンを引きつける要素になっているという指摘もある。
↩︎ - 「steal more games」という表現が指すのは、シャークスのゴーリー、特にアスカロフ(+少しネデルコビッチ)が、非常に苦しい状況でも並外れたセーブ性能を発揮してチームを勝利に導くことを意味している。
北米の分析では、この「盗む(steal)」は単なる好セーブだけでなく、「ゴールズ・セイヴド・アブヴ・エクスペクテッド(GSAx)」という指標で測られることが多い。たとえばRaw Chargeは、「ゴーリーが予想より多くのゴールを防ぎ、その差(GSAx)が試合の得点差を上回ると、そのゲームは‘steal’(盗まれた勝利)とみなされる」と定義する。
さらに、あるゴーリー分析サイトでは“Stolen Games”という統計を使い、「非常に多くのショットや質の高い得点チャンスに直面しながらも、予想を超える働きでチームの勝利を支える試合」を「盗まれた試合」と定義している。
つまり、シャークスが勝率5割を超えるには、アスカロフが“ただ守るだけ”ではなく、「味方スケーターが崩されても彼が粘って得点を許さない」、いわば“チームの弱点をゴーリーひとりで補う”ような働きが必要だと北米メディアは見ている。
↩︎